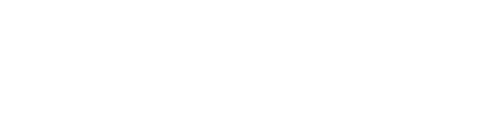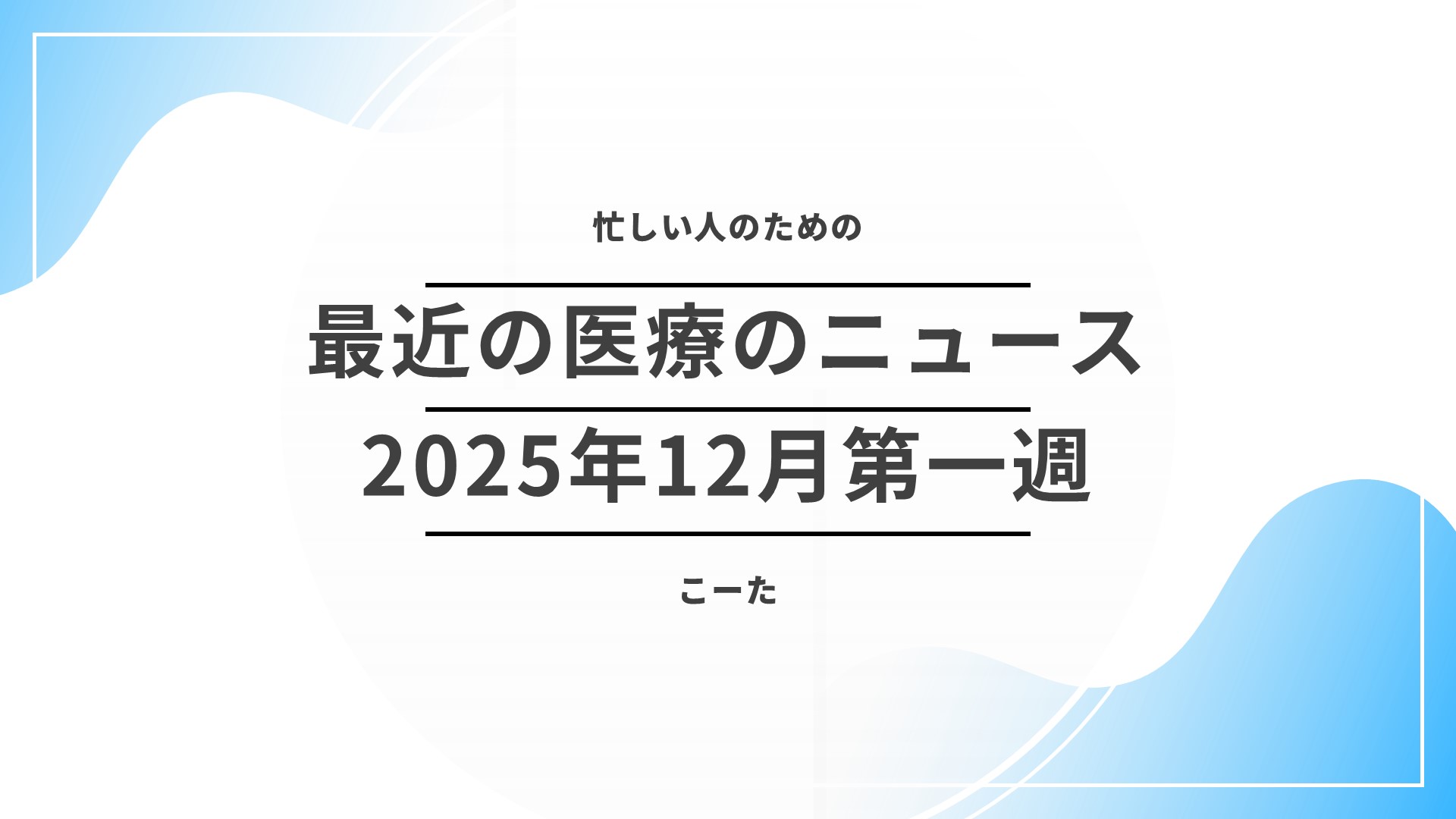はじめに
2026年度の診療報酬改定に向けた前哨戦が、いよいよ激しさを増しています。「一般病院の6割が赤字転落」という衝撃的なデータに加え、医師偏在是正や病床削減といった国による構造改革の波は、これまでの病院経営の常識を根底から揺さぶっています。
本記事では、日々多忙なビジネスパーソンや医療従事者の皆様に向けて、今週報じられた重要ニュースを厳選し、医業経営コンサルタントの視点でその背景と影響を解説します。
激動する医療業界の「現在地」と、生き残りをかけた「未来図」を、短時間で深く掴んでいただけます。
 Kota
Kota
35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。
9年間医療事務として外来・入院を担当。
毎月約9億円を請求していました。
現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。
投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。
趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。
Twitterはこちら
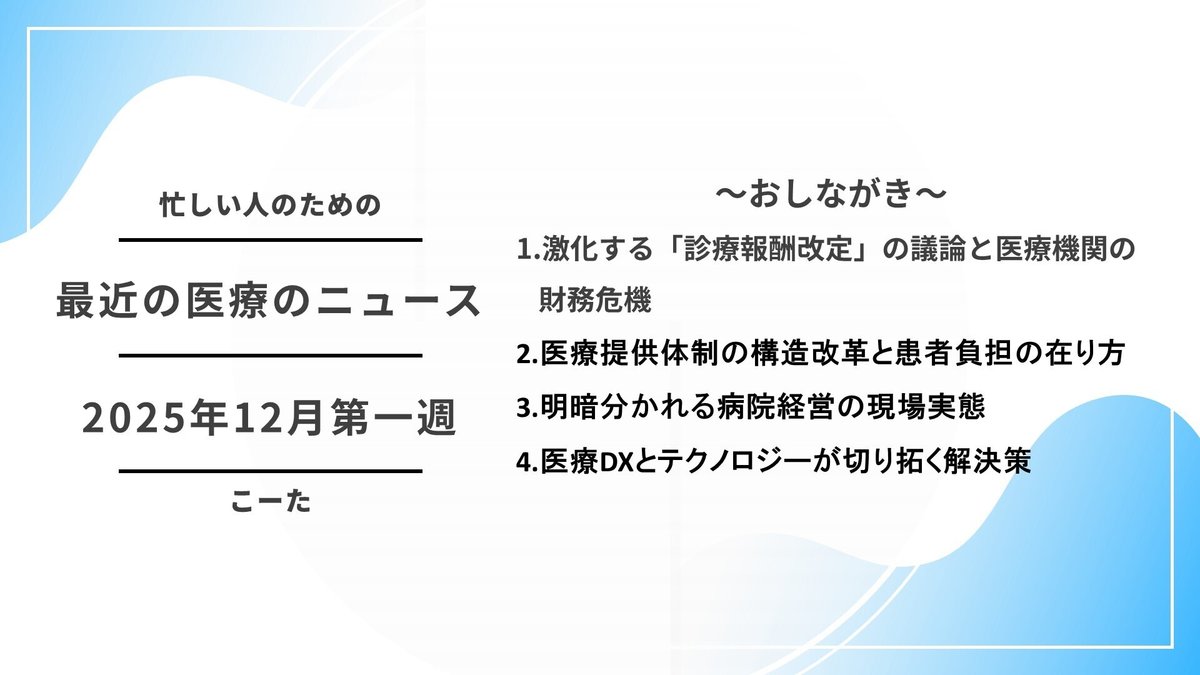
激化する「診療報酬改定」の議論と医療機関の財務危機
2026年度の診療報酬改定に向けた議論が、早くも熱を帯びています。
日本医師会をはじめとする医療関係団体は、昨今の物価高騰やスタッフの賃上げ原資を確保するため、診療報酬本体の「大幅なプラス改定」を強く求めています。
これに対し、財務省は慎重な姿勢を崩していません。彼らが根拠としているのは、診療所の経営状況です。
2024年度の診療所の利益率は4.8%の黒字と比較的堅調であるデータを盾に、「めりはりのある改定」すなわち全体の大幅な引き上げには難色を示しており、年末に向けて激しい攻防が続く見通しです。
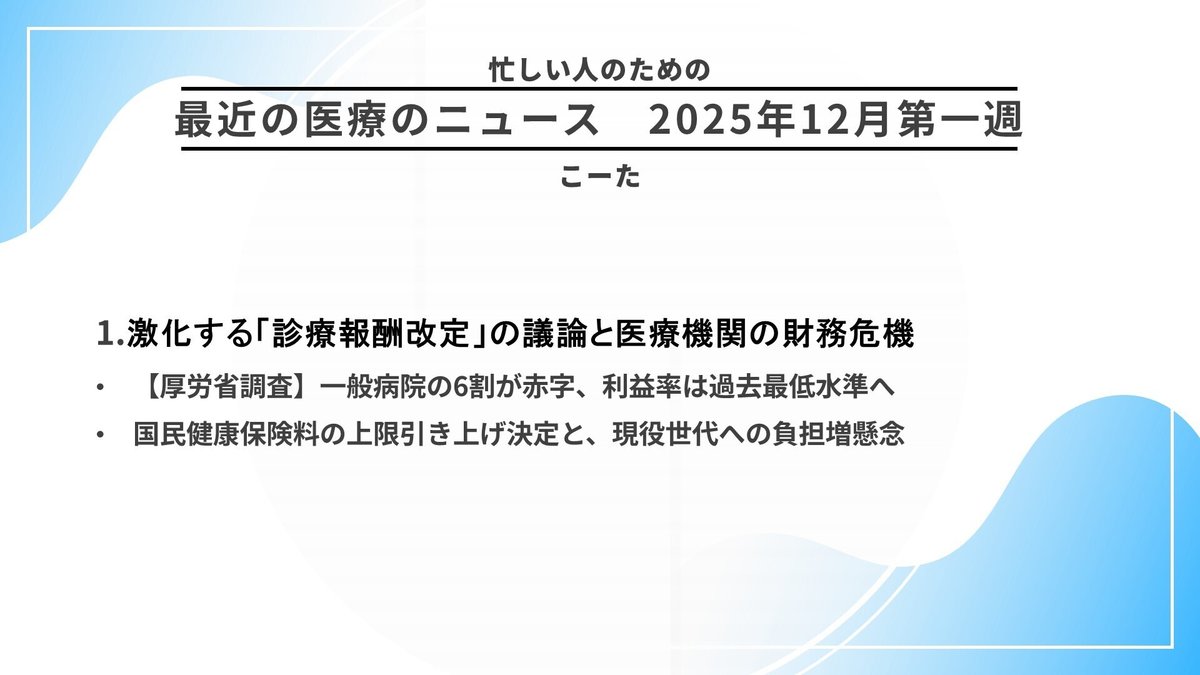
【厚労省調査】一般病院の6割が赤字、利益率は過去最低水準へ
財務省の主張とは対照的に、病院経営の足元は崩れかけています。
2024年度、一般病院の約6割が赤字に転落し、利益率は平均マイナス7.3%と、2019年以降で最低の水準まで悪化しています。
特に公立病院に至っては、利益率がマイナス18.5%という極めて厳しい数字が出ています。 特筆すべきは、医業収益自体は2.5%増加している点です。
収入が増えているにもかかわらず、給食材料費が6.0%増、水道光熱費が5.3%増と、コストの増加幅が収入増を遥かに上回っていることが、赤字の主因となっています。
この「収益は増えたが、利益は激減した」という事実は、現場の経営努力だけではカバーしきれない構造的なインフレの影響を如実に表しています。
一般企業であれば価格転嫁で対応する局面ですが、公定価格(=診療報酬)で縛られている医療機関にはそれができません。
病院団体が要求している「10%以上の引き上げ」という数字は一見過大に見えますが、マイナス7.3%という利益率を埋め合わせ、さらに将来の投資を行うためには、決して根拠のない数字ではないと言えます。もはや「経営改善」のレベルを超え、「地域医療インフラの維持」という視点での議論が不可欠です。
国民健康保険料の上限引き上げ決定と、現役世代への負担増懸念
診療報酬を引き上げれば、当然その財源が必要となりますが、その「財布」となる保険料の負担も限界に近づいています。
国民健康保険の年間保険料上限額について、2026年度から1万円引き上げ、110万円とする案が了承されました。上限額の引き上げはこれで5年連続となります。これは高齢化に伴う医療費増に対応するため、高所得者の負担を増やす狙いがありますが、現役世代の負担感は増す一方です。
財務省が診療報酬の大幅引き上げに反対する背景には、これ以上の国民負担増に対する強い懸念があります。
「医療機関の経営難」と「現役世代の負担増」は、完全にトレードオフの関係にあり、今回の改定議論でも最大の争点となります。
ただ単に「報酬を上げて解決」という単純な図式は、社会保険料の負担増を嫌う世論を考慮すると通用しづらくなっています。今後は、一律の引き上げを求めるだけでなく、「どの機能を持つ病院を救うのか」「効率化できる部分はどこか」という、医療機能の選別と集約化の議論が一層シビアにならざるを得ないでしょう。
経営者としては、単に改定を待つのではなく、自院が地域で不可欠なインフラであることをデータで証明できる体制づくりが急務となります。
医療提供体制の構造改革と患者負担の在り方
国は今、医療費の膨張を抑えつつ、限られた医療資源を効率的に配分するために、かつてないほど強い権限を行使し始めています。
「いつでも、どこでも、誰でも」という日本の医療のフリーアクセスが、制度面から大きな転換点を迎えていることを示唆するニュースが相次ぎました。
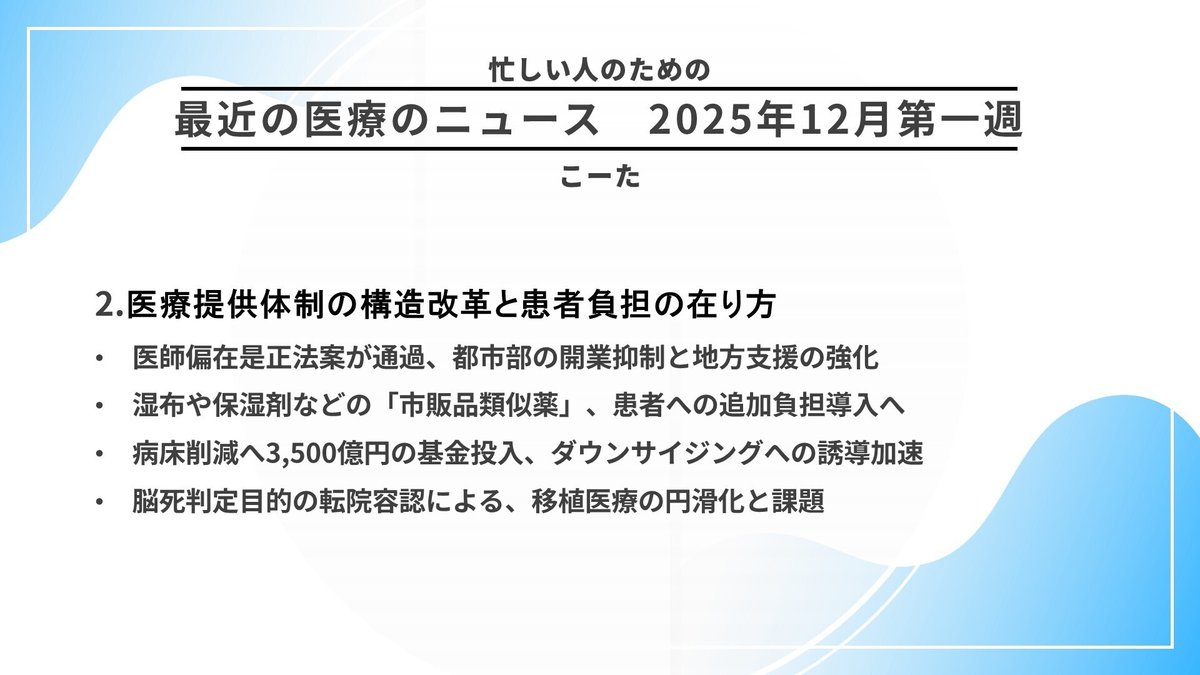
医師偏在是正法案が通過、都市部の開業抑制と地方支援の強化
医師の地域間の偏在を解消するため、政府はついに「開業の自由」への介入に踏み切ります。
医師偏在是正に向けた改正法案が衆院を通過しました。
この法案の目玉は、都市部などの医師多数区域における「新規開業の抑制」です。不足している医療機能を担うよう要請し、従わない場合には勧告や公表を検討するという強い措置が含まれています。
一方で、医師不足地域を「重点医師偏在対策支援区域」に指定し、手当の増額や事業承継の支援を行うという「アメ」の政策もセットになっています。
これは、これから開業を目指す勤務医の先生方にとって、極めて重大なゲームチェンジャーとなります。これまでは「駅前の好立地」などマーケティング視点だけで開業場所を選べましたが、今後は「そこでの開業が許可されるか」という規制リスクを考慮しなければなりません。
既存の開業医にとっては競合参入が減るメリットがある一方、地域医療全体で見れば、都市部のクリニックが高齢化し、新陳代謝が滞るリスクも孕んでいます。「どこで開業するか」という戦略が、これまで以上に経営の成否を分けることになるでしょう。
湿布や保湿剤などの「市販品類似薬」、患者への追加負担導入へ
薬局やドラッグストアで購入できる薬(=OTC医薬品)と同じ成分の処方薬について、患者負担の仕組みが変わろうとしています。
厚労省は湿布、保湿剤、解熱鎮痛薬など約7,000品目の「OTC類似薬」について、保険適用自体は維持しつつ、患者に新たな「追加負担」を求める方向で調整に入りました。
日本維新の会などは「保険適用からの除外」を求めていましたが、医師会や患者団体の強い反対もあり、完全な除外は見送られ、上乗せ徴収という折衷案に落ち着いた形です。
完全な保険除外(=10割負担)は回避されましたが、「病院で湿布をもらった方が安いから」という受診動機を抑制する効果は一定程度あるでしょう。 経営的な視点で見ると、整形外科や皮膚科のクリニックにとっては、軽症患者の受診控えによる患者数減少が懸念されます。
また、窓口での「追加負担」の計算や患者への説明という事務コストが増加することも避けられません。現場のオペレーションに混乱を生まないよう、受付スタッフへの教育やシステム対応の準備を早めに進めておく必要があります。
病床削減へ3,500億円の基金投入、ダウンサイジングへの誘導加速
「病院が多すぎる」という国の認識のもと、病床削減への圧力が強まっています。厚労省は入院ベッドを削減するための基金として、補正予算案に約3500億円を計上しました。
具体的には、病床を削減する医療機関に対し、1床あたり410万円の補助金を支給し、全国で約9万8千床の削減を目指します。
1床あたり400万円超という金額は、国がいかに本気で「病床のリストラ」を進めたいかという意思表示です。稼働率が低迷している慢性期病院や、人口減少エリアの病院にとっては、この補助金は「撤退戦」あるいは「ダウンサイジング」を成功させるための重要な原資になり得ます。
無理に空床を抱えて赤字を垂れ流すよりも、補助金を活用して身の丈に合った規模に縮小し、筋肉質な経営体質へ転換する。これは決して敗北ではなく、生き残るための高度な経営判断と言えるでしょう。
脳死判定目的の転院容認による、移植医療の円滑化と課題
日本の移植医療のボトルネックとなっていたルールが一つ緩和されます。
厚労省はこれまで原則認めていなかった「脳死判定のみを目的とした転院搬送」を容認する方針を固めました。 地方の小規模な病院などで、脳死の可能性がある患者が発生しても、人員や設備不足で正式な法的脳死判定ができないケースがありました。今回の変更により、高度な機能を持つ施設へ患者を搬送し、判定を行うことが可能になります。
これは医療現場の「役割分担」を明確にする動きです。
すべての病院が脳死判定という高度かつ精神的負担の大きい業務を担う必要はありません。 一方で、脳死状態に近い患者さんを搬送するというリスクの高い行為には、搬送元と搬送先の病院間での緊密な連携と信頼関係が不可欠です。今後は、地域の基幹病院と周辺病院との間で、こうした特殊なケースを想定したホットラインや連携フローの構築が求められることになります。
明暗分かれる病院経営の現場実態
病院経営を取り巻く環境が一様ではないことが、今週のニュースからも浮き彫りになりました。
医師不足やコスト高に耐えきれず機能不全に陥る病院がある一方で、大胆な働き方改革によって人材確保と質の向上を同時に実現する病院も現れています。「経営力の差」が、そのまま「地域医療の存続」に直結するシビアな局面に入っています。
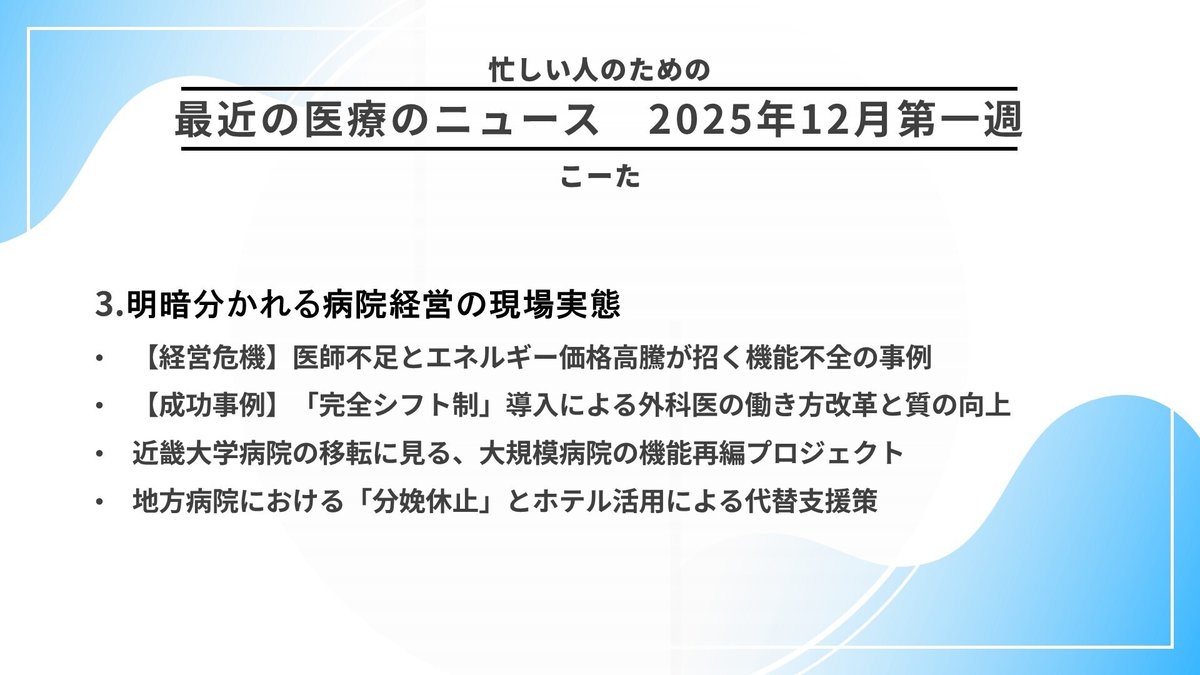
【経営危機】医師不足とエネルギー価格高騰が招く機能不全の事例
地方自治体が運営する公立病院でさえ、経営の維持が困難になっています。 静岡市立清水病院の事例は、まさに医療崩壊の危機的状況を象徴しています。
同病院は2024年度に約22億円という巨額の赤字を計上。節電のために「午後のエスカレーター停止」という異例の措置をとらざるを得なくなりました。
しかし、より深刻なのは「医師不足による減収」です。脳神経外科医が4人から1人に激減したことで、手術の受け入れを停止し、皮膚科も休診となりました。
また、富山県立中央病院も資金繰りが悪化し、金融機関などから約34億円を借り入れる事態となっています。
千葉県のたむら記念病院が閉院を決めたように、民間・公立問わず、限界を迎える施設が相次いでいます。
清水病院の「エスカレーター停止」は、節約効果以上に「この病院は危ないのではないか」という不安を患者や地域住民に植え付ける、強烈なネガティブメッセージとなってしまいます。
これを避けられなかった点に、現場の切迫感が滲み出ています。 根本的な問題は、光熱費などのコストカットではどうにもならない「医師引き揚げによる医業収益のダウン」です。
医師がいなければ、どれほど立派な設備があっても収益は生まれません。経営陣は「節約」よりも「医師のリクルート」に全精力を注ぐべきですが、一度悪評が立つと人材が集まらないという負のスパイラルに陥りやすく、公的資金による緊急輸血なしには再生が難しいフェーズにあると言えます。
【成功事例】「完全シフト制」導入による外科医の働き方改革と質の向上
暗いニュースの一方で、富山大学附属病院からは希望の持てる事例が報告されました。同病院の消化器外科では「完全シフト制」を導入し、長時間手術の途中交代や、夜間・休日の呼び出しゼロを実現しました。
外科医、特に大学病院の勤務医は過酷な長時間労働が常態化していましたが、この改革により女性医師が働きやすい環境が整い、所属医師25人中8人が女性となっています。
さらに、医師が集中力を保てるようになったことで、手術の合併症率が下がるなど、医療の質の向上という成果も出ています。
「外科医にシフト制は無理だ」「主治医が最後まで診るべきだ」という従来の精神論を、データとシステムで覆した画期的な事例です。
ここで注目すべきは、働き方改革が「医師の健康」だけでなく、「採用力」と「医療の質」の向上に直結している点です。若い世代の医師は、給与以上にQOL(=生活の質)や労働環境を重視して就職先を選びます。
富山大のように「人間らしい働き方ができる」というブランドは、今後、医師争奪戦において最強の武器となります。これは大学病院に限らず、民間病院でも模倣すべき生存戦略です。
近畿大学病院の移転に見る、大規模病院の機能再編プロジェクト
都市部では、大規模な病院移転という一大プロジェクトが完了しました。
近畿大学病院が大阪狭山市から堺市へ移転し、重症患者を含む125人の入院患者を一斉搬送しました。
車両38台、スタッフ500人を動員し、約4時間半かけてトラブルなく完了させた背景には、点滴の事前処理や食事時間の調整など、綿密な計画がありました。
病院の移転は単なる「引っ越し」ではなく、業務フローや組織文化をリセット・再構築する最大のチャンスです。 老朽化した建物では非効率だった動線を、新病院で一新することで、スタッフの動きや患者さんの利便性は劇的に変わります。
今回のスムーズな搬送劇は、新病院での運用がいかにシミュレーションされていたかの証左でもあります。建物が変わるタイミングで、運用もアップデートできた病院は、その後の経営効率が大きく改善します。
地方病院における「分娩休止」とホテル活用による代替支援策
「病院を残せない」地域では、民間サービスと連携した新しいインフラ維持の形が生まれています。
長野県立木曽病院が麻酔科医不足で分娩を休止することに伴い、近隣自治体とビジネスホテルチェーンのルートイングループが協定を結びました。妊婦とその家族が、分娩可能な病院の近くにあるホテルに無償で宿泊(最大14日間)できる仕組みです。
これは「地方から病院がなくなる時代」の現実解です。無理に医師を派遣して病院機能を維持しようとするよりも、患者さん(妊婦さん)の方を、医療資源のある場所に移動・滞在させる方が、安全性もコスト効率も高い場合があります。 医療機関単体で解決しようとせず、ホテルなどの異業種と連携して「アクセスの保障」を行うこのモデルは、分娩に限らず、透析や化学療法など、他の医療過疎地域での課題解決のヒントになるでしょう。
医療DXとテクノロジーが切り拓く解決策
人手不足が深刻化する医療現場において、デジタル技術はもはや「あると便利」なオプションではなく、医療崩壊を食い止めるための「ライフライン」になりつつあります。遠隔医療、AI、そしてデジタルデバイスの活用が、場所や時間の制約を取り払い始めています。
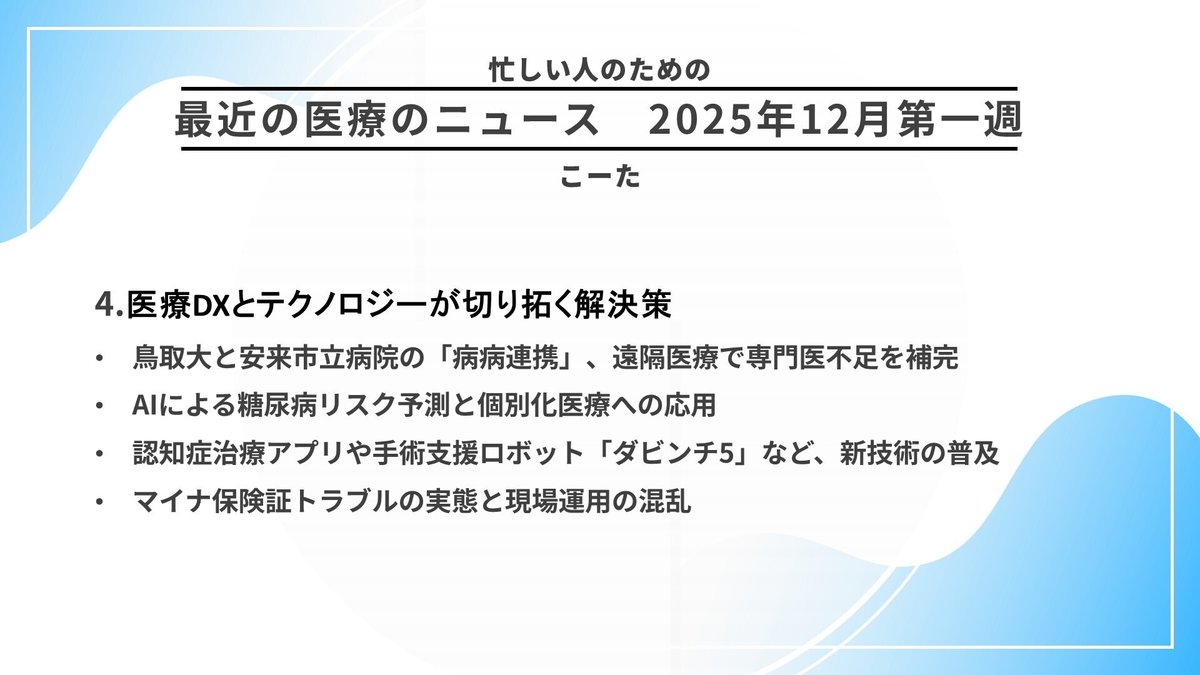
鳥取大と安来市立病院の「病病連携」、遠隔医療で専門医不足を補完
物理的に医師を派遣することが難しい地域で、新しい連携の形が始まります。
鳥取大学医学部附属病院と島根県の安来市立病院は、ウィーメックス社の遠隔医療システム「Teladoc HEALTH」を導入し、県境を越えた「病病連携」を開始します。
2026年4月の本格稼働を目指し、鳥取大の専門医が、遠隔地から安来市立病院の救急外来やカンファレンスに参加して助言を行います。医師そのものを派遣するのではなく、高精細な映像と音声をリアルタイムで繋ぐことで、あたかもその場に専門医がいるかのような環境を作り出し、現場の診療を支援します。
これまでの地域医療支援は「医師の派遣」が主流でしたが、医師の働き方改革が進む中、移動時間を要する派遣は限界を迎えています。今回のモデルは、医師の移動という「コスト」をゼロにしつつ、専門知という「価値」だけを届ける、極めて合理的な解決策です。
特に救急現場において、経験豊富な専門医の判断をリアルタイムで仰げることは、現場医師の精神的負担を大きく軽減し、医療安全の向上にも直結します。今後はこうした「知識の遠隔提供」に対し、適切な診療報酬上の評価がつくかどうかが普及の鍵となるでしょう。
AIによる糖尿病リスク予測と個別化医療への応用
AI(=人工知能)の活用は、画一的な治療から、個々の患者に合わせた「個別化医療」へとステージを進めています。
福島県立医科大学の研究チームは、AIを用いて糖尿病患者を5つのタイプに分類し、診断時に将来の合併症リスクを予測できることを明らかにしました。特に「重症インスリン抵抗性糖尿病」タイプは腎臓病リスクが高いなど、予後を見据えた早期介入が可能になります。 また、ガーミンジャパンもウェアラブルデバイスとAIを組み合わせた糖尿病マネジメントの提供を開始しました。
日常生活のデータをAIが解析し、運動や食事のアドバイスを行うことで、薬だけに頼らない治療を目指します。
これらは「予防」と「重症化予防」の質を劇的に変える技術です。従来の「悪くなってから治す」医療から、「リスクを予測して先回りする」医療への転換点と言えます。
経営的な視点で見れば、こうしたAI解析やデータ管理は、将来的に保険点数として評価される可能性があるほか、人間ドックのオプションなどの自由診療メニューとしての付加価値にもなり得ます。
データを活用して患者さんの健康意識を高めることは、結果として通院継続率の向上にもつながるでしょう。
認知症治療アプリや手術支援ロボット「ダビンチ5」など、新技術の普及
治療の選択肢も、デジタル技術によって多様化しています。大阪大学発のスタートアップが、2026年秋にも認知症治療アプリの治験を開始します。AIが患者の苦手な認知機能を特定し、重点的にトレーニングを行うことで改善を図る「デジタルセラピューティクス(DTx)」の一種です。
一方、ハードウェア面では、徳島県立中央病院が手術支援ロボットの最新鋭機「ダビンチ5」を四国で初めて導入しました。
触覚を執刀医に伝える新機能などが搭載されており、月額680万円でリース導入されています。
「アプリで治す」時代の到来は、製薬ビジネスだけでなく、病院経営にも変化をもたらします。アプリ処方は在庫スペースも不要で、管理コストが低い新たな収益源になり得ます。
一方で、ダビンチのような高額医療機器は、導入コストの回収計画がシビアに求められます。しかし、「最新機器がある」ことは、若手医師の研修先としての魅力や、患者さんからの信頼(集患力)に直結するため、単純な収支だけでなく「病院のブランド投資」としての側面も強く持っています。
マイナ保険証トラブルの実態と現場運用の混乱
DXの推進には痛みが伴うことも忘れてはなりません。
山口県保険医協会が行ったアンケートの結果は、現場の混乱を浮き彫りにしました。回答した医療機関の約77%が、マイナ保険証の資格確認で何らかのトラブルを経験しています。「名前の間違い」「機器エラー」などが頻発し、結局は従来の健康保険証で確認せざるを得ないケースが7割を占めました。
導入初期のトラブルはある程度想定されたこととはいえ、77%という数字は現場のオペレーションにとって看過できない負荷です。受付でのトラブル対応は、事務スタッフのストレス増大や、待ち時間の延長による患者満足度の低下に直結します。
政府は「一本化」を急いでいますが、現場レベルでは、システムが安定するまで従来の保険証も併用できる「安全網」を維持する運用が、現実的なリスクヘッジとして必要不可欠です。
クリニック経営者としては、スタッフがトラブル時にパニックにならないよう、マニュアル整備と「謝らなくてよい」という精神的なフォローをしておくことが重要です。
おわりに
財務省と医療現場の攻防、そして赤字病院の急増は、日本の医療システムが「持続可能性」を問われる限界点に達していることを示しています。
もはや、国からの救済を待つだけでは生き残れない時代に入りました。 しかし、富山大学の働き方改革や、鳥取大学の遠隔医療連携の事例が示すように、知恵とテクノロジーでこの壁を突破しようとする動きも確実に生まれています。
今、経営者や現場リーダーに求められているのは、制度変更を嘆くことではなく、変化を「自院を変革するトリガー」と捉え、行動に移すことです。今後も、皆様の意思決定の一助となる視点をお届けしていきます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!