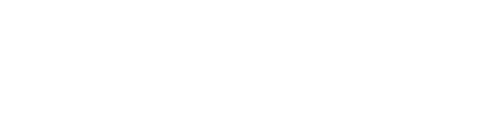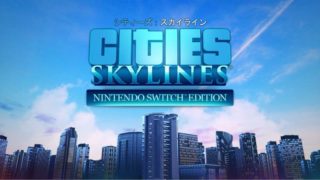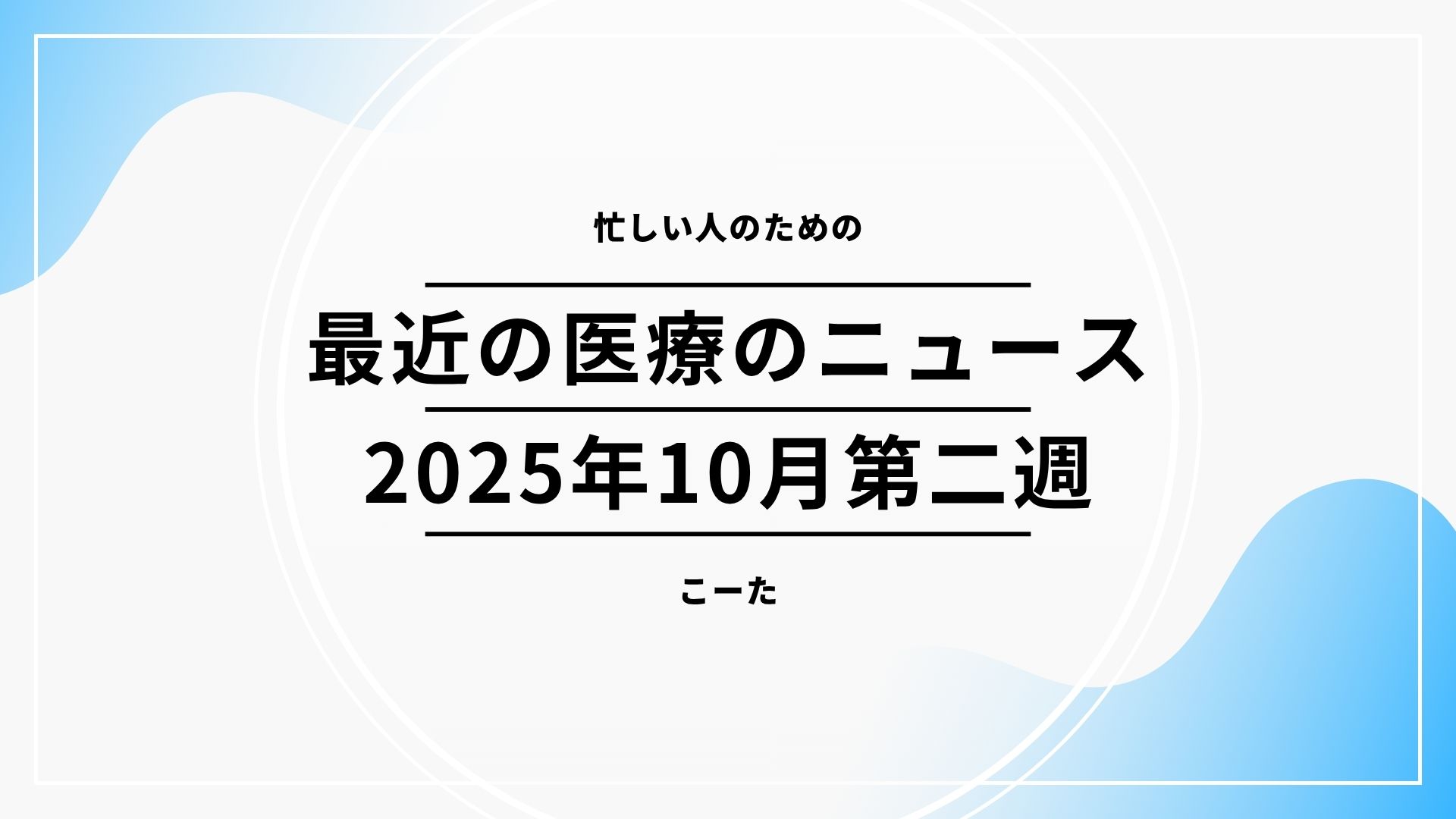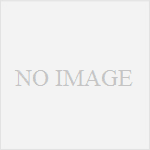はじめに
「最近、近所のクリニックが閉院した」「大きな病院の待ち時間がさらに長くなった」と感じることはありませんか?
実は今、日本の多くの病院が深刻な経営危機に瀕しています。
2024年度の調査では、実に61%もの病院が赤字に陥っているという衝撃的なデータが報告されました。これは、単に病院だけの問題ではなく、私たちの誰もが質の高い医療を受けられなくなる「医療崩壊」の序章かもしれません。
この記事では、日々忙しく情報を追うのが難しいビジネスパーソンや医療関係者の皆様に向けて、「なぜ病院経営はここまで厳しいのか?」という現状を最新ニュースから読み解き、解決の鍵となりうる「医療DX」の可能性について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
 Kota
Kota
35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。
9年間医療事務として外来・入院を担当。
毎月約9億円を請求していました。
現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。
投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。
趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。
Twitterはこちら
もはや限界?全国で深刻化する病院の赤字経営
全国調査で浮き彫りになった厳しい実態
2024年度の診療報酬改定が行われたにもかかわらず、病院経営の苦境は続いています。
福祉新聞によると、全日本病院協会の調査では経常利益が赤字の病院の割合は61%に達しました。特に、公立病院に絞るとその状況はさらに深刻で、共同通信の報道では、2024年度の公立病院事業全体の経常収支は過去最大となる3952億円の赤字を記録し、赤字病院の割合も過去最大の83%に達しています。
この背景には、歴史的な物価高騰や、職員の待遇改善に伴う給与費の増加があります。これらのコスト増が、診療報酬の伸びを上回ってしまい、病院経営を直接圧迫しているのです。
全日本病院協会の会長からは「地域医療は崩壊寸前だ」という悲痛な声も上がっており、もはや個々の病院の努力だけでは乗り越えられない、構造的な問題に直面していることがわかります。
地域の中核病院で相次ぐ経営問題
この経営悪化の波は、都市部・地方を問わず、地域医療を支える中核病院にも押し寄せています。
- 兵庫県では、神戸新聞の調査により、県内の公的病院の88%が赤字となり、黒字化を「不可能」「ほぼ不可能」と考える病院が74%に上ることが明らかになりました。
- 静岡県でも状況は同様で、静岡新聞によれば、赤字見込みの病院が約7割に増加。特に、救急医療などを担う高度急性期・急性期病院では81.6%が赤字を見込んでいます。
- 長野県松本市の相澤病院では、甲信越地方で唯一だった先進的ながん治療設備「陽子線治療センター」が、赤字続きのために来年3月末での休止を決定しました。
- 山梨大学付属病院では、物価高騰で建設費が当初の1.3倍に膨らんだ結果、新診療棟の建設延期を余儀なくされています。
これらの事例は、単なる赤字問題にとどまりません。最新の医療設備への投資が滞り、地域住民が必要な医療を受けられなくなる未来がすぐそこまで来ていることを示唆しています。
なぜ?病院経営を苦しめる「2つの構造的要因」
なぜ、これほど多くの病院が赤字に陥ってしまうのでしょうか。その背景には、医療業界特有の構造的な要因が存在します。
要因1:物価が上がっても値上げできない「公定価格」の壁
一つ目の要因は、医療サービスの価格である「診療報酬」が国によって一律に定められていることです。一般的な企業であれば、原材料費や人件費が上がれば、製品やサービスの価格に転嫁(値上げ)して利益を確保します。
しかし、病院はそれができません。医薬品や医療材料の価格、電気代やガス代が高騰しても、国が定める診療報酬はすぐには変わらないため、コスト増をすべて病院自身が吸収しなければならないのです。
静岡県の浜松医療センターでは、給与引き上げだけで人件費が約3億円も増加する見込みですが、その分を診療報酬で補うことは極めて難しいのが現状です。
要因2:地域医療を支えるほど赤字になる「ジレンマ」
二つ目の要因は、特に地域の中核病院が陥りやすい「地域医療を支えるほど赤字になる」というジレンマです。CBニュースに掲載された総合病院国保旭中央病院・野村統括病院長の寄稿によると、救命救急センターを持つ病院(93%)や400床以上の大規模病院(94%)ほど赤字割合が高くなっています。
これは、救急医療や小児科、産科といった、いわゆる「不採算部門」を維持するために多くの人員や設備を割いているためです。
不採算部門は、地域住民の命を守るために不可欠ですが、診療報酬上は利益が出にくい構造になっています。地域医療に貢献しようとすればするほど、経営が厳しくなるという矛盾を抱えているのです。
苦境を打破する鍵は「医療DX」?未来を拓く最新テクノロジー
この厳しい状況を打破する鍵として、今、大きな期待が寄せられているのが「医療DX(デジタル・トランスフォーメーション)」です。最新のAIやクラウド技術を活用し、医療現場の業務を効率化することで、経営改善と医療の質向上を両立させようという動きが加速しています。
AIが医療従事者の負担を劇的に減らす
医療現場は、患者さんのケア以外にも、問診やカルテ記録といった膨大な事務作業に追われています。ここにAI技術を導入する事例が急速に増えています。
- 問診・看護記録の自動化: 大阪国際がんセンターでは、日本IBMなどと協力し、AIアバターが患者の問診を行う「問診生成AI」や、看護師の会話を自動で要約・記録する「看護音声入力生成AI」の運用を開始しました。これにより、医療者の業務負担が最大で4割以上も削減されたという驚くべき成果を上げています。
- 受付業務のAIエージェント化: 富士通と米エヌビディアは、受付や問診、診療科の振り分けなどを自動で行う「ヘルスケアAIエージェント」の実証実験を進めています。これが実現すれば、患者さんの待ち時間短縮と、職員の負担軽減に大きく貢献することが期待されます。
これらの技術は、医療従事者を煩雑な事務作業から解放し、本来やるべきである「患者と向き合う時間」を生み出すための強力なツールとなり得ます。
自宅から病院までを繋ぐ「医療MaaS」という新たな挑戦
さらに、地域全体の医療を効率化する壮大な構想も始まっています。
神戸大学とアマゾン・ウェブ・サービス・ジャパン(AWSジャパン)は、次世代医療プラットフォーム「医療MaaS」の構築に向けた協定を締結しました。
これは、患者さんやスタッフといった「人」、検体や薬などの「モノ」、そして検査結果などの「データ」が、自宅から病院、さらには在宅ケアまで、クラウド上で切れ目なく繋がる仕組みを目指すものです。
例えば、交通手段が限られる地域の高齢者が自宅でオンライン診療を受けたり、地域内の複数の医療機関が患者情報をスムーズに共有したりすることが可能になります。
こういったことで、患者さんの利便性向上はもちろん、医療従事者の業務効率を飛躍的に高め、地域全体の医療リソースを最適化できると期待されています。
おわりに:私たちにできることは何か?
今回見てきたように、日本の病院経営は、物価高騰と公定価格という構造的な課題の中で、まさに危機的状況にあります。このままでは、地域医療が立ち行かなくなり、誰もが安心して医療を受けられる社会が失われかねません。
しかし、悲観してばかりもいられません。AIやクラウドといった医療DXの波は、この苦境を乗り越えるための大きな希望です。
テクノロジーの力で医療現場の生産性を向上させ、医療従事者がより専門性の高い業務に集中できる環境を整えることができれば、経営改善と医療の質向上を両立させる道筋は見えてくるはずです。
私たち一人ひとりが、こうした医療現場の現状に関心を持つこと。そして、医療機関自身が、旧来のやり方にとらわれず、変化を恐れずにDXのような新たな挑戦に踏み出すこと。その両輪が、日本の医療の未来を守るために今、求められています。
ここまでお読みいただきありがとうございました!