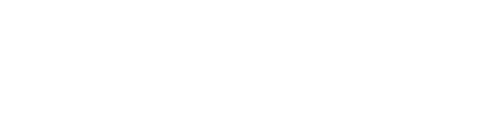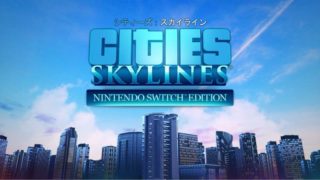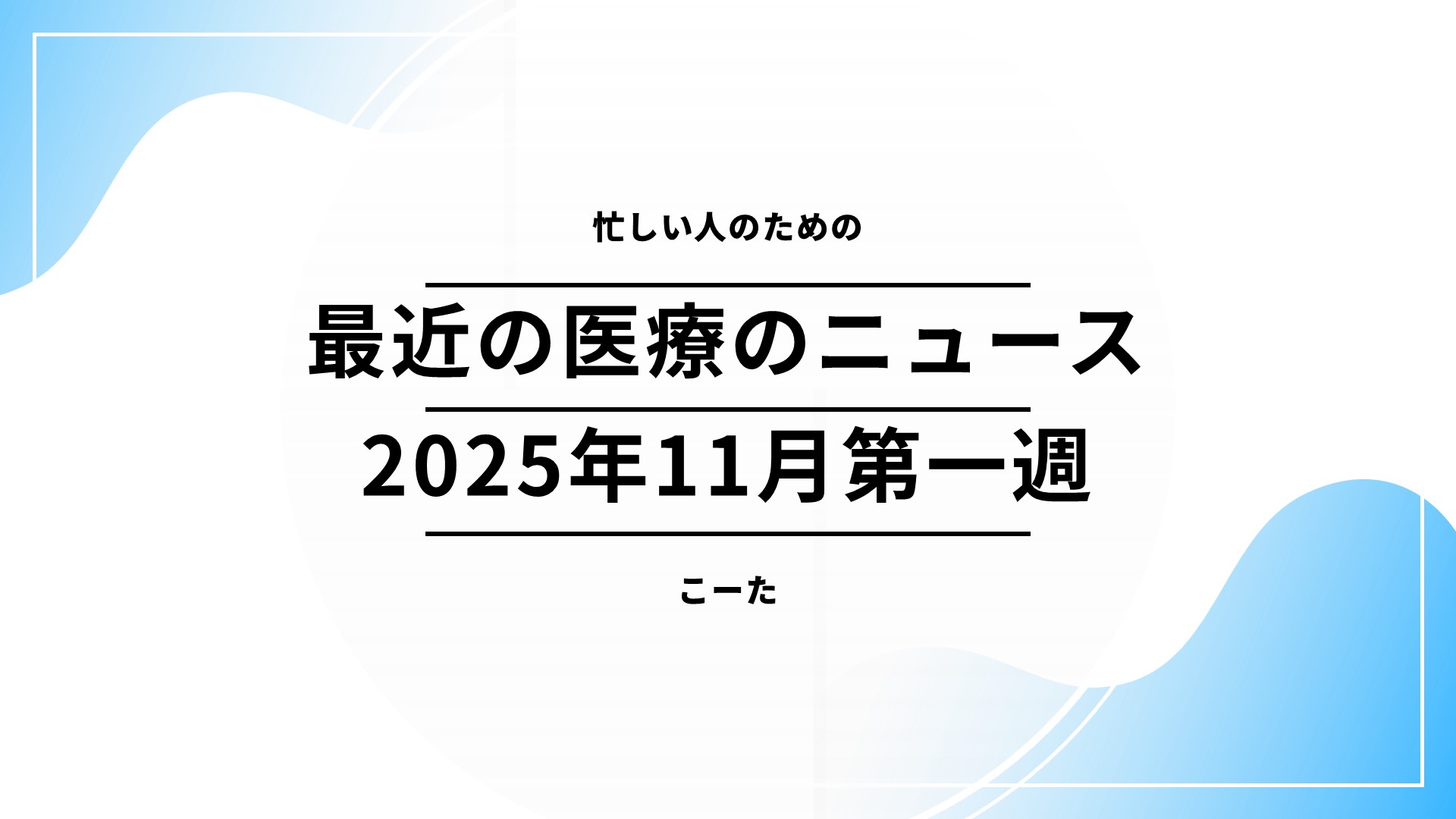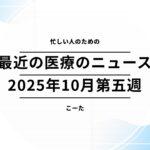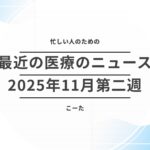- はじめに
- 医療制度・政策の最新動向
- 厳しさ増す病院経営と再編のリアル
- 加速する医療DXとAI活用の最前線
- 医師経験生かす「松本デジタル相」就任、マイナ保険証促進と医療DXに注力
- 災害拠点病院(岐阜)が独自アプリ「災害掲示板」を訓練で初運用、情報共有を迅速化
- 手術室の稼働状況をAIで可視化・最適化。SaaS「オペプロ」提供開始
- 富士通がAIで病院経営改善、病床稼働率向上で年10%の収入増見込む(長崎・壱岐市)
- 医療・製薬DX市場、2035年に1.3兆円規模へ。「AI創薬」が急成長を牽引
- 脳とAIを「生きたニューロン」で接続する新BCI技術、米スタートアップが開発
- AIによる子宮頸がんスクリーニング、低所得国での活用にインフラ整備の課題
- 韓国企業、サムスンソウル病院と共同で「ヒューマノイド型手術補助ロボット」開発へ
- 医療現場の課題と新たな取り組み
- 「医療・福祉業」で精神障害の労災認定が急増、2020年比で2倍に(過労死白書)
- 精神疾患の措置入院、自治体の8割が「退院後支援計画は必要」と回答
- 福島県立大野病院の後継病院、1階に外来・検査を集約し「患者の移動負担軽減」する設計案を採用
- 富山県上市町、骨粗しょう症予防で「誕生月ワンコイン検診」を開始
- 消化器外科医の若手確保へ、富山大学付属病院がクラウドファンディング活用
- 低体重(2.5kg未満)出生女性、子どもを産める期間が短い傾向。国立成育医療研が調査
- 欧米の「夏時間(サマータイム)」制度、年に2回の切り替えは健康に悪影響と科学者が警告
- 異種移植のブタ腎臓、移植後9カ月機能し「世界記録」と米病院
- 「京大卒」と経歴偽り無資格でがん治療の問診。クリニック院長を医師法違反容疑で逮捕
- ヘルスケア関連企業の戦略と動向
- おわりに
はじめに
今週も、高齢者の窓口負担増の検討開始、深刻化する病院経営の赤字問題、そしてAI活用による医療DXの急速な進展まで、将来を左右する重要なニュースが相次ぎました。
日々お忙しいビジネスパーソンや医療関係者の皆様にとって、こうした情報を詳しく追い、自院や自社への影響を分析するのは容易なことではないかもしれません。
この記事では、2025年11月第一週の主要な動向を厳選し、その背景と本質を分かりやすく解説していきます。
ぜひ最後までお付き合いください。
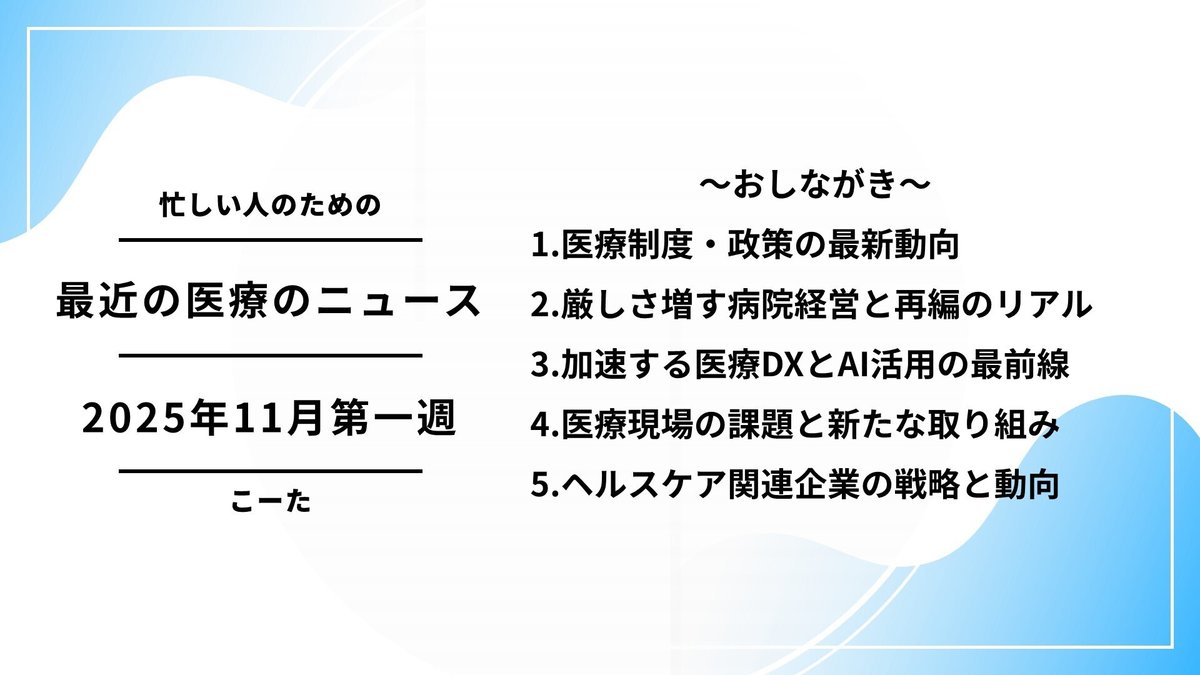
医療制度・政策の最新動向

高齢者の医療費窓口負担「3割」対象拡大へ、厚労省が本格検討
少子高齢化が進む中、現役世代の社会保険料負担の軽減が長年の課題となっています。
こうした背景から、厚生労働省は70歳以上の高齢者が医療機関で支払う窓口負担について、現在「現役並み所得者」に限られている3割負担の対象者を拡大する検討を本格的に始めました。
現行制度では、70~74歳は原則2割、75歳以上は原則1割負担ですが、所得に応じて2割や3割の負担が設定されています。
今回の検討は、自民党と日本維新の会が連立政権樹立の際に合意した「年齢によらない真に公平な応能負担の実現」という方針も後押ししています。
ただし、課題も山積しています。健康保険組合連合会(健保連)は、単純に3割負担の対象者を増やすだけでは、75歳以上の医療費の約4割を占める現役世代からの支援金が減らず、負担軽減につながらないと指摘しています。
また、3割負担の対象者を広げるために年収基準を引き下げた場合、「もはや『現役並み所得』とは呼べないのではないか」という懸念も厚労省幹部から示されています。
この議論は医療費の「総額抑制」ではなく、あくまで「負担の再配分」である点に注意が必要であると思っています。
現役世代の負担軽減をうたっていますが、健保連の指摘通り、財源構造全体、特に公費の割合などを見直さない限り、現役世代の実質的な負担感は変わらない可能性が残ります。
医療機関にとっては、負担割合の変更が患者さんの受診行動にどのような影響を与えるかを注視していく必要があります。
外国人等の国保保険料「前納」可能に、未払い防止で厚労省通知
外国人による医療費や国民健康保険(国保)保険料の未払いを防ぐため、厚生労働省は、市区町村が外国籍の人などに対して国保加入時に保険料を「前納」させることができるよう、関連条例の改正例などを盛り込んだ通知を全国の自治体に出しました。
早ければ2026年4月にも導入される可能性があります。
2024年末時点の調査では、国保加入者全体の納付率が93%であるのに対し、外国人の納付率は63%にとどまっており、制度の公平性確保が課題となっていました。
前納の対象者は、保険料を課す前年度の1月1日時点で日本国内に住民登録をしていない世帯主で、国籍による差別とならないよう日本人も含まれます。
導入する自治体では、最大1年分の保険料の前納を求めることが可能になります。
ただし、世帯人数が多く保険料が高額になる場合や、年度内の転出が予想される場合など、「特別の事情」があれば対象から外すこともできるとしています。
納付率の著しい低さ(全体93%に対し外国人63%)を鑑みると、保険制度の公平性と持続性を保つために一定の対策は必要であると思います。
ただし、運用面での配慮が求められます。
特に「特別の事情」の判断基準を各自治体がどう設定するかが焦点となります。
一律的な運用が、やむを得ない事情を抱える外国人等の生活を過度に圧迫しないような、現場での柔軟な対応が不可欠です。
出産費用、平均51.9万円で過去最高に。2026年度「自己負担無償化」に向け議論本格化
厚生労働省の発表によると、2024年度の正常分娩における平均出産費用は51万9,805円となり、前年度から1万3,265円増加し過去最高を更新しました。
物価高騰などが背景にあると見られます。
出産費用の更新によって、全国平均の出産費用が、現行の出産育児一時金(50万円)を上回る事態となりました。
地域差も大きく、最も高い東京都(64万8,309円)と最も低い熊本県(40万4,411円)では、約24万円の開きがあります。
政府は「骨太の方針」において、2026年度を目途に「標準的な出産費用の自己負担の無償化」を進める方針を明記しており、社会保障審議会では制度設計に向けた議論が本格化しています。
平均費用が一時金を上回ったことで、無償化への圧力は一層高まる可能性あります。
注目すべきは「無償化」の具体的な手法です。単に一時金を引き上げるだけでは、それに合わせて出産費用も上昇するという「いたちごっこ」を繰り返す懸念が残ります。
議論されているように、標準的な費用を国が定めてその範囲内を無償化し、個室代や特別なサービスなどは自己負担とするといった、費用の「見える化」と「標準化」がセットで進むかがポイントだと考えています。
ケアマネジャー資格の「更新制」廃止へ、厚労省が担い手確保に向け要件緩和案
介護サービスの「かなめ」役であるケアマネジャー(介護支援専門員)の担い手不足が深刻化する中、厚生労働省は社会保障審議会で、資格の「更新制」を廃止する案を示しました。
現行制度では5年に1度の研修受講が更新の条件ですが、これが現場のケアマネジャーの大きな負担になっているとの指摘がありました。
更新制を廃止した後も定期的な研修は必要としつつ、5年間で分割して受講できるなど、柔軟な運用を目指すとしています。
さらに、担い手を増やすため、資格取得に必要な実務経験を現行の5年から3年に短縮する方針や、実務経験の対象となる国家資格に救急救命士や公認心理師など新たに5資格を加える方針も示されました。
厚労省は年末までに議論をまとめ、来年の通常国会に関連法の改正案を提出したい考えです。
ケアマネジャーの不足は、医療と介護の連携、すなわち地域包括ケアシステムの根幹に関わる問題であり、担い手確保は急務です。
更新制廃止や実務経験短縮は、現場の負担軽減と門戸拡大に直結するため、一定の効果が見込めると思われます。
しかし一方で、ケアマネジャーには医療と介護をつなぐ高度な知識と調整能力が求められます。
今回の緩和策と並行して、質の担保をどう図るのか、例えば定期研修の内容をより実践的なものに刷新するなど、具体的な仕組み作りが今後の焦点になると考えられます。
「時給は最低賃金以下」医師らが診療報酬「10%以上」の引き上げ求め集会、経営難訴え
「このままでは地域の医療機関がつぶれてしまう」――。
物価高騰や人件費の上昇が続く中、全国保険医団体連合会(保団連)が主催する集会が開催され、全国から集まった医師らが深刻な経営状況を訴え、診療報酬の大幅な引き上げを求めました。
厚労省のデータ分析でも、病院の経常利益率はマイナス0.2%と赤字に転落し、特に一般病院では赤字割合が50.8%と半数を超える厳しい実態が示されています。
集会では、「職員の給与を確保するため自分の給与を削っている」といった医師の声や、「私の時給は最低賃金以下だ」という歯科医師の切実な意見も紹介されました。
この危機的状況に対し、保団連は2026年度の診療報酬改定で、基本診療料を中心に「少なくとも10%以上」の引き上げを行うことなどを求めるアピールを採択しました。
病院の半数が赤字というデータは、地域医療の持続可能性に対する強い警告と言えます。
特に、診療報酬本体と、物価高騰や他産業に追随する賃上げといった外部要因によるコスト増との間に生じたギャップが、経営を直撃しています。
現場から「10%以上」という具体的な数字が出たことは、それだけ危機感が強い表れです。
2026年度の次期改定で、このコスト増をどの程度補填できるかが、医療提供体制を維持できるかどうかの分水嶺になる可能性があります。
厳しさ増す病院経営と再編のリアル

近畿大病院、新病院へ移転。入院患者125人を4時間半で一斉搬送
大阪府南部の中核医療機関である近畿大学病院が、老朽化に伴い堺市南区の新病院へ移転しました。
11月1日には、人工呼吸器が必要な重症患者17人を含む入院患者125人の一斉搬送が「移送作戦」として実行され、医師や看護師ら約500人態勢のもと、約4時間半で無事完了しました。
新病院での外来診療は11月6日から開始される予定です。
病院の移転は単なる「引っ越し」とは全く異なります。
患者さんの安全を最優先しながら、医療機器やスタッフ、情報システムまで全てを動かす、病院の総合的な危機管理能力が問われる一大プロジェクトです。
移送対象を当初想定の190人から125人に絞り込み、安全に完遂させた計画性は、同様の課題を抱える病院にとって重要な参考事例となります。
赤穂市民病院、赤字体質改善へ2027年春から「公設民営」に移行
兵庫県赤穂市は、恒常的な赤字体質が続く市民病院の経営形態を、2027年春から「公設民営」へ移行すると発表しました。
2024年度決算で約14億円の単年度赤字を計上しており、このままでは赤字が続く見込みです。
交渉先は、市内のもう一つの中核病院を運営する医療法人「伯鳳会」が予定されています。
「公設民営」化は、自治体病院が赤字体質から脱却する選択肢の一つであると思います。
「公立」としてのインフラや地域医療の責務を残しつつ、民間の効率的な運営ノウハウを導入するのが主な目的です。
経営難の沼田病院(群馬)、医療機能を地域6病院が継承する方向で調整
経営悪化により医療機能の維持が難しくなっている群馬県の国立病院機構沼田病院について、その機能を利根沼田地域の他の6病院が引き継ぐ方向で調整が進められることが決まりました。
「感染症」や「へき地医療」、「救急」「災害」「がん」など、沼田病院が担ってきた機能を6病院で分担する形です。
今後は、機能を引き継ぐために必要な支援策を国や県に求めていく方針です。
これは一つの病院の機能を地域全体で分担する「機能の集約化・ネットワーク化」の典型的な例です。
一つの病院で全ての機能を維持するのが困難な中、各病院が強みを持ち寄って地域医療を守るという、まさに地域医療構想が目指す姿とも言えます。
ただし、機能を引き継ぐ側の病院にとっては、新たな設備投資や人員確保が必要となり、負担が増加します。
国や県からの十分な財政的・人的支援がなければ、共倒れになるリスクもはらんでおり、今後の支援策の具体化が成功の鍵となります。
久留米中央病院(福岡)、運営法人が破産手続き開始。負債13億円
福岡県久留米市の「久留米中央病院」(61床)を運営していた医療法人「いたの会」が事業を停止し、破産手続きの準備に入ったことが明らかになりました。
負債総額は約13億2,485万円(2023年8月時点)にのぼります。
同院は肝臓がん専門病院として始まり、近年は内科やリハビリ科を運営していましたが、コロナ禍での受診控えなども響き業績が低迷し、2025年8月の理事長の急逝後、閉院していました。
資材高騰で新築費用が167億円→271億円に。昭和伊南総合病院(長野)が県に支援要請
長野県上伊那地域南部の基幹病院である昭和伊南総合病院(239床)は、開業42年が経過し老朽化が進む中、新病院の建設計画を進めています。
しかし、おととし約167億円と見込まれた事業費が、建築資材の高騰などにより約271億円まで増加しました。
運営する伊南行政組合(4市町村で構成)は、県に対して財政支援を要請しました。
これは全国の病院建て替え計画に共通する深刻な問題です。
わずか1~2年で事業費が100億円以上も跳ね上がる事態は、多くの病院にとって「想定外」のレベルを超えています。
病院の建て替えは、単に建物を新しくするだけでなく、最新の医療機器導入や感染症対策といった医療の質・安全の向上に不可欠です。
このコスト高騰が続けば、必要な設備更新を断念・縮小せざるを得ない病院が全国で続出する懸念があります。
兵庫県、県立3病院で計130床を一時休止へ。物価高騰・受診控えで経営悪化
兵庫県は、県立病院の赤字が続いている状況を受け、病床稼働率が低い3病院(加古川医療センター、淡路医療センター、がんセンター)の一部病棟を一時的に閉鎖し、計130床を休止すると決定しました。
物価高騰や人件費の上昇に加え、コロナ禍以降の受診控えも重なり、県立10病院の経常損益は2023年度で91億円、2024年度は128億円の赤字でした。
これは経営悪化に対する「止血」のための施策です。
たとえ空床だったとしても、一定の看護師配置や光熱費などの固定費が発生し続けます。
稼働率が70%台にとどまる病棟を一時的に「休床」し、スタッフを他の多忙な部署へ再配置するのは、赤字を食い止めるための合理的な経営判断です。
コロナ禍を経た「受診控え」が慢性化している可能性も示唆しており、需要回復を待つだけでなく、供給を適正化する動きが今後も広がる可能性があります。
富山国保病院(千葉)、住民団体の6割超が「存続・充実」を求め市に訴え
千葉県南房総市立富山国保病院の運営方針を巡り、住民団体がアンケート結果をもとに、公立病院としての存続を市に訴えました。
アンケートでは回答者の6割以上が「必要な診療科が近くにない」といった医療への困り事を抱えており、病院の将来像については65%超が「存続・充実」を求めました。
通院手段の9割が自家用車であることから、将来運転できなくなることへの不安も示されています。
これは「経営効率化を進めたい行政」と「身近な医療アクセスの維持を望む住民」との間で生じる典型的な摩擦です。
回答者の67%が65歳以上で、通院手段が自家用車に依存している現状では、病院の存続は生活の安全保障そのものであると思います。
2023年に統合案が一度白紙撤回されている経緯もあり、市側が「存続・充実」以外の選択肢を提示する場合は、自家用車に頼らない通院手段の確保や、訪問診療・オンライン診療体制の強化といった「代替アクセス」を具体的に示さなければ、住民の理解を得ることは難しいと考えられます。
加速する医療DXとAI活用の最前線
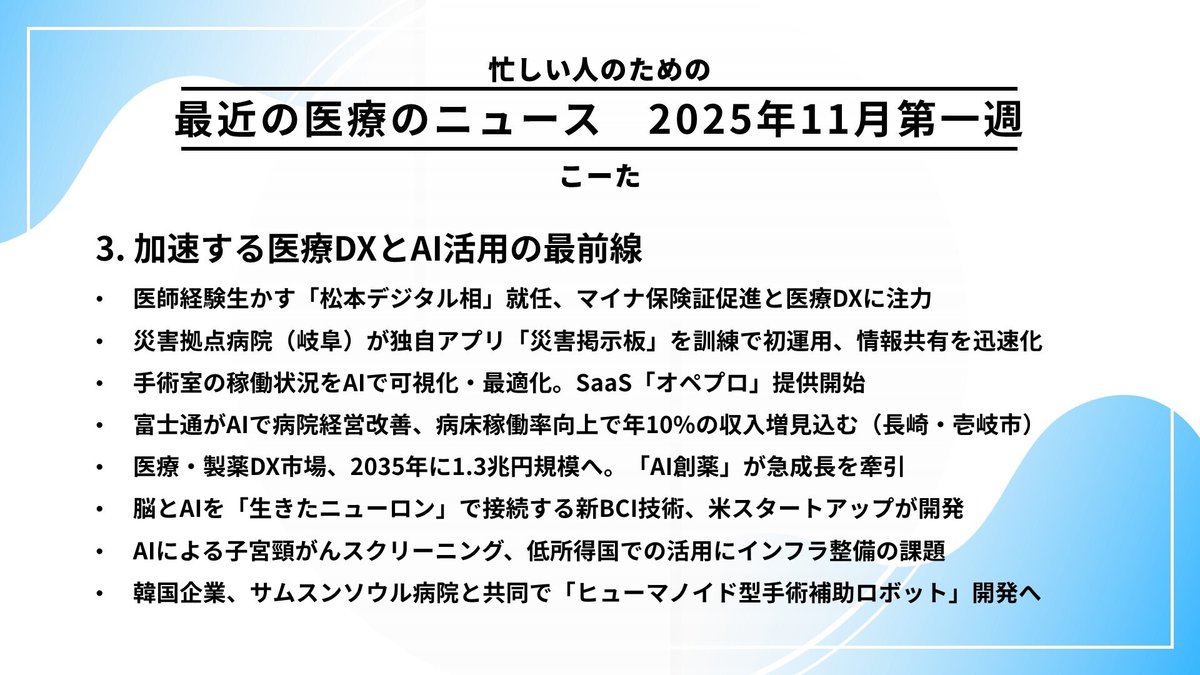
医師経験生かす「松本デジタル相」就任、マイナ保険証促進と医療DXに注力
医師の資格を持つ松本尚氏がデジタル大臣に就任し、その経験を活かして医療分野のDXに注力する考えを示しました。
喫緊の課題として「マイナ保険証」の利用促進を挙げ、医療機関でのデータ共有が進むことで、診療時間の短縮や医師と患者の対話時間の増加につながる可能性に言及しています。
また、松本氏はデジタル化への不安やためらいに対し「ひとつひとつを解きほぐすように説明するのが仕事」と強調しました。
さらに、医療データの利活用が日本の創薬力回復や経済成長にもつながるとして、活用のハードルを下げたいとの意向も示しています。
医療現場の実態を知る医師がデジタル政策のトップに立ったことは、大きな意味を持つ可能性があります。
特に、現場の医療機関が感じているマイナ保険証導入への負担や不安に対し、「解きほぐすように説明する」という姿勢は重要です。
ただし、データ利活用については、国や産業界が期待する「経済成長」といった視点と、医療現場が直面する「日々の業務負担」とのバランスをどう取るかが、施策の浸透における最大の鍵となると思われます。
災害拠点病院(岐阜)が独自アプリ「災害掲示板」を訓練で初運用、情報共有を迅速化
岐阜県笠松町の災害拠点病院である松波総合病院で、大規模地震を想定した災害訓練が行われました。
今回の訓練では、迅速な情報伝達のために病院が独自開発したアプリ「災害掲示板」が初めて運用されました。
このアプリは、搬送された患者の症状の重さによって治療優先度を決める「トリアージ」の結果や患者情報を、スマートフォンを使ってリアルタイムで院内全体に共有する仕組みです。
同病院の医師は、患者情報の一覧化が即座にでき、患者数、重症度、必要な処置がわかるため、救命率の向上につながるとコメントしています。
災害時の混乱した現場では、情報伝達の遅れや錯綜が、そのまま救えるはずの命を救えない事態に直結します。
従来のような紙やホワイトボードでの情報集約には限界があり、このようなデジタルツールで「患者数、重症度、処置状況」をリアルタイムに一覧化できる意義は非常に大きいと言えます。
病院が「独自開発」したという点も、現場のニーズに即している証拠であり、他の災害拠点病院にも広がる可能性のある優れた取り組みです。
手術室の稼働状況をAIで可視化・最適化。SaaS「オペプロ」提供開始
国内の急性期病院において、手術室の稼働率が平均6割程度にとどまっているという経営課題に対し、AIを活用した手術予定管理SaaS「オペプロ」が正式に提供開始されました。
従来、各診療科が紙やExcelで個別に管理し、ブラックボックス化しがちだった手術予定を、医師がiPadから統一フォーマットで入力・可視化し、リアルタイムで共有できます。
AIは蓄積されたデータをもとに稼働状況や医師の負担を分析し、空き枠の再割り当てなどを提案。
実証実験では手術室稼働率の改善効果が確認されています。
手術室は病院にとって大きな収益源の一つであると同時に、人・モノ・金が集中する部門です。
「稼働率6割」というのは、逆に言うと高価な設備と専門スタッフが4割の時間、遊休状態にあることを意味し、経営上の大きなボトルネックとなっています。
このツールは、属人的な「勘と経験」で行われていた手術枠の調整をデータに基づいて最適化するもので、病院経営の改善と医師の負担軽減を両立させるDXの好事例と言えるでしょう。
富士通がAIで病院経営改善、病床稼働率向上で年10%の収入増見込む(長崎・壱岐市)
富士通が、長崎県壱岐市の社会医療法人玄州会が運営する病院で、AIを活用した経営改善システムを導入し、成果を上げたと発表しました。
このシステムは、患者さんの重症度や状態に応じて最適なベッド割り当てを行ったり、入院期間をAIが予測したりします。
この取り組みにより、一般病棟の病床稼働率を従来の70%から90%に引き上げ、年間約10%の収入増加が見込める体制を整備したとのことです。
富士通はこのシステムを2026年中に国内の他の病院にも展開する方針です。
「病床稼働率」は病院経営の最重要指標の一つであり、稼働率70%から90%への改善は、経営インパクトが極めて大きいものです。
このシステムの本質は、従来、ベテランの看護師長や病棟クラークの経験知に頼っていた「ベッドコントロール」業務を、AIで客観的にサポートする点にあります。
入院期間を正確に予測できれば、退院支援や次の入院患者さんの受け入れ準備を前倒しで進められ、結果として病床の回転が速まります。
全国の病院の約7割が赤字とされる中、こうしたDXによる経営効率化は、地域医療を維持するために不可欠な手段となりつつあります。
医療・製薬DX市場、2035年に1.3兆円規模へ。「AI創薬」が急成長を牽引
富士経済の調査によると、医療・製薬DX関連の国内市場が急拡大し、2035年には1兆3,511億円(=2024年比 約90%増)に達する見込みであることがわかりました。
現在は電子カルテなどの医療情報プラットフォームが市場の中心ですが、今後は「クラウド型電子カルテ」への移行や、サイバーセキュリティ対策の需要が加速すると見られます。
特に市場の急成長を牽引すると予測されているのが「AI創薬支援システム」で、2024年比で57.1倍(2,000億円規模)という驚異的な伸びが見込まれています。
研究費や施設規模に依存せず創薬できる点が支持されているようです。
病院経営の視点で注目すべきは「クラウド型電子カルテ」の拡大です。
高額なサーバーを院内に設置・管理する従来のオンプレミス型からの移行を意味し、初期コストの低減やセキュリティ管理の外部委託といったメリットが期待できます。
一方で、「AI創薬」の爆発的な伸び予測は、従来莫大な時間とコストを要した新薬開発のプロセスが、AIによって根本的に変わろうとしていることを示唆しています。
脳とAIを「生きたニューロン」で接続する新BCI技術、米スタートアップが開発
脳とコンピューターを接続するBCI技術において、米国のスタートアップ企業サイエンス社が画期的なアプローチを開発しています。
従来、脳の情報を高密度で読み取るには電極を脳に挿入する必要があり、脳を傷つけるという大きな制約がありました。
同社の「バイオハイブリッドBCI」は、電極の代わりに「生きたニューロン」を搭載したデバイスを脳の表面に置き、移植ニューロンが脳組織と自然に結合することを目指すものです。
マウス実験では、この移植ニューロンを経由してマウスの行動に影響を与えるなど、双方向の通信が可能であることを示しています。
AIによる子宮頸がんスクリーニング、低所得国での活用にインフラ整備の課題
子宮頸がんのスクリーニング受診率は、高所得国と低所得国の間で大きな差があります。
この格差を埋めるため、ケニアの農村部で、AI支援型の子宮頸がん細胞診スクリーニングシステムを導入する試みが行われました。
現地の医療スタッフが検体画像をデジタル化し、クラウド経由でAI分析と遠隔地の専門家による検証が行われました。
結果として、技術的には実現可能であったものの、試薬の供給停滞や品質不足、停電といった現地のインフラ問題が、診断の精度を制限する大きな壁となったことが報告されました。
高度なAI診断技術も、それを使う現地の「土台」がなければ機能しないことを示す重要な報告だと思います。
医療技術の格差解消において、最新のAIツールを提供する「空中戦」だけでなく、安定した試薬供給ルートの確保、電力の安定供給、高速な通信網といったいわゆる「地上戦」がいかに不可欠であるかを示しています。
AIの導入は、単なるツールの導入ではなく、現地の医療システム全体の強化とセットで考える必要があります。
韓国企業、サムスンソウル病院と共同で「ヒューマノイド型手術補助ロボット」開発へ
韓国のロボット企業レインボーロボティクス社が、政府の大型研究開発プロジェクトに選定され、サムスンソウル病院などと共同で「手術補助ロボット」の開発に着手しました。
このプロジェクトが目指すのは、手術室での反復的な作業や精密な作業を補助できる、ヒューマノイド型のロボットシステムです。
「フィジカルAI」という技術を活用し、単にプログラムされた動きをするだけでなく、手術の状況をリアルタイムで認識・予測し、自律的に医療スタッフを補助することを目指しています。
「ダヴィンチ」などの現在の手術支援ロボットは、主に医師が遠隔操作する「マニピュレータ」として機能します。
しかし、この韓国のプロジェクトは、手術の文脈を読んで「自律的に動く」補助ロボット、いわば「賢い第3の手」や「もう一人の助手」を作ろうとするものであり、目指すレベルが一段階異なります。
これが実現すれば、手術の安全性向上はもちろん、長時間の手術における医師やスタッフの疲労軽減にも大きく貢献することが期待されます。
医療現場の課題と新たな取り組み
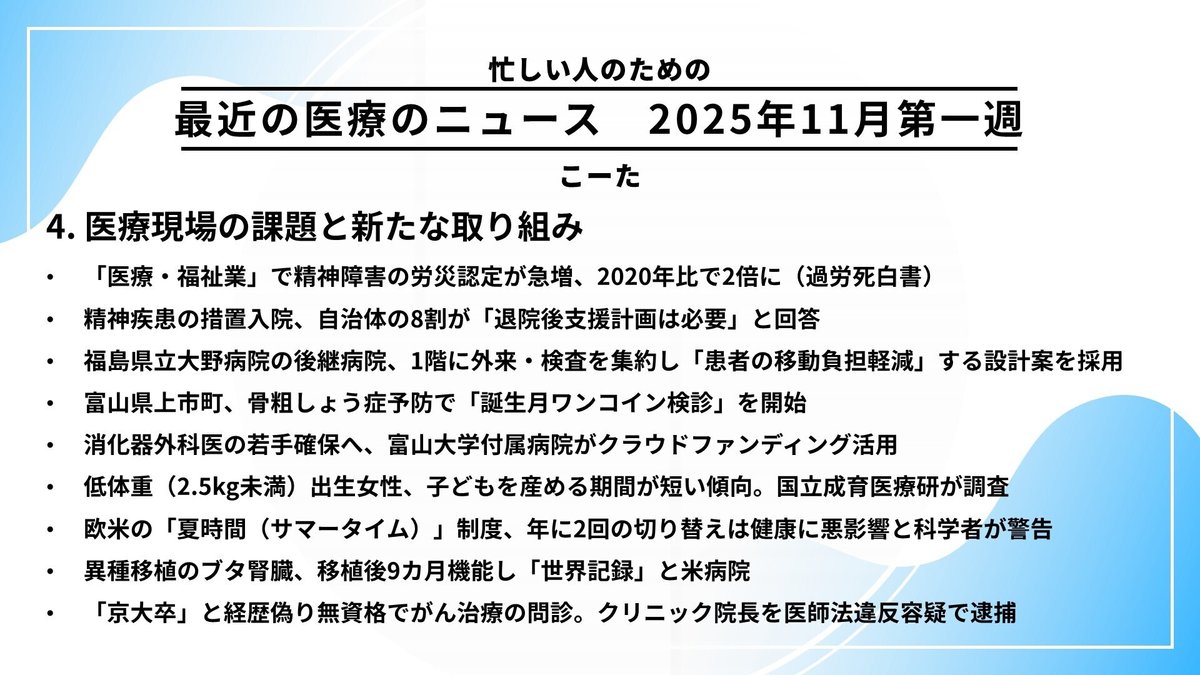
「医療・福祉業」で精神障害の労災認定が急増、2020年比で2倍に(過労死白書)
厚生労働省が発表した「過労死等防止対策白書」によると、「医療、福祉業」における精神障害の労災請求件数が急増していることが明らかになりました。
2024年の請求件数は969件と前年比で12%増加し、2020年(478件)と比較するとわずか4年で2倍に達しています。
特に医療の事案数は、2011年~2016年の平均14件台に対し、2020年~2022年の平均は46.7件と3倍以上に増加。
その具体的な要因として、「悲惨な事故や災害の体験、目撃」や「同僚などから暴行またはいじめ・いやがらせ」が、全産業の平均と比べて2倍以上発生している実態が浮かび上がりました。
精神疾患の措置入院、自治体の8割が「退院後支援計画は必要」と回答
精神疾患で自傷・他害の恐れがある人に行政判断で強制入院させる「措置入院」について、患者の退院後支援計画の作成主体となる自治体の8割が、「計画は必要である」との認識を持っていることが共同通信の調査で分かりました。
計画が必要な理由としては「適切な治療継続に有効」といった声が目立つ一方、監視強化への懸念や病気の自覚のなさなどから「患者側の同意が得られず」作成に至らない事例も確認されています。
専門家からは、医療側と患者側の信頼構築が前提であるとの指摘も上がっています。
自治体の8割が計画の必要性を感じている背景には、退院後の支援が途切れることで患者さんが地域で孤立し、病状の悪化や再入院を繰り返してしまう、いわゆる「回転ドア」問題への強い危機感があります。
計画の必要性は明らかですが、最大の壁は「患者さんの同意」です。
措置入院という強制的なプロセスを経た患者さんにとって、退院後の計画が「監視」と受け取られ、抵抗感が生まれるのは想像に難くありません。
専門家の指摘通り、計画書を作成すること自体が目的ではなく、患者さんとの信頼関係を築き、本人が望む生活を支援するという「プロセス」こそが本質です。
自治体が求める手厚い人員配置は、まさにこの信頼関係の構築に時間をかけるために不可欠な投資だと思います。
福島県立大野病院の後継病院、1階に外来・検査を集約し「患者の移動負担軽減」する設計案を採用
東京電力福島第1原発事故の影響で休止している福島県立大野病院の後継病院(2029年度以降開院予定)の設計案が決定しました。
最も高く評価されたのは、建物1階に外来、検査機能、救急部門、放射線部門などを集約し、患者さんの「移動負担を最小限に抑える」設計であった点です。
また、院内感染対策として動線を明確に分ける設計や、周辺の商業施設などとの周遊性を高める工夫も評価されています。
新病院の設計において「患者の移動負担軽減」が最優先の評価軸の一つとなった点は、今後の病院設計のトレンドを示すものと考えられます。
特に高齢の患者さんにとって、検査や診察のたびに院内の上下階を何度も移動することは、受診時間以上に大きな負担となります。
1階に主要な外来機能を集約する設計は、患者満足度の向上だけでなく、患者さんを誘導・搬送するスタッフの業務効率化にも直結します。また、コロナ禍を経て、設計段階から感染症対策を明確に組み込むことは、もはや「オプション」ではなく、現代の病院建築における「標準仕様」になったと言えます。
富山県上市町、骨粗しょう症予防で「誕生月ワンコイン検診」を開始
富山県上市町と、かみいち総合病院は、骨粗しょう症の早期発見・予防事業として「誕生月ワンコイン検診」を共同で開始しました。
この取り組みは、40歳~70歳の女性などの対象となる町民が、自身の誕生月に通常4,500円かかる骨密度検査を500円で受けられるというものです。
検査後には看護師による運動や食事に関するアドバイスも行われます。
これは自治体と中核病院が緊密に連携した、非常に優れた「予防医療」かつ「受診勧奨」のケースです。
骨粗しょう症は、自覚症状がないまま進行し、転倒による骨折がきっかけで寝たきりや要介護状態になるリスクの高い疾患です。
この取り組みのポイントは、「ワンコイン」という経済的ハードルの低さと、「誕生月」という受診タイミングの特定により、これまで無関心だった層の行動変容を促している点にあります。
自治体にとっては将来の介護給付費の抑制、病院にとっては地域住民の健康増進への貢献という、双方にメリットのある戦略的な施策と言えます。
消化器外科医の若手確保へ、富山大学付属病院がクラウドファンディング活用
膵臓がん手術など高度な技術を要する消化器外科医の志願者減少が全国的な課題となる中、富山大学付属病院が若手医師の確保・育成のため、クラウドファンディングを実施しました。
資金は若手向けの採用ホームページ作成や研究活動支援などに充てられ、5年間で30人の採用を目指すとしています。
CFは第1目標の1,000万円を達成し、注目を集めています。
医師の採用活動にクラウドファンディングを活用するというのは、非常に新しいアプローチです。
これは単に「資金集め」を目的としているのではなく、CFというプロセスを通じて「富山大学の消化器外科が、いかに若手医師の育成に本気であるか」という熱意とビジョンを、全国の医学生や研修医、そして地域住民に対して発信する、強力な「広報活動」としての意味合いも考えられます。
人手不足が業務の過酷さを招き、それが更なる若手敬遠につながるという負のスパイラルに陥りがちな外科系診療科において、資金使途を「研究支援」など若手のキャリアパスに直結する内容に絞った点も、戦略的と言えます。
低体重(2.5kg未満)出生女性、子どもを産める期間が短い傾向。国立成育医療研が調査
国立成育医療研究センターなどのチームが約4万人の女性を対象に分析した結果、出生時の体重が2.5キロ未満だった「低体重児」の女性は、3キロ台で生まれた女性と比較して、子どもを産める期間が約5~8か月短くなる傾向があり、月経不順のリスクも高いことが分かりました。
国内では10人に1人が低体重で生まれており、母親の痩せや妊娠中の過度な体重増加抑制などが要因とされています。
欧米の「夏時間(サマータイム)」制度、年に2回の切り替えは健康に悪影響と科学者が警告
欧米で導入されている夏時間(デイライト・セービング・タイム)制度について、年に2回、時計を1時間ずらす「切り替え」自体が、人々の健康に悪影響を及ぼすという研究報告が相次いでいます。
米スタンフォード大学の研究者なども、この切り替えが生活リズムを乱し、心臓疾患や自動車事故の増加につながる可能性があると指摘しています。
米国での調査では、国民の72%が時間の切り替えを望んでおらず、恒常的な「標準時(冬時間)」を支持する人が48%と最も多い結果も出ています。
これは社会的なルールが、個人の生体リズムに与える影響を問う公衆衛生上のテーマです。
経済活動などのメリットが強調されてきた一方で、年に2回の強制的な生活リズムの変更が、心臓疾患のリスク増といった具体的な健康被害につながるという指摘は重く受け止める必要があります。
米国で「恒常的な標準時」支持が最も多いのは、朝の光を浴びることが生体リズムを整える上で最も自然である、という科学的知見とも一致します。
経済的メリットと健康リスクを天秤にかけた、社会的な議論が必要とされているようです。
異種移植のブタ腎臓、移植後9カ月機能し「世界記録」と米病院
米東部ボストンのマサチューセッツ総合病院は、今年1月に末期腎不全の患者さん(67歳男性)に移植した、遺伝子操作を施したブタの腎臓が、271日間(約9カ月)にわたり機能したと発表しました。
これは「世界記録」となります。その後、機能低下が見られたため腎臓は摘出され、患者さんは透析治療に戻りました。
世界中で臓器提供者が圧倒的に不足する中、ブタなどの臓器を利用する「異種移植」の研究が進められています。
これは「異種移植」が臨床応用に向け、また一つ大きなハードルを越えたことを示すニュースです。
末期腎不全の患者さんにとって、ドナー不足は深刻な問題であり、異種移植はその根本的な解決策として長年期待されてきました。
今回の「9カ月機能」という記録は、ヒトの免疫による拒絶反応を長期間にわたりコントロールできたことを意味し、技術的に飛躍的な進歩と言えます。
最終的に機能低下に至ったという課題は残るものの、数日~数週間で拒絶されていた過去の事例と比べると、将来の治療選択肢となる可能性を強く感じさせます。
「京大卒」と経歴偽り無資格でがん治療の問診。クリニック院長を医師法違反容疑で逮捕
医師免許がないにもかかわらず、「京都大学医学部卒業」などと経歴を偽り、大阪市のがん治療専門クリニックの院長として患者の問診などを繰り返していたとして、66歳の会社役員が医師法違反の疑いで逮捕されました。
容疑者は採用時、医師免許について「紛失して再発行中」などと説明し、クリニック側は信じ込んでいたとされます。これまでに169人の患者に対し400回以上の問診などを行っていたとみられています。
これは特に「がん治療」という、患者さんやご家族が藁にもすがる思いで訪れる領域で行われたことは、非常に悪質だと思います。
最大の疑問は、なぜクリニック側が「医師免許の原本確認」という、採用における最も基本的かつ重要なプロセスを怠ったのか、という点に尽きます。
ヘルスケア関連企業の戦略と動向
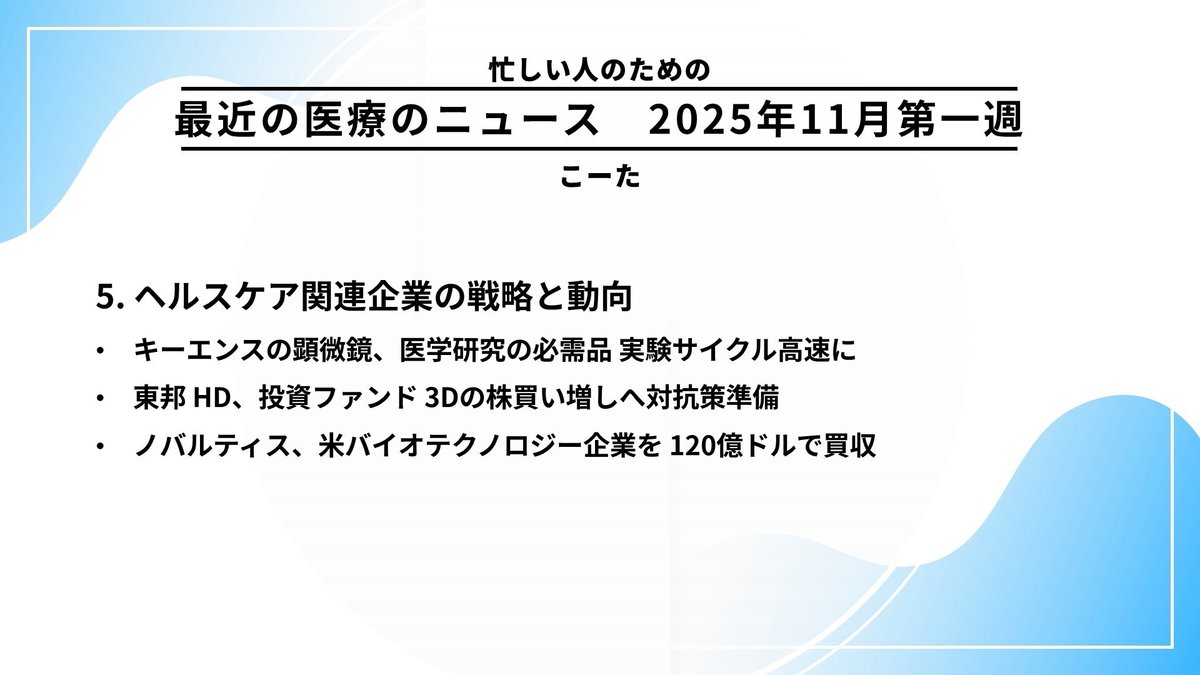
キーエンスの顕微鏡、医学研究の必需品 実験サイクル高速に
FA機器やセンサーで知られるキーエンスの蛍光顕微鏡が、今、医学系の研究者から「必需品」として高い評価を受けています。
最高解像度を追求するニコンやツァイスといった専門メーカーのハイエンド機(1台数千万円)とは異なり、キーエンス製品は「いい意味」でロースペックと評されています。
その真意は、高額な共用機のように予約や暗室を必要とせず、研究室の予算で導入できる価格帯で、手軽に実験を始められる点にあります。
研究者がアイデアを思いついた瞬間に即座に検証できるため、「実験サイクルを高速に回せる」ことが最大の価値となっています。
直販体制によるきめ細かく迅速なアフターサービスも、研究者たちの信頼を掴んでいます。
東邦 HD、投資ファンド 3Dの株買い増しへ対抗策準備
医薬品卸大手の東邦ホールディングスは、シンガポールの投資ファンド「3Dインベストメント・パートナーズ」による急速な株式買い増しを受け、買収防衛策(対応方針)を導入すると発表しました。
3Dは2024年6月時点の保有比率約5%から、わずか数ヶ月で23%超まで買い進めており、これは経営陣にとって「急襲」とも言える動きです。
東邦HDが導入する対応方針は、3Dが24%以上の保有を狙う場合、新株予約権を発行するなどして3Dの議決権比率を下げる、いわゆる「ポイズンピル」です。
これは「物言う株主」と日本企業の経営陣との間で繰り広げられる、典型的な攻防戦です。
医薬品卸業界は、アルフレッサ、メディパル、スズケン、そして東邦HDの4大グループによる寡占市場ですが、利益率が低く、効率化の余地が大きいと見られがちです。
3Dは、東邦HDの経営に非効率な点や、資産の有効活用がなされていない点があると考え、株価を上げるための変革を迫っていると推測されます。
買収防衛策はあくまで「時間稼ぎ」であり、東邦HDの経営陣は、3Dだけでなく一般の株主をも納得させるだけの、具体的な企業価値向上策を早急に示す必要に迫られています。
ノバルティス、米バイオテクノロジー企業を 120億ドルで買収
スイスの製薬大手ノバルティスが、希少な筋疾患治療薬を手がける米国のバイオテクノロジー企業「アビディティ・バイオサイエンシズ」を、約120億ドル(約1.8兆円※1ドル150円換算)の現金で買収すると発表しました。
これは、市場株価に対し46%ものプレミアム(上乗せ価格)を支払う大型買収です。
ノバルティスは、心不全治療薬「エントレスト」など、現在の主力医薬品の特許切れ(パテントクリフ)が迫っており、将来の収益源を確保することが急務となっています。
今回の買収は、そのための具体的な一手です。
おわりに
今週も、医療制度の変更に向けた具体的な動き、物価高騰や人手不足を背景とした病院経営の厳しい現実、そしてAIや新技術がもたらす変革の兆しまで、多岐にわたるトピックをご紹介しました。
各ニュースは独立しているように見えても、「限られた医療資源をどう最適に配分するか」という共通の大きな課題に根ざしていることが分かります。
こうした変化の波は、今後も止まることはありません。
私たち医療に関わる者は、これらの動向を単なる「情報」として受け取るだけでなく、自らの現場や経営にどう活かしていくか、あるいはどう備えていくかを常に問い続ける姿勢が求められます。
今後も引き続き、重要な動向を注視し、その背景にある意味を皆様にお届けできるよう努めてまいります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。