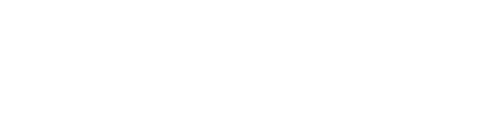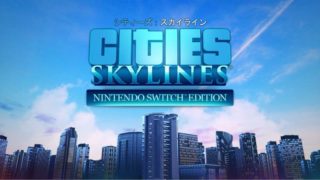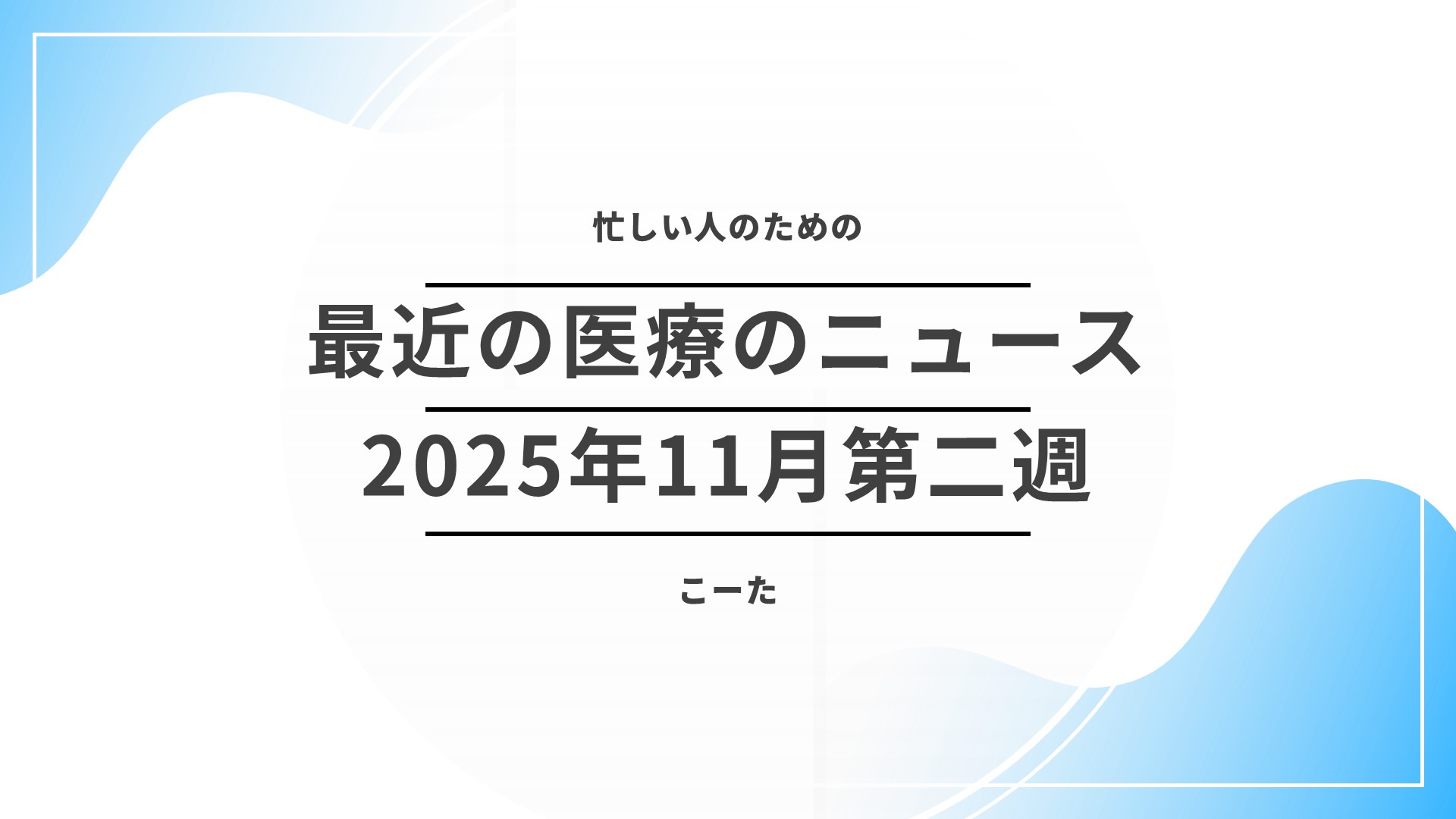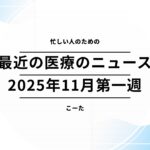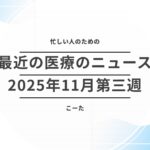はじめに
日々多くの情報が飛び交う中、医療・ヘルスケア分野の重要な動向を追いかけるのは容易ではありません。
2025年11月第二週も、入院時食事代の負担増議論や国立大学病院の経営危機、AIによる健康予測技術、チャットGPTの倫理問題など、制度・経営・テクノロジーの各面で注目すべきニュースが報じられました。
この記事では、多忙なビジネスパーソンや医療関係者の皆様に向け、単なる事実の羅列ではなく、医業経営コンサルタントとしての視点を交えながら、その背景や現場への影響を解説します。
ぜひ最後までお付き合いください。
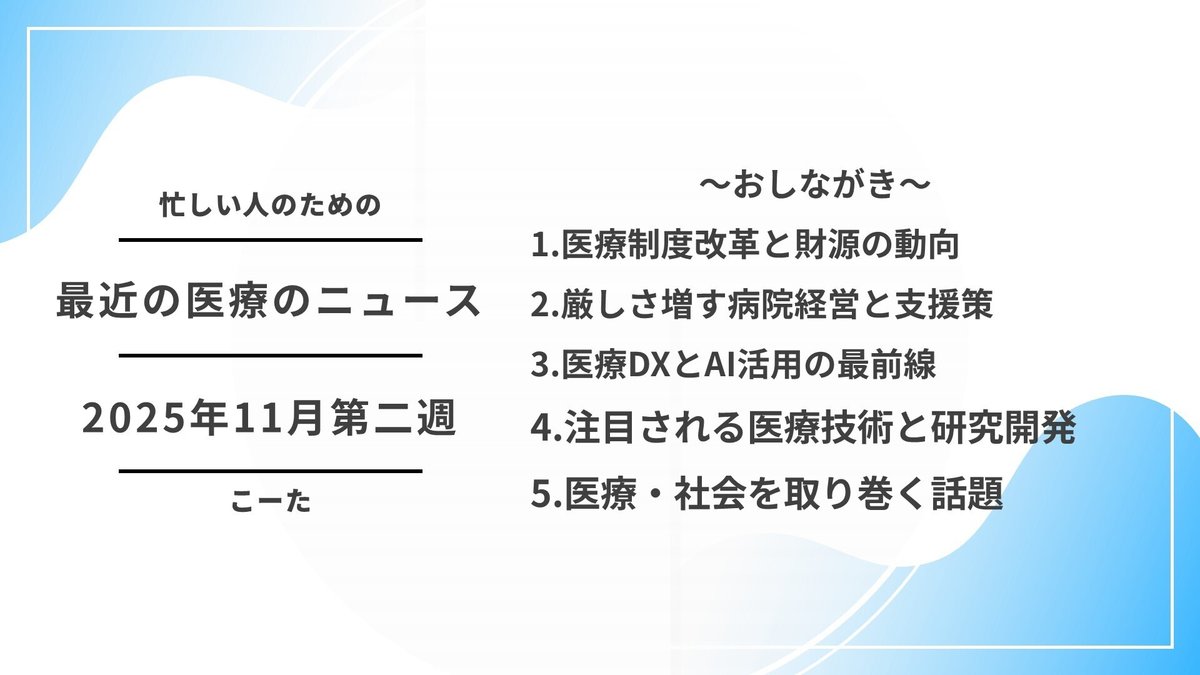
医療制度改革と財源の動向
医療費の適正化と財源の確保は、国の医療政策における最重要課題の一つです。
ここでは、入院時の食事代、お薬の自己負担、病床のあり方など、私たちのお金や医療体制に直結する最新の議論や決定事項を解説します。
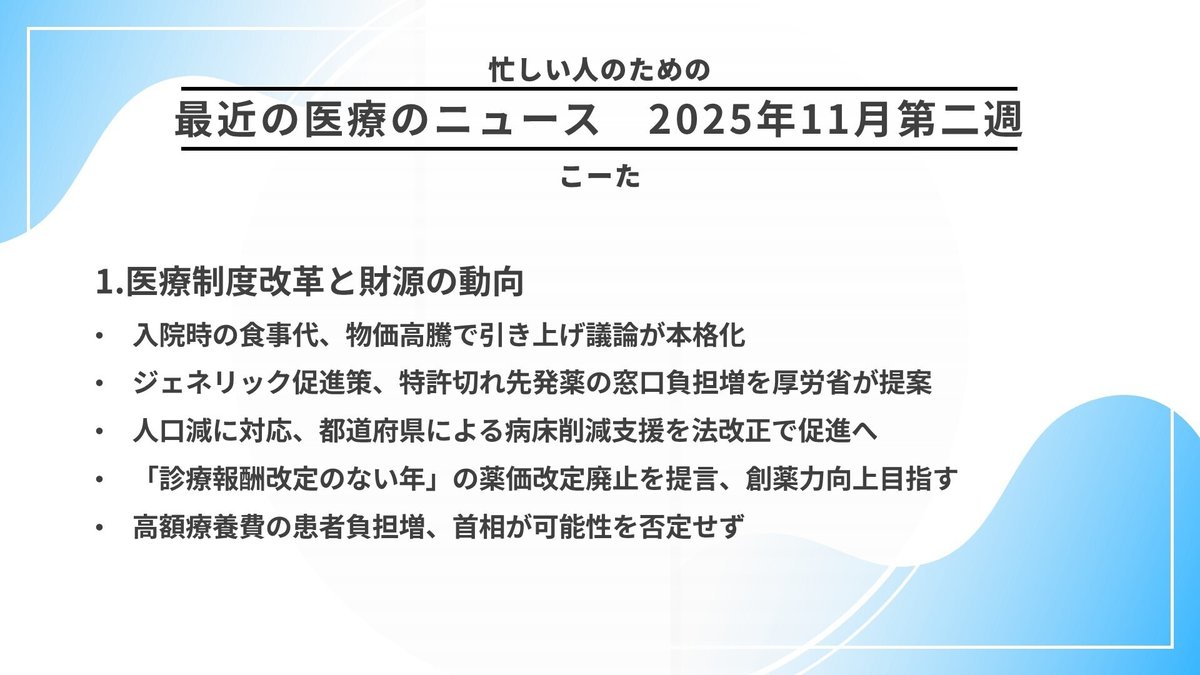
入院時の食事代、物価高騰で引き上げ議論が本格化
厚生労働省は11月7日、入院患者が負担する食事代の引き上げに向けた議論を中医協(中央社会保険医療協議会)で開始しました。
長引く食材費の値上がりが、食事を提供する医療機関の経営を圧迫していることが背景にあります。
現在、入院時の食事代は国が定めた基準額(1食690円)に対し、患者さんが原則510円を負担し、残りの180円が公的医療保険から給付されています。
この患者負担分は、物価高騰への対応として2024年6月に30円、2025年4月に20円と、近年立て続けに引き上げられてきました。
しかし、それでも食材費の高騰は続いており、中医協の委員からは物価高への対応自体に異論は出ませんでしたが、「3年連続の負担増となる場合、患者の理解が得られるよう最大限配慮してほしい」といった意見も出ています。
厚労省は今後、食材費だけでなく光熱費や水道代の高騰も踏まえた検討を進める方針です。
医療機関の経営実態、特に給食部門の収支を考えると、この引き上げ議論は避けられない流れだと考えられます。
食材費だけでなく光熱費も高騰しており、患者さんへの食事提供体制を維持すること自体が困難になりつつあるためです。
食事の質を維持するためにも、一定の財源確保は必要になるでしょう。
ジェネリック促進策、特許切れ先発薬の窓口負担増を厚労省が提案
厚生労働省は11月6日、特許が切れた先発医薬品(長期収載品)を患者さんが希望した場合の窓口負担を引き上げる方向で調整に入りました。
価格の安いジェネリック医薬品(後発薬)の使用をさらに促し、公的医療保険の給付を抑える(=結果として現役世代の保険料負担を軽減する)狙いがあります。
現在の仕組みでは、患者さんがジェネリック医薬品ではなく先発薬をあえて選んだ場合、医療費の1〜3割の自己負担に加えて、「先発薬とジェネリックの価格差の25%」を追加で支払う必要があります。
厚労省は今回、この追加負担の割合を「50%」「75%」「差額の全額」に引き上げる3つの案を社会保障審議会で提示しました。
年末までに議論が取りまとめられ、早ければ来春にも引き上げが実施される可能性があります。
これは国の医療費抑制策として強力な一手であり、ジェネリックの使用割合をさらに引き上げる効果が期待されます。
今回の選択する案によっては大幅に増える可能性があるため、これまでと同じように先発薬を選び続ける場合、経済的に大きな影響が予想されます。
人口減に対応、都道府県による病床削減支援を法改正で促進へ
自民党、日本維新の会、公明党の3党は、医療機関による病床の削減を都道府県が支援できるよう、医療法などを改正する検討に入りました。
日本の人口減少に伴い、将来的に過剰になると見込まれる病床の削減を促進するのが狙いです。
具体的には、法律に「都道府県は(中略)医療機関が緊急に病床を削減することを支援する事業を行える」といった内容を時限的に明記し、都道府県の役割を明確にします。
病床を削減すると医療機関の収入が減少するため、その減収分を都道府県が財政支援し、その費用の一部を国も負担することを想定しています。
また、政府が2030年までに目指す「電子カルテの普及率100%」の方針も法律に明記される方向です。
この法改正案は、臨時国会での成立を目指しています。
この検討は、国が進める「地域医療構想」の実現に向けた、より具体的な一歩と言えると思います。
これまでなかなか進まなかった病床の機能分化や削減に対し、財政支援という具体的な手段を用意することで、医療機関の再編・統合を実質的に後押しする狙いがあります。
「診療報酬改定のない年」の薬価改定廃止を提言、創薬力向上目指す
厚生労働省の「創薬力向上のための官民協議会ワーキンググループ」は11月5日、「毎年の薬価改定」が日本の医薬品市場の低成長の原因になっているとして、診療報酬改定が行われない年の薬価改定は「廃止すべき」との意見を盛り込んだ議論の整理を公表しました。
薬価は現在、原則として2年に1度の診療報酬改定時と、その中間の年の年1回、市場の実勢価格(医療機関や薬局での実際の仕入れ値)に合わせて引き下げられています。
ワーキンググループでは、この「中間年改定」を廃止するほか、インフレなどの経済動向を反映して薬価を一定程度引き上げる仕組みも検討すべき、との意見も上がりました。
また、特許が切れた先発医薬品に依存するビジネスモデルからの脱却も主張され、「先発品は原則として市場から撤退することを目指すべき」とも提言されています。
「中間年改定の廃止」が実現すれば、製薬企業にとっては、薬価の予見可能性が高まり、経営的なメリットは大きいです。
一方で、保険財政の観点からは、薬価改定の頻度が減ることで薬剤費の削減効果が鈍化する懸念があります。
国民の保険料負担に影響する可能性があるため、慎重な議論が必要です。
高額療養費の患者負担増、首相が可能性を否定せず
高市早苗首相は11月4日の衆院本会議で、医療費の月額上限を定める「高額療養費制度」について、患者負担を引き上げる可能性を否定しませんでした。
高市首相は、自民党総裁選時の政策アンケートでは「引き上げるべきではない」と反対の意向を示していました。
答弁で首相は、「患者の経済的な負担が過度にならないよう配慮しながら、増大する高額療養費を負担能力に応じてどのように分かち合うか、検討を丁寧に進める」と述べました。
政府は昨年、この高額療養費の負担上限月額を引き上げる方針を決めていましたが、患者団体や野党の強い反発を受けて全面凍結していました。
石破前首相は「今秋までに再検討」と表明していましたが、結論は12月にずれ込む可能性も出ています。
高額療養費制度の見直しは、特に継続的な治療や高額な治療が必要な患者さんにとって、生活に直結する非常に大きな問題です。
首相の答弁からは、国の財政的な要請と、国民感情や生活への配慮との間で、非常に難しい調整が続いている様子がうかがえます。
厳しさ増す病院経営と支援策
物価高や人件費の高騰は、医療機関の経営に深刻な影響を与えています。
特に公的役割の大きい病院の赤字が目立ち、国や自治体による支援策、あるいは病院自体の再編計画の見直しが各地で報じられています。
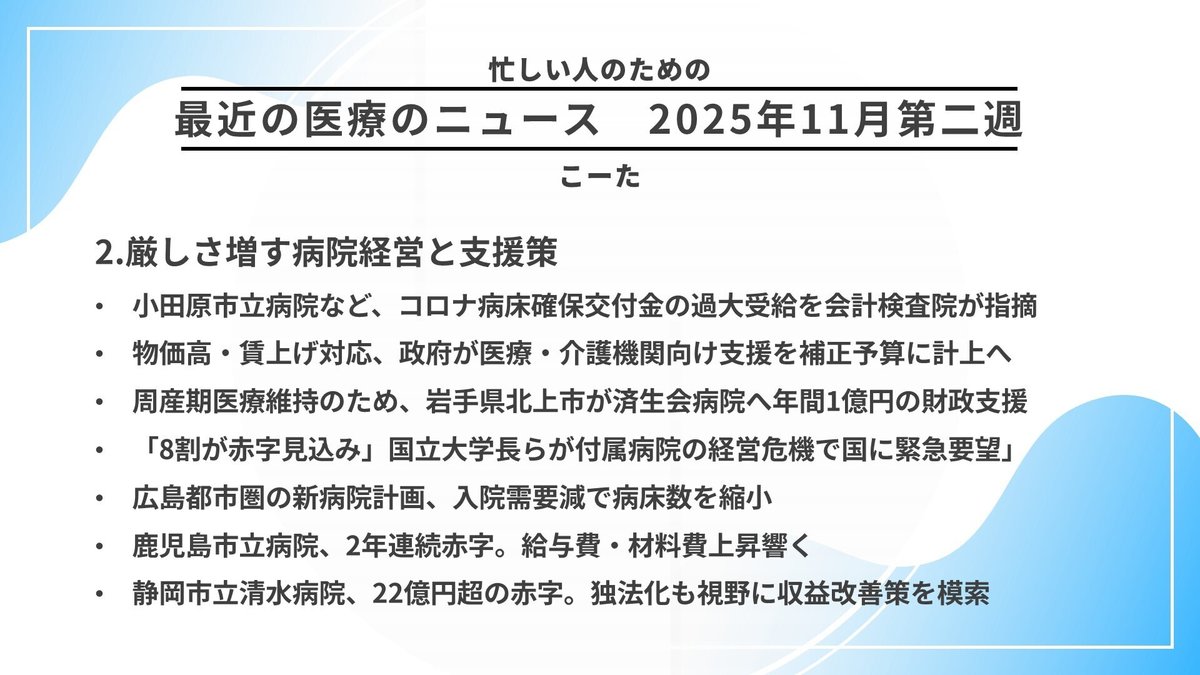
小田原市立病院など、コロナ病床確保交付金の過大受給を会計検査院が指摘
会計検査院は11月5日、新型コロナ対策の「緊急包括支援交付金」について、神奈川県などで過大受給があったと公表しました。
小田原市立病院(約3億円)と湘南泉病院(約778万円)が指摘を受けています。
県の報告書確認が不十分だったとされています。
小田原市立病院は過大分を国に返還する方針ですが、病院担当者は「当時の基準が明確ではない中、現場の実績に合わせて算出した。検査院の決定は受け入れるが、その判断には納得がいかない」ともコメントしています。
当時、パンデミックという未曽有の事態において、現場は即応を求められました。
今回の事態は、当時の逼迫した状況下でのルール解釈の曖昧さや、交付金申請プロセスの複雑さが招いた側面もあるのではないかと推察されます。
医療機関側のガバナンスも問われますが、同時に、緊急時の支援スキームのあり方について課題を残した事例と言えると思います。
物価高・賃上げ対応、政府が医療・介護機関向け支援を補正予算に計上へ
政府は、物価高や人件費高騰で経営が悪化している医療機関や介護施設を支援するため、2025年度補正予算案に補助金を盛り込む調整に入りました。
全国の民間病院の約半数が2024年度決算で赤字となるなど、厳しい経営状況に対応する狙いです。
医療や介護は診療報酬・介護報酬などの公定価格でサービス料が決まっているため、コストの上昇分を価格に転嫁できないという構造的な課題があります。
今回の支援は、特に経営が厳しい救急医療や周産期医療を担う病院を手厚くし、業務効率化も後押しする内容となる見通しです。
2年に1度の診療報酬改定を待っていては、足元の急激なコスト増に対応できないため、補正予算による機動的な支援は不可欠です。
特に、地域のセーフティネットである救急や周産期医療といった不採算部門をどう守るかは喫緊の課題であり、支援の傾斜配分は妥当な判断だと考えられます。
周産期医療維持のため、岩手県北上市が済生会病院へ年間1億円の財政支援
岩手県北上市は11月6日、地域の周産期医療体制を維持するため、北上済生会病院に対して2025年度から3年間、年1億円の財政支援を行う方針を明らかにしました。
同病院は移転新築に伴う借入金返済に加え、患者数の減少やコスト高騰で経営環境が悪化しており、「このままでは不採算となっている周産期部門の維持が困難」と市に要望していました。
これは自治体が地域の医療インフラや、周産期医療、小児医療、救急などの特に採算確保が難しい「政策医療」をどう守っていくか、という課題の典型的な事例です。
病院の経営努力だけでは限界がある分野に対し、行政が財政的に直接関与するという判断は、地域住民の安心を守る上で重要だと思います。
「8割が赤字見込み」国立大学長らが付属病院の経営危機で国に緊急要望
11月7日、病院を抱える国立大学の学長ら44人が連名で、文部科学省と厚生労働省に対し、付属病院の経営危機に関する緊急要望を提出しました。
国立大学病院長会議によると、2025年度は8割近い33病院が赤字となる見込みで、赤字総額は330億円に上るとしています。
医薬品の高額化や人件費上昇で「診療すればするほど赤字が膨らむ状況」だとし、このままでは地域医療の崩壊や医学研究の停滞を招きかねないと訴え、運営費交付金や診療報酬の大幅な増額を求めています。
国立大学病院は、
①地域の高度医療の最後の砦
②医師や看護師の養成
③地域医療機関への医師派遣
という3つの重要な公的役割を担っています。
その中核機関が軒並み経営危機に陥っているという事実は、日本の医療提供体制の根幹が揺らいでいることを示しており、極めて深刻な事態です。
広島都市圏の新病院計画、入院需要減で病床数を縮小
広島県が進める広島都市圏の病院再編計画において、2030年度に開院予定の新病院の基本計画が改定されました。
当初1,000床だった病床数を860床程度に縮小します。
これは、全国的な入院日数の短縮や在宅医療への移行が進み、入院需要が減少傾向にあることに対応するためです。
また、建築費高騰への対策として、当初解体予定だった既存の建物を残して活用し、新病院棟の階数を縮小することも決定されました。
これは将来の医療需要のシミュレーションを現実的に見据えた、妥当な計画修正だと評価できます。
同時に、昨今の急激な建築費高騰という外部環境の変化にも対応しており、計画の柔軟性を示した事例と言えます。
ただし、病院の建設計画は、構想から開院まで数年近くかかることも珍しくありません。
その間に医療制度や患者動向は大きく変化するため、計画を固定化せず、状況に応じて見直す視点は非常に重要です。
鹿児島市立病院、2年連続赤字。給与費・材料費上昇響く
鹿児島市立病院の2024年度決算案が報告され、約26億円の純損失となり、2年連続の赤字だったことが分かりました。
赤字額は前年度より約2.2億円減少しています。
入院・外来ともに患者数は増加(全体で7.3%増)し改善傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には戻っていません。
一方で、患者増に伴う薬品費などの材料費や、人事院勧告などによる給与費が大幅に増加し、コスト増が収益を圧迫した形です。また、看護職員の退職者が増加していることも課題として報告されています。
これは「患者数が増えても、それ以上に人件費と材料費などのコストが上昇すれば赤字になる」という、現在の多くの病院が直面する経営の難しさを象徴しています。
特に、人材確保のための給与費増は避けられず、看護職員の離職対策は経営上の最重要課題の一つです。
患者数が回復傾向にあること自体はポジティブな兆候です。
しかし、それが経営黒字化に直結しないのが現在の医療経営の厳しい現実です。
看護職員の退職理由として「転職(27人)」が「家庭の事情(29人)」に迫る人数となっている点は看過できません。
給与面だけでなく、労働環境やキャリアパスを含めた処遇改善が急務であると思います。
静岡市立清水病院、22億円超の赤字。独法化も視野に収益改善策を模索
静岡市立清水病院の2024年度決算が22億円あまりの損失額となったことが報告されました。
病院長は、医療政策アドバイザーの助言を受けながら収益改善に取り組んでいるとし、「保険診療ではなくて自費診療で何かできないか」という可能性も模索していると説明しました。
静岡市は、同病院について2030年度までに地方独立行政法人へ移行することを目指しています。
巨額の赤字を前に、公立病院として保険診療の枠内での経営改善努力を続けるだけでなく、収益源の多様化として「自費診療」の導入を検討している点が注目されます。
また、経営形態そのものを見直す「地方独立行政法人化」は、抜本的な経営改革の選択肢の一つです。
公立病院が自費診療を導入するには、設置条例や地域の医療機関との兼ね合いなど、多くのハードルがあります。
しかし、保険診療収益だけでは立ち行かないという危機感の表れであると感じました。
地方独立行政法人化は、経営の自由度が高まるメリットが期待できます。
ですが、独法化すれば自動的に経営が改善するわけではありません。
自治体からの運営費交付金が削減される可能性もあり、よりシビアな経営手腕が求められることになります。
医療DXとAI活用の最前線
医療分野でも、デジタル技術を活用した業務効率化や、AIによる新たな診断・予測技術の開発が急速に進んでいます。
ここでは、国全体のデータ基盤整備から、病院・救急現場、個人の健康管理に至るまでの最新のDX動向をご紹介します。
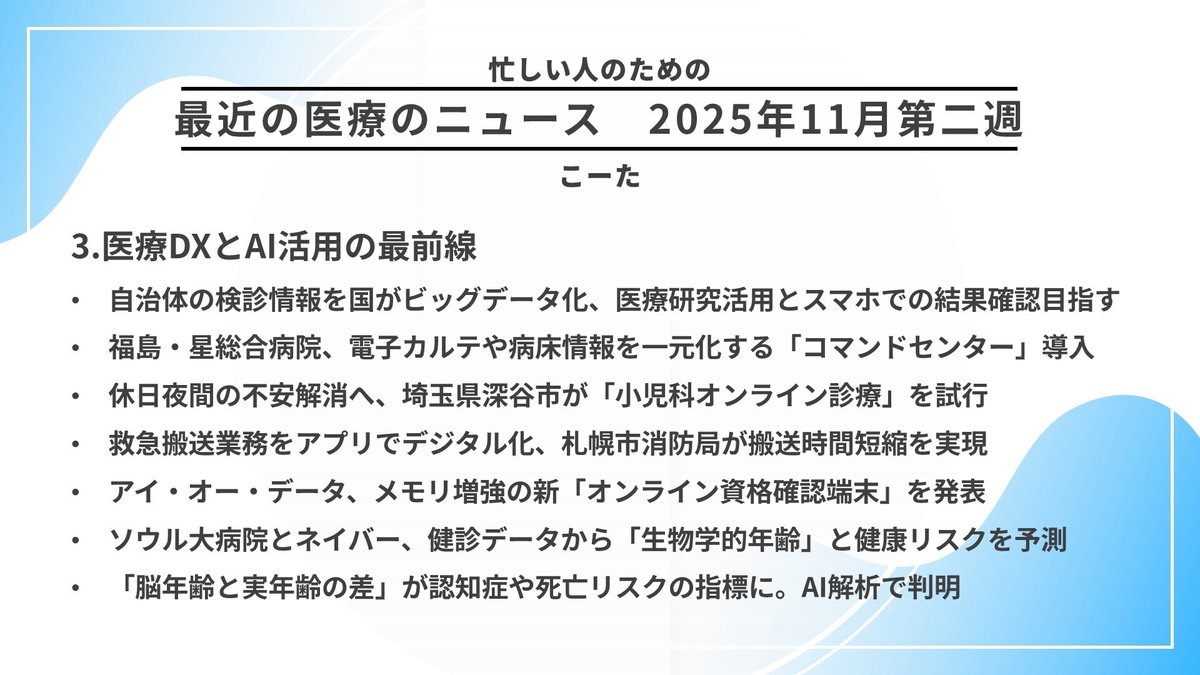
自治体の検診情報を国がビッグデータ化、医療研究活用とスマホでの結果確認目指す
厚生労働省は、市区町村が行う検診の結果をデジタル化し、国でデータベースに集約する事業に着手します。
集められた情報は、個人が特定できないよう匿名化処理を施した上で「医療ビッグデータ」として、大学や専門機関での研究に活用されます。
病気の新たな予防方法の発見や、効果的な医療政策の立案につなげる狙いです。
住民側にもメリットがあり、将来的にはスマートフォンなどからマイナポータルを通じて、自身の検診結果を時系列で確認できるようになるため、健康管理がしやすくなることが期待できます。
まずは来年3月にも8市区町で実証事業が開始され、2029年度の全国実施を目指しています。
個人の利便性向上はもちろんですが、これまで自治体ごとに分散していた貴重な検診データが匿名化の上で集約されれば、日本の予防医療研究が大きく進展する可能性を秘めています。
課題は「強固なセキュリティとプライバシーの保護」です。
匿名化処理の精度や、データの利用範囲を定める厳格なルール作りが、国民の信頼を得る上で不可欠となります。
自治体ごとに異なるシステムやデータ形式を標準化する必要があり、現場のシステム改修や事務的な負担が一時的に増大することも予想されます。
福島・星総合病院、電子カルテや病床情報を一元化する「コマンドセンター」導入
福島県郡山市の星総合病院は、電子カルテの情報や病床の空き状況などをリアルタイムで一元管理し、モニターに表示する「コマンドセンター」と呼ばれるシステムを県内で初めて導入しました。
導入によって、各病棟の入院患者数や予定、手術や検査のスケジュール、退院目標日といった情報が10分ごとに更新され、関係各所で常時共有されます。
導入後は、入退院管理者が電話で予定を確認したり、他の医療機関への空き病床確認の連絡をしたりする手間が大幅に削減されました。
また、情報伝達や引き継ぎ業務も簡略化されています。
病院運営における「情報の分断」は、業務効率を低下させ、時に医療安全にも関わる長年の課題です。
この取り組みは、院内の情報をリアルタイムで「見える化」することで、病床管理の最適化を図る、先進的なDXの事例です。
休日夜間の不安解消へ、埼玉県深谷市が「小児科オンライン診療」を試行
埼玉県深谷市は、小児の休日夜間診療体制を充実させるため、ビデオ通話による「小児科オンライン診療」の試行を11月2日から開始しました。
背景には、インフルエンザ患者の増加に加え、地域の休日夜間診療所が医師不足や高齢化により日曜・祝日の夜間診療を取りやめていた事情があります。
この試行実施は、保護者が専用アプリで予約した後、市役所の相談室に来場する形式です。
会場では看護師が体温や呼吸音などを計測し、そのデータに基づき遠隔地にいる小児科医がオンラインで診療します。処方箋も発行されます。
利用者からは「診てもらえる場所があるのは安心」と好評で、市は効果検証を経て来年4月からの本格導入を目指しています。
これは医師不足や偏在が深刻な地域において、デジタル技術を活用して医療アクセスを維持・補完しようとする現実的な解決策です。
特に保護者の不安が大きい「小児の休日夜間」という領域で、行政が主体となって安心を提供しようとする姿勢は、住民のニーズに的確に応えたものと言えます。
救急搬送業務をアプリでデジタル化、札幌市消防局が搬送時間短縮を実現
札幌市消防局は、救急搬送件数の増加と隊員の負担増という課題に対応するため、救急隊向けアプリ「NSER mobile」を導入し、搬送業務のデジタル化を進めました。
このアプリはiPadなどを活用し、患者情報の入力や搬送先の医療機関情報などをリアルタイムで共有できます。
従来は電話と紙で行っていた医療機関とのやり取りがデジタル化されたことで、搬送のスピードと精度が向上しました。
特に、これまで1件ずつ電話確認していた受け入れ要請を、アプリで複数の病院に一括送信できるようになったことで、搬送時間の大幅な短縮につながっています。
救急医療において「搬送時間の短縮」と「正確な情報伝達」は、患者さんの予後を左右する最も重要な要素です。
このアプリ導入は、救急隊と受け入れ病院の双方の業務を劇的に効率化し、結果として地域住民が受ける医療の質そのものを高める、DXの優れた事例と言えます。
アイ・オー・データ、メモリ増強の新「オンライン資格確認端末」を発表
アイ・オー・データ機器は11月5日、医療業界向けのオンライン資格確認端末の新製品「APX2-MEDICAL/QCD」を発表しました。マイナンバーカードによる保険証確認などで使われる端末です。
従来モデルの高い信頼性を継承しつつ、メモリを増強し、USB Type-Cポートを搭載するなど、現場のニーズに応じたアップデートが施されています。また、日医標準レセプトソフト「WebORCA」のオンプレミス版を導入したアプライアンス端末であり、PDF署名アプリも利用可能です。
オンライン資格確認システムは、今や医療機関の受付業務に不可欠なインフラです。その中核となる端末の安定稼働は、医療DXの基盤を支える上で欠かせません。
今回の新製品は、処理速度の向上など、日々の業務をよりスムーズにするための着実な改良が加えられており、医療機関のシステム更新における選択肢を広げるものです。
ソウル大病院とネイバー、健診データから「生物学的年齢」と健康リスクを予測
韓国のソウル大学病院とIT大手のネイバーが、約15万人の健康診断データをAIで分析し、個人の「生物学的年齢」と将来の健康リスクを同時に評価できるモデルを開発しました。
このAIは、血圧、血糖、肺機能、コレステロールなど複数の健康指標を統合的に分析し、その人の生物学的な年齢を予測します。
さらに、その数値が実年齢とどれだけ離れているかを算出し、現在の健康状態が将来的な生存率とどのような統計的関連性を持つかを評価できます。
疾病の有無や死亡リスク情報も同時に学習させている点が特徴です。
これはAIを活用した「個別化予防医療」の進展を示す興味深い研究です。
単に「あなたは実年齢より○歳若い」と伝えるだけでなく、その「年齢ギャップ」が将来の疾病リスクや死亡率とどう結びつくかを統計的に示せる点は、個人の健康への意識や行動変容を促す、強力な動機づけになる可能性があります。
「脳年齢と実年齢の差」が認知症や死亡リスクの指標に。AI解析で判明
AIによる健康予測のもう一つの事例です。
中国の研究グループが、頭部MRI画像をディープラーニングで解析し、推定した「脳年齢」と実年齢の差である「脳年齢ギャップ」が、脳の老化を予測する有力な指標になる可能性があると発表しました。
4万人以上の大規模データを解析した結果、このBAGが大きい(=実年齢より脳年齢が高い)ほど、認知機能低下や認知症、多発性硬化症、精神疾患のリスクが高まることが示されました。
具体的には、BAGが1年増加するごとに、アルツハイマー病リスクは16.5%、全死亡リスクは12%上昇していました。
前のニュース(生物学的年齢)と関連しますが、こちらは「脳」の健康状態に特化した指標です。
MRIという画像診断とAI解析を組み合わせることで、これまで漠然としていた「脳の老化」を「BAG」という客観的な数値で可視化し、将来の深刻な疾患リスクと結びつけた点に大きな意義があります。
早期発見・早期介入のための新たなツールになることが期待されます。
注目される医療技術と研究開発
医療の進歩は、基礎研究から実用的な技術革新まで多岐にわたります。ここでは、iPS細胞やがん治療といった最先端の研究成果から、ドローン配送、治療法の国内製造、医療機器の進化など、現場の医療を変えうる新しい技術動向を紹介します。
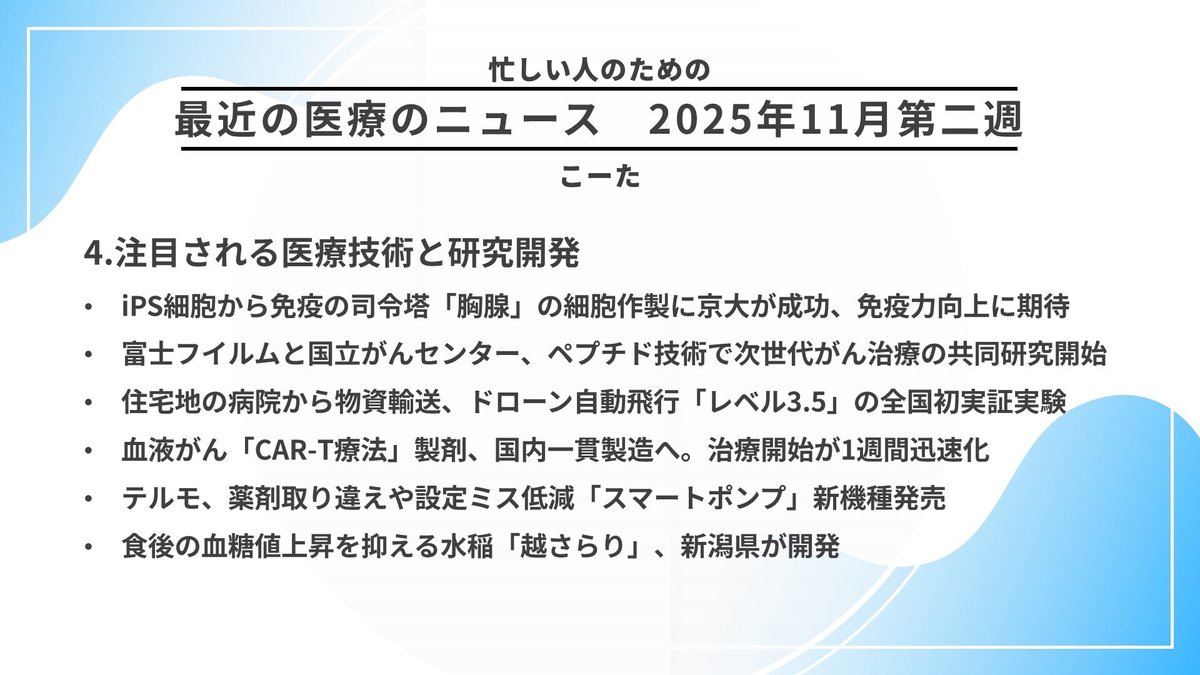
iPS細胞から免疫の司令塔「胸腺」の細胞作製に京大が成功、免疫力向上に期待
京都大学iPS細胞研究所は、体内の免疫システムの中核である「T細胞」を生成する器官「胸腺」の構成細胞を、ヒトのiPS細胞から作製することに成功しました。
胸腺はT細胞を教育する学校のような役割を持ちますが、成人すると小さくなり機能が低下します。
研究グループは、iPS細胞の培養過程でビタミンA由来の物質の濃度を最適化することで、この胸腺の細胞を作製。
さらに、T細胞の基となる細胞と一緒に培養した結果、あらゆる病原体に対応できる「ナイーブT細胞」に似た働きを持つ細胞ができることを確認しました。
この成果は、生まれつき胸腺がない患者さんや、加齢などで免疫力が低下した人の治療に役立つ可能性があります。
これは「失われた免疫機能の再構築」という将来の医療に近づく、重要な基礎研究の成果です。
T細胞を増やす既存の免疫療法とは異なり、T細胞そのものを生み出す「工場」の基盤を作る技術であり、加齢による免疫低下といった、これまで根本治療が難しかった分野への応用が長期的に期待されます。
富士フイルムと国立がんセンター、ペプチド技術で次世代がん治療の共同研究開始
富士フイルムは11月7日、国立がん研究センターと次世代がん治療のための共同研究を開始すると発表しました。
富士フイルムが持つ、がん細胞に強固に結びつく「環状ペプチド」の技術と、国立がん研究センターが持つ、がん細胞を自滅させる働きを持つ「アンチセンス核酸」という化合物の設計技術を組み合わせます。
ペプチドを「運び屋」として利用し、アンチセンス核酸をミサイルのように効率よくがん細胞まで届ける(ドラッグ・デリバリー・システム:DDS)ことで、副作用を抑えつつ高い治療効果を目指します。
これは「必要な薬を、必要な場所に、必要なだけ届ける」というDDS(ドラッグ・デリバリー・システム)の高度化を目指す取り組みです。
アンチセンス核酸のような有望な治療薬候補も、標的のがん細胞に正確に届かなければ効果は出ず、正常な細胞を傷つければ副作用となります。
異業種の独自技術が、創薬の課題を解決する鍵になるか注目されます。
住宅地の病院から物資輸送、ドローン自動飛行「レベル3.5」の全国初実証実験
和歌山市で11月4日、ドローンの自動飛行実験「レベル3.5」が実施されました。「レベル3.5」とは、地上の補助員や看板設置なしでドローンを自動飛行させる段階を指します。
今回、人口集中地区(住宅地)を含む飛行ルートでの運航は全国で初めてとなりました。
実験は、住宅地に立地する宇都宮病院から4キロ離れた「道の駅」まで、病院内の施設で作られた弁当を積んで飛行し、往復約20分の飛行に問題なく成功しました。
配送事業会社は、将来的な定期便としての運航を目指しています。
ドローンの医療分野での活用、特に「レベル3.5」が人口集中地区で成功した意義は非常に大きいです。
これまでは中山間地や離島での実証が中心でしたが、都市部においても、交通渋滞に左右されない緊急時の医薬品配送や、病院・薬局から在宅患者への物資輸送など、物流の「ラストワンマイル」を担うインフラとして、一気に現実味を帯びてきました。
血液がん「CAR-T療法」製剤、国内一貫製造へ。治療開始が1週間迅速化
再発・難治性の血液がんに対する免疫細胞療法「CAR-T療法」の製剤について、全ての製造工程を国内で行える見通しとなりました。
製造は、ニコンの子会社であるニコン・セル・イノベーションが受託します。
CAR-T療法は、患者さん自身の血液から免疫細胞(T細胞)を取り出し、遺伝子を改変してがんへの攻撃力を高めて製剤化し、再び患者さんの体内に投与する治療法です。
現在は、国内で採取した細胞を米国などに空輸して加工し、製剤を再び日本に運んで投与しているため、治療開始までに1〜2か月を要していました。
国内で一貫生産が可能になることで、この日米間の輸送が不要となり、治療開始が約1週間早まると期待されています。
これは患者さんにとって、まさに「時間との戦い」を支援する大きな前進です。
CAR-T療法は非常に高額であると同時に、治療適応となる患者さんは病気の進行が非常に早いケースが多く、1〜2ヶ月の製造期間中に病状が悪化し、治療機会を失うこともありました。
国内製造による1週間の短縮は、文字通り命に直結する価値があると言えます。
テルモ、薬剤取り違えや設定ミス低減「スマートポンプ」新機種発売
テルモは10月29日、薬剤の取り違えや設定ミスを低減するための「スマートインフュージョンシステム」の新機種4機種を発売しました。
新機種のうち2機種はRFIDに対応しており、薬剤ライブラリ(病院側で設定した薬剤の安全な投与ルール)と、ICタグ付きシリンジを自動照合します。
自動照合によって、薬剤の取り違えといったヒューマンエラーを防ぐ仕組みが導入されています。
また、全機種に薬剤投与完了までの残時間表示機能が搭載され、電子カルテと連携して遠隔での確認や記録も可能となり、看護師の業務効率化を図ります。
薬剤の投与ミス(量、種類、速度の間違い)は、医療安全における重大な課題の一つです。
この新機種は、RFIDによる「自動照合」という技術を用いて、人間の「思い込み」や「見間違い」といったヒューマンエラーを物理的に防ごうとするアプローチです。看護師の業務負担軽減と、患者さんの安全向上に直結する重要な技術革新だと評価できます。
食後の血糖値上昇を抑える水稲「越さらり」、新潟県が開発
新潟県農業総合研究所が、消化されにくいデンプン「難消化性でんぷん(レジスタントスターチ)」を多く含む水稲の新品種、「越さらり」を開発しました。
難消化性でんぷんは、小腸で消化されにくく大腸まで届くため、食後の急激な血糖値の上昇を抑える効果が期待されています。
この「越さらり」は、炊飯米に含まれる難消化性でんぷんの量が、「コシヒカリ」の25倍以上と非常に高いことが特徴です。
一方で、収穫量がコシヒカリより2割少なく、食味も良くないため、通常の米飯としてではなく、ブレンド米や健康食品への加工用途での活用が見込まれています。
これは医療そのものではありませんが、日常の「食」を通じた予防医療や健康管理の分野で注目すべき動きです。
糖尿病やその予備群の増加が社会問題となる中、こうした特定の健康機能に特化した農産物が開発されることで、病院食や介護食、あるいは健康志向の強い消費者向けの新しい食品市場が生まれる可能性があります。
医療・社会を取り巻く重要話題
医療業界は、社会全体の動きと密接に関連しています。ここでは、国立大学の組織改革、不適切な広告への対応、医療従事者の働き方に関わる労働規制、さらにはAIの倫理問題など、医療を取り巻く幅広い重要トピックをお伝えします。
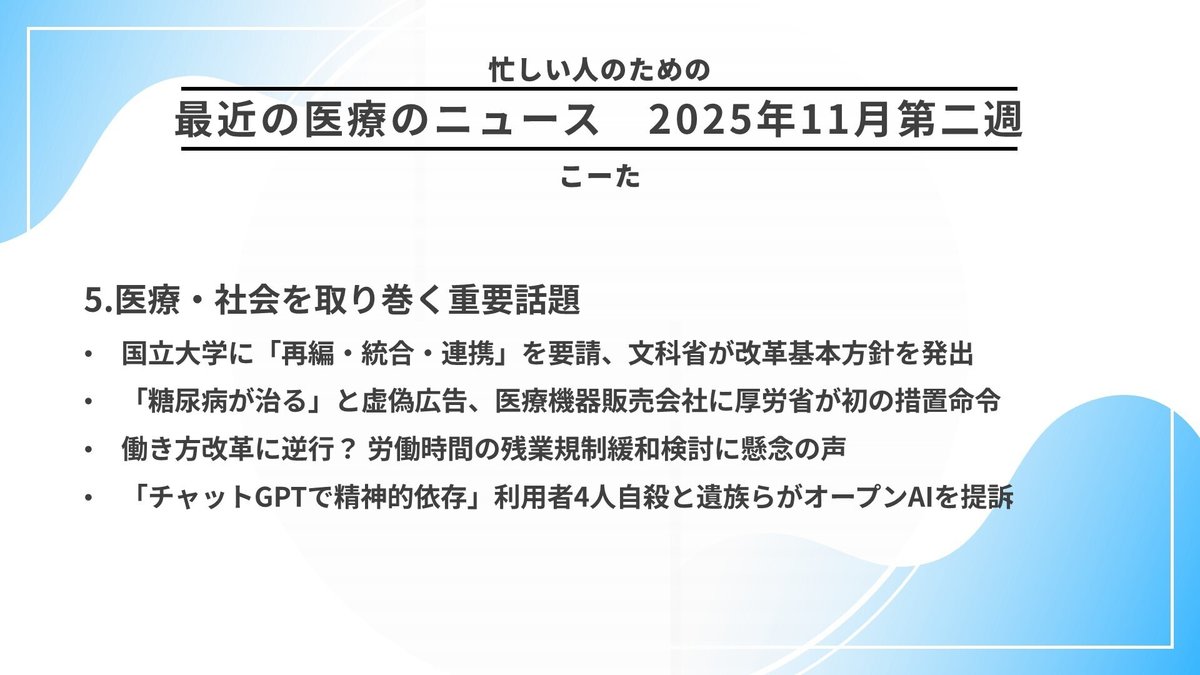
国立大学に「再編・統合・連携」を要請、文科省が改革基本方針を発出
文部科学省は11月7日、国立大学法人などに対し、自大学のリソースだけに頼らず、他の国公私立大学や研究機関との「連携・再編・統合」を通じてミッションの実現を目指すよう求める改革基本方針を発出しました。
国立大学は、2028年度から始まる第5期中期計画にこの方針を反映させる必要があります。
方針では、財務戦略や人事戦略、マネジメント体制の抜本的な強化が求められました。文科省は、運営費交付金の配分などを通じて、各大学の組織改革を促していく考えです。
これは先のニュースで触れた「国立大学病院の経営危機」とも深く関連しています。
大学本体の経営基盤が厳しくなる中、国は「自助努力」として、大学間の連携や再編による経営の効率化・規模の確保を強く求めている形です。
大学病院の経営問題も、大学単体ではなく、こうした大きな枠組みの中で解決策を模索していくことになります。
「糖尿病が治る」と虚偽広告、医療機器販売会社に厚労省が初の措置命令
厚生労働省は11月7日、家庭用電位治療器について「糖尿病が治る」「血液をきれいにする」など、承認されていない効能をうたう虚偽・誇大広告を行ったとして、販売会社「インプレッション」(兵庫県尼崎市)に対し、医薬品医療機器法に基づき再発防止を求める措置命令を出しました。
同法による措置命令は、これが初めてのケースとなります。
同社は全国の営業所で開いた体験会などで、こうした掲示を行っていたとされています。
医療や健康に関する情報は、時に人の命に関わるため、極めて高い正確性と倫理性が求められます。
今回、厚労省が「初の措置命令」という強い対応に出たことは、特に高齢者などを対象とした健康関連商品の不適切な販売手法に対し、国が厳格な姿勢で臨むという明確なメッセージになります。
医療機関としても、患者さんがこのような不確かな情報に惑わされていないか、日頃から注意を払う必要があります。
働き方改革に逆行? 労働時間の残業規制緩和検討に懸念の声
高市早苗首相が打ち出した「労働時間の規制緩和」の検討指示に対し、「働き方改革に逆行する」との懸念が広がっています。
首相は上野賢一郎厚生労働相に対し、労働政策審議会で議論を進めるよう指示しました。
背景には、人手不足に悩む経営側の意向があるとされています。2019年に施行された関連法では、残業時間の上限(月100時間、年720時間以内)が初めて罰則付きで定められましたが、2024年度の過労死などに関する労災補償請求件数は過去最多を更新しており、改革は道半ばです。
規制緩和は、実際の労働時間にかかわらず賃金を支払う「裁量労働制」などを念頭に置いているとされ、望まない長時間労働の増加につながるのではないかと危惧されています。
この議論の行方は、医療・介護業界にとっても極めて重要です。
医師の働き方改革(時間外労働の上限規制)が始まったばかりのタイミングで、社会全体として規制緩和の方向に舵が切られれば、ただでさえ人手不足が深刻な医療現場の労働環境改善に水を差すことになりかねません。
生産性の向上と、働く人の健康確保は、常に両輪で語られるべき課題です。
「チャットGPTで精神的依存」利用者4人自殺と遺族らがオープンAIを提訴
米国の法律事務所は11月6日、対話型AI「チャットGPT」の利用を通じて4人(17〜48歳)が自殺に追い込まれたとして、遺族らが開発元の米オープンAIを提訴したと発表しました。
原告側は、4人が日常的にチャットGPTを利用し、次第に精神的な依存を深めていったと主張。「チャットGPTは専門家に助けを求めるよう導く代わりに、利用者の自殺願望を助長した」と批判しています。
また、オープンAIが安全性テストを短縮し、安全対策が不十分だったとも指摘しています。
AIが社会に急速に普及する中で、その利便性の裏にある「負の側面」が顕在化した、重い事例だと受け止めるべきです。
特にメンタルヘルスの領域において、AIが利用者の孤独感や悩みに寄り添う一方で、適切な専門的介入を怠れば、今回のような深刻な事態を招く危険性があります。
AIの開発側には、より高度な倫理観と安全対策の実装が求められます。
おわりに
今回は、2025年11月第二週の医療・ヘルスケア関連ニュースを、制度改革、病院経営、医療DX、新技術、社会トピックという5つの視点から解説しました。
国立大学病院の赤字拡大や相次ぐ公立病院の経営難、物価高騰に伴う患者負担増の議論など、医療提供体制の厳しさを示すニュースが目立つ一方で、AIやデジタル技術による業務効率化、CAR-T療法の国内製造といった治療の進歩、iPS細胞研究の成果など、未来に向けた前向きな動きも存在しています。
医療を取り巻く環境は今後も大きく変動していきます。
私たち医療関係者や関連ビジネスに携わる者は、こうした変化の兆候を的確に捉え、自院の経営や業務にどう活かしていくか、あるいはどう対応していくかを常に考えていく必要があります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。