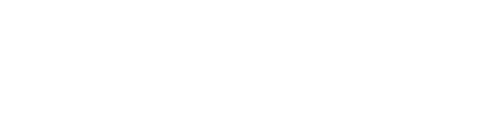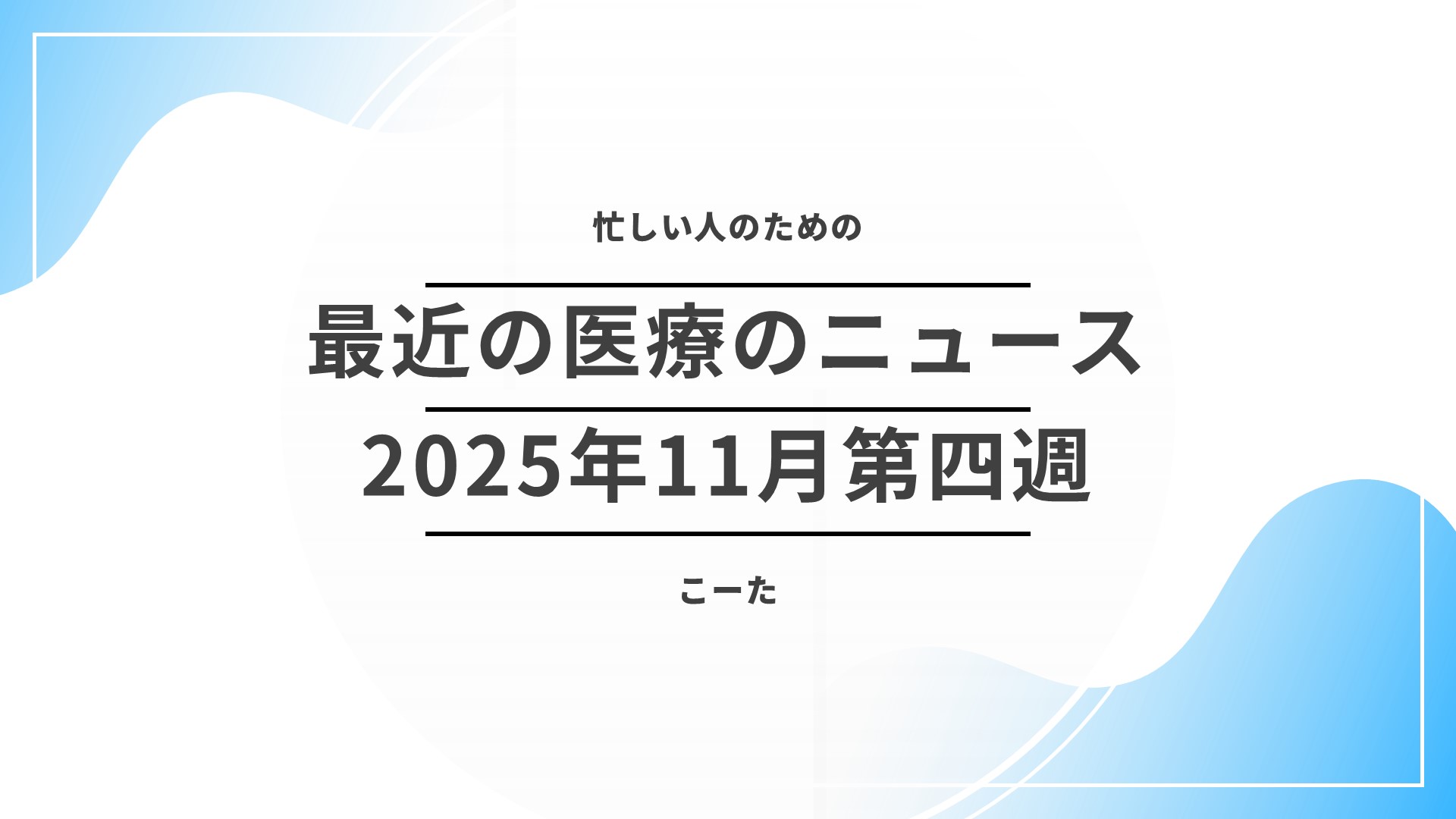はじめに
2026年度診療報酬改定の足音が近づく今、医療業界はかつてない変革の波に直面しています。
物価高騰に伴う賃上げの圧力、加速するAIの実装、そして相次ぐ病院経営の危機——。
本記事では、2025年11月の重要ニュースを毎週厳選し、医業経営コンサルタントの視点で解説します。
表面的な事実だけでなく、その裏にある「構造変化」を読み解くことで、ビジネスや生活に直結する未来の医療の姿が見えてくるはずです。
ぜひ最後までお付き合いください。
 Kota
Kota
35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。
9年間医療事務として外来・入院を担当。
毎月約9億円を請求していました。
現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。
投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。
趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。
Twitterはこちら
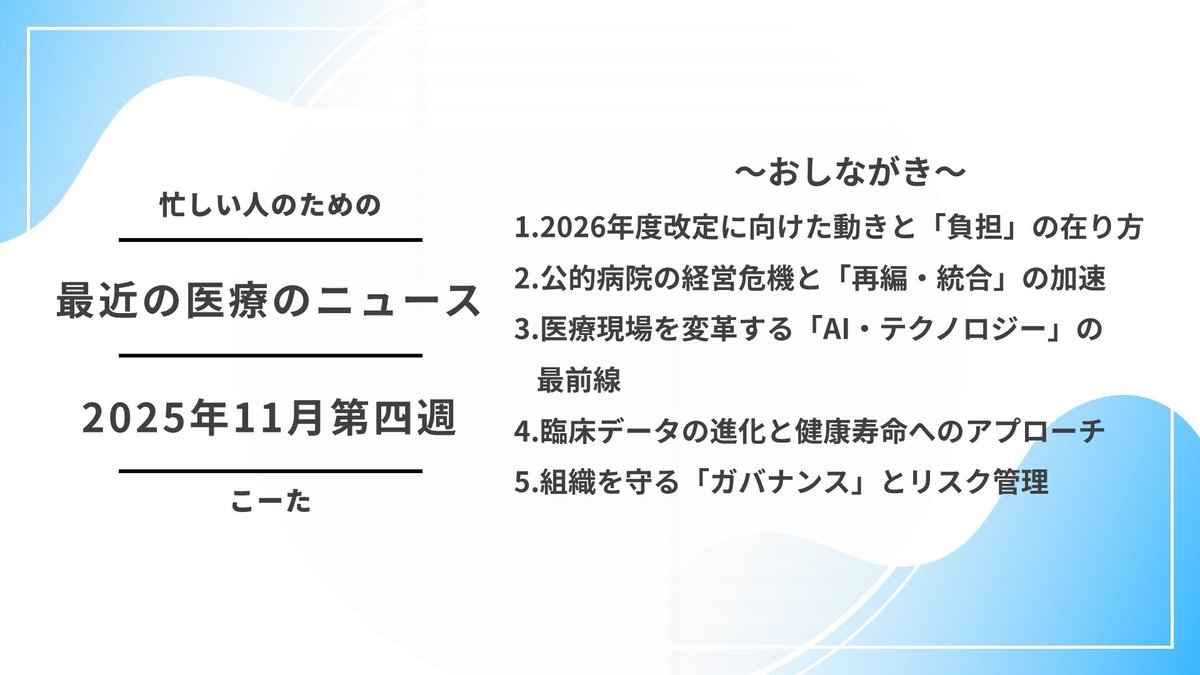
2026年度改定に向けた動きと「負担」の在り方
2026年度の診療報酬改定に向けた議論が、いよいよ本格化しています。
今回の改定議論で中心となるテーマは、物価高騰への対応と、制度を持続させるための「痛み分け」です。
医療現場、患者、そして現役世代。それぞれの立場で何が変わり、どのような負担が求められようとしているのか、最新のニュースをもとに解説します。
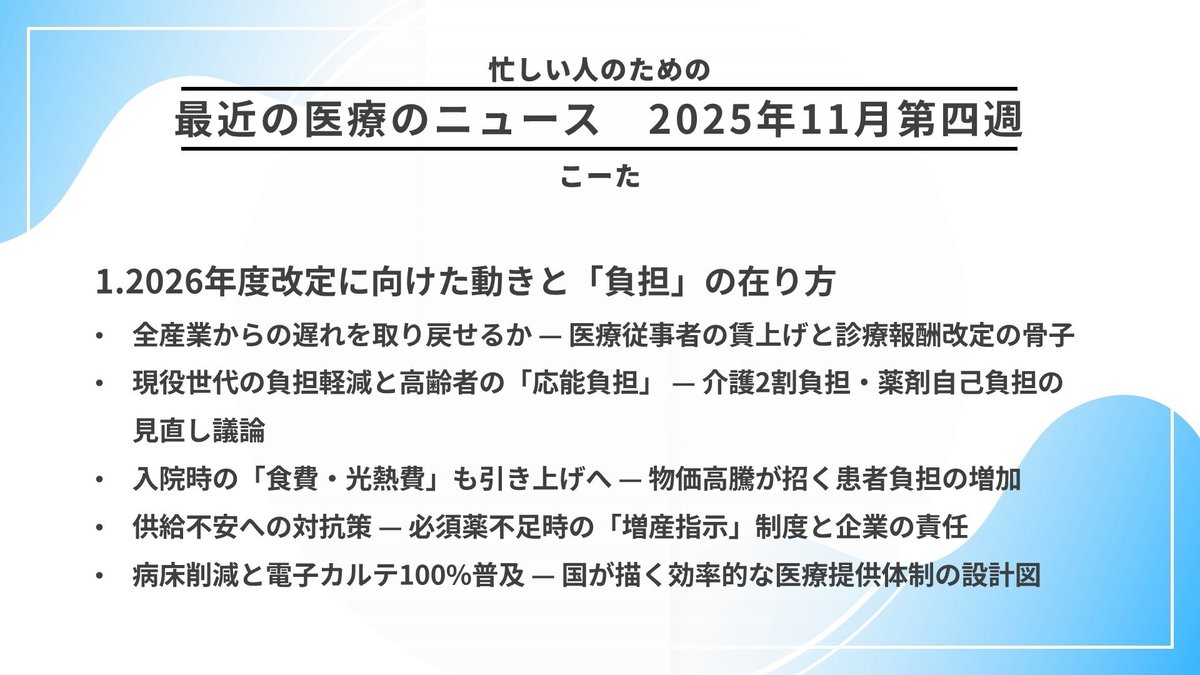
全産業からの遅れを取り戻せるか — 医療従事者の賃上げと診療報酬改定の骨子
政府は2026年度の診療報酬改定に向けた基本方針の骨子案を固めました。
最大の焦点は、医療従事者の「賃上げ」です。
現在、全産業的に賃上げが進む中で、公定価格(国が決めた価格)で運営される医療業界は、物価高騰によるコスト増を価格転嫁できず、賃金水準が他産業から取り残されつつあります。
骨子案ではこの状況を重く見て、人材確保のためにも賃上げが「急務」であると明記されました。
また、なり手不足が深刻な外科医などの処遇改善も盛り込まれています。
長時間労働や緊急手術の負担が大きいにもかかわらず、給与が見合っていない現状を変えるため、働き方改革に取り組む医療機関を評価する方針です。
一方で、単に報酬を上げるだけでなく、AIやICTを活用して業務を効率化することも同時に求められています。
今回の「賃上げ」は単なる待遇改善以上の意味を持っています。
一般企業であればコスト増を商品価格に上乗せできますが、医療機関はそれができません。したがって、診療報酬での手当てが必須となります。
しかし、ここで重要なのは、国がセットで提示している「業務効率化」という条件です。「賃金を上げるための原資は渡すが、その分、AI活用などで人を増やさずに回せる仕組みを作ってほしい」というメッセージとも受け取れます。
経営者としては、賃上げで満足度を高めつつ、同時にDX投資を行わなければ生き残れないという、非常に高度なかじ取りを迫られる改定になるでしょう。
現役世代の負担軽減と高齢者の「応能負担」 — 介護2割負担・薬剤自己負担の見直し議論
少子高齢化が進む中、現役世代の保険料負担をこれ以上増やさないための策として、高齢者にも経済力に応じた負担を求める議論が進んでいます。
注目すべきは介護保険の利用料です。現在は原則1割負担ですが、これを「2割負担」とする対象者の範囲を広げる検討がなされています。
これまでは所得(年金収入など)のみを基準にしていましたが、今回は預貯金などの「金融資産」も考慮に入れる案が浮上しました。
また、医療費においても「OTC類似薬」に関する自己負担の見直しが検討されています。これは、湿布薬や保湿剤など、市販薬でも代用できる軽微な薬については、保険適用を縮小して自己負担を増やそうというものです。
このニュースは、日本の社会保障が「フロー(所得)ベース」から「ストック(資産)ベース」の負担能力評価へ転換しようとしている大きな節目を示唆しています。
資産の把握はマイナンバーとの紐づけなど実務的なハードルが高いですが、現役世代の負担が限界に達している今、避けられない流れと言えます。
また、OTC類似薬の負担増は、患者さんの受診行動を「軽症なら薬局へ」と変える動機づけになります。
医療機関としては、軽症患者の来院数が減る可能性がある一方で、より専門性の高い医療にリソースを集中させるチャンスとも捉えられます。
入院時の「食費・光熱費」も引き上げへ — 物価高騰が招く患者負担の増加
入院した際にかかる食事代や光熱費の負担額についても、引き上げが検討されています。
食材費やエネルギー価格の高騰は、家庭だけでなく病院経営も直撃しています。
現在、入院時の食事代は1食あたり690円と設定されていますが、患者さんの自己負担額(原則510円)を引き上げる方向で調整が進んでいます。
過去2回の引き上げ分も患者負担とされており、今回も同様の流れとなる見込みです。
病院経営の現場を見ると、給食部門は多くの病院で赤字、あるいはギリギリの収支で運営されています。
食材費が上がっても、決められた価格で提供しなければならないため、質を維持しようとすれば病院側で持ち出しが発生することになります。
患者さんにとって負担増は痛手ですが、もし負担額を据え置けば、病院は「食事の質を落とす」か「給食事業から撤退・委託変更する」しかなくなります。
適切な栄養管理と食事の質を維持するためには、ある程度の負担増はやむを得ない措置だと考えられます。
供給不安への対抗策 — 必須薬不足時の「増産指示」制度と企業の責任
ここ数年、ジェネリック医薬品を中心に薬の供給不足が続いていますが、これに対して厚労省が新たな手を打ちました。
抗菌薬や麻酔薬など、生命に関わる重要な75の成分について、不足時やその恐れがある場合に、製薬会社へ「増産」や「輸入」を指示できる新制度が始まりました。
正当な理由なく指示に従わない場合は企業名を公表するという、かなり強い措置です。
これは、医薬品を単なる「商品」ではなく、電気やガスと同じ「インフラ」として国が管理を強化したことを意味しています。
これまでジェネリック医薬品業界は、過度な価格競争により、ギリギリのコストで製造せざるを得ない状況にありました。それが品質不正や供給停止の一因となっていたのです。
今後は「安ければ良い」という時代が終わり、多少コストがかかっても「安定供給できる企業」が選別される時代になります。
医療機関側も、採用薬を決める際に、価格だけでなく供給体制の安定性を重視するよう意識改革が求められます。
病床削減と電子カルテ100%普及 — 国が描く効率的な医療提供体制の設計図
人口減少に伴い、将来的に不要となる病床を減らすための法改正案がまとまりました。
都道府県が主導して病床削減を支援できる仕組みを作り、国が費用を負担することで、過剰な病床の整理を促します。
これと並行して、政府は2030年までに電子カルテの普及率を100%にする目標を明記しました。
「病床削減」と「電子カルテ普及」は、一見別の話に見えますが、実は「少ない人数で医療を回す」という一点でつながっています。
病床を減らすことは、経営者にとっては売上の減少に直結するため、非常に苦渋の決断です。
しかし、地域全体の人口が減る中で無理に規模を維持すれば、共倒れになります。 そこで鍵になるのが電子カルテです。
単に記録をデジタル化するだけでなく、地域全体で患者データを共有し、役割分担をスムーズにするための基盤です。
「病院の規模を適正化し、デジタルでつなぐ」
これが国が描く未来図であり、各病院はこの設計図の中で自院がどう生き残るかを決断する時期に来ています。
公的病院の経営危機と「再編・統合」の加速
地域医療の最後の砦とされる公的病院が、かつてない経営危機に直面しています。物価高や人口減少といった外部環境の変化に加え、長年抱えてきた構造的な問題が限界に達しつつあります。
ここでは、大学病院や市民病院が置かれている厳しい現実と、そこから生まれつつある新たな生き残り策について詳述します。
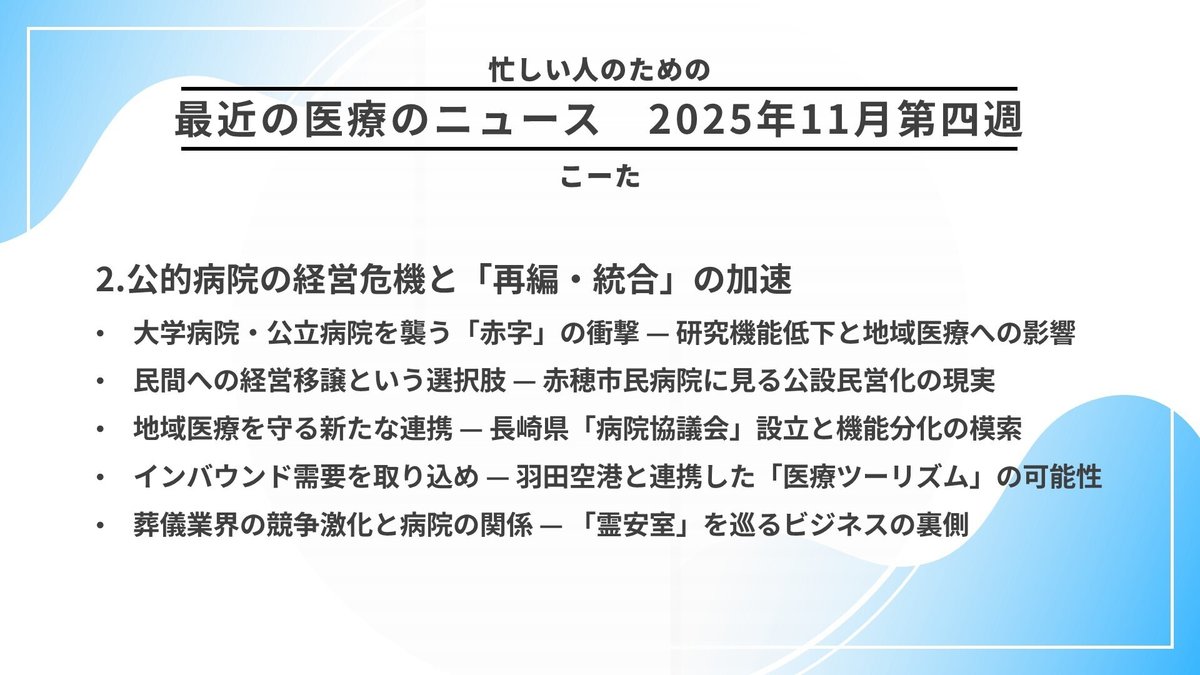
大学病院・公立病院を襲う「赤字」の衝撃 — 研究機能低下と地域医療への影響
日本の医療を牽引してきた大学病院や公立病院の経営が、急速に悪化しています。
全国の大学病院の2024年度の経常損益は、合計で500億円を超える赤字となりました。本来、大学病院は「診療」だけでなく、「研究」や「教育」という重要な役割を担っています。
しかし、光熱費や薬剤費の高騰で赤字が膨らみ、その穴埋めのために医師が診療に追われ、研究に時間を割けないという本末転倒な事態が起きています。
地方の公立病院も同様に追い詰められています。
宮崎県串間市や長野県松本市の市民病院では、医師の退職や分娩の廃止などが引き金となり、黒字から一転して赤字に転落する見通しです。
さらに福岡県大牟田市では、人口が全盛期の半分になったにもかかわらず病院数が多すぎるため、共倒れを防ぐために国立病院機構の病院が自ら病床削減に踏み切りました。
人口減少地域では、既存の医療インフラを維持すること自体が物理的に困難になりつつあります。
このニュースから読み取るべきは、「フルセット型の医療」の終焉です。
これまで自治体病院は「市民のために」と、内科から産科、小児科まであらゆる診療科を揃えようとしてきました。
しかし、医師不足と人口減が進む今、一つの病院ですべてを完結させるモデルは崩壊しています。 特に大学病院の窮状は深刻です。
日本の医学研究力が低下していると言われて久しいですが、その背景には、研究者が「稼ぐこと」を強いられている経営構造の問題があります。
これは将来の医療の進歩を止めることにもなりかねず、国レベルでの資金注入や構造改革が待ったなしの状況です。
民間への経営移譲という選択肢 — 赤穂市民病院に見る公設民営化の現実
巨額の赤字を抱える公立病院の解決策として、「民間の力」を借りる動きが出ています。
兵庫県赤穂市の市民病院は、累積赤字が約74億円に達し、今後も単年度で10億円以上の赤字が見込まれることから、民間の医療法人に運営を任せる「指定管理者制度」の導入を決めました。
「公設民営」と呼ばれるこの手法は、建物の所有権は市に残しつつ、実際の病院運営は民間のノウハウで行うものです。市は、民間ならではの効率的な経営により、救急や産科といった不採算部門も含めた医療体制の維持を目指しています。
公立病院の経営再建において、指定管理者制度への移行は「劇薬」ですが、極めて合理的な選択肢です。公立病院は公務員規定などの縛りがあり、給与体系の変更や迅速なコスト削減が難しい側面があります。
一方、民間法人は意思決定が速く、柔軟な人員配置や調達コストの抑制が得意です。
ただし、丸投げすれば解決するわけではありません。「不採算だが地域に必要な医療」をどこまで維持するか、事前に自治体と民間側で握っておかなければ、収益優先になりすぎて住民サービスが低下するリスクもあります。
地域医療を守る新たな連携 — 長崎県「病院協議会」設立と機能分化の模索
厳しい経営環境の中、個々の病院が競い合うのではなく、手を取り合う動きも始まっています。
長崎県では、公立・民間あわせて80もの病院や団体が参加する「県病院協議会」が設立されました。
経営母体が異なる病院同士が、垣根を越えて一つのテーブルにつき、地域の医療提供体制のあり方を議論し、行政へ提言を行うとしています。
これまで、近隣の病院同士は「患者の奪い合い」をするライバル関係になりがちでした。しかし、この事例は「競合」から「協調」へとフェーズが移ったことを象徴しています。
特に注目すべきは、これが行政主導のトップダウンではなく、病院側からのボトムアップに近い形で進んでいる点です。「自分たちで話し合って役割分担(=機能分化)を決めなければ、共倒れする」という強烈な危機感が現場にある証拠でしょう。
今後は、地域単位で「A病院は救急、B病院はリハビリ」といった役割の棲み分けが、より加速していくと考えられます。
インバウンド需要を取り込め — 羽田空港と連携した「医療ツーリズム」の可能性
公的保険診療の収益が頭打ちになる中、自由診療による新たな収益源の確保も模索されています。
京浜急行やJTBなどが連携し、羽田空港を利用する訪日外国人(=インバウンド)を対象とした「医療ツーリズム」の実証実験が始まります。
これは、空港での乗り継ぎ時間などを活用し、近隣の病院で人間ドックを受け、さらに温泉体験などをセットにするというプランです。
「医療ツーリズム」は長年期待されながらも、言語の壁や受け入れ体制の不備でなかなか定着しませんでした。
しかし、今回の取り組みは「空港のスキマ時間」にターゲットを絞り、「検診」というリスクの低い医療サービスと、日本の観光資源である「温泉」を組み合わせた点が秀逸です。
病院にとっては、保険診療外の収益を得られるだけでなく、日本の高度な医療機器やサービスを海外にアピールする機会にもなります。公的保険に依存しない収益の柱を作るための、具体的な第一歩として評価できます。
葬儀業界の競争激化と病院の関係 — 「霊安室」を巡るビジネスの裏側
少し視点を変えて病院の「出口」に関わるニュースです。
病院の霊安室における葬儀社選びが、激しい競争に晒されています。 遺族の多くは葬儀社を決めていない状態で病院で亡くなるため、霊安室業務を担当する葬儀社がそのまま葬儀を受注するケースが多くなります。
そのため、公立病院の霊安室担当を決める入札に多数の業者が殺到したり、私立病院では指名を得るために過剰な営業が行われたりする実態があります。
これは医療の本質とは離れますが、病院経営やリスク管理の観点からは無視できない問題です。 病院側としては、特定の業者との癒着はコンプライアンス上の大きなリスクとなります。
一方で、霊安室の管理をプロである葬儀社に任せることは、看護師の負担軽減につながるメリットもあります。 大切なのは「透明性」です。患者さんやご遺族が、混乱の中で不本意な契約を結ばされることがないよう、病院側も業者任せにせず、節度ある運用ルールを徹底する必要があります。
医療現場を変革する「AI・テクノロジー」の最前線
医療の世界にもAIやロボット技術の波が押し寄せています。
「いつか実現する未来」の話ではなく、すでに現場の働き方や治療のあり方を劇的に変えつつある最新事例を紹介します。
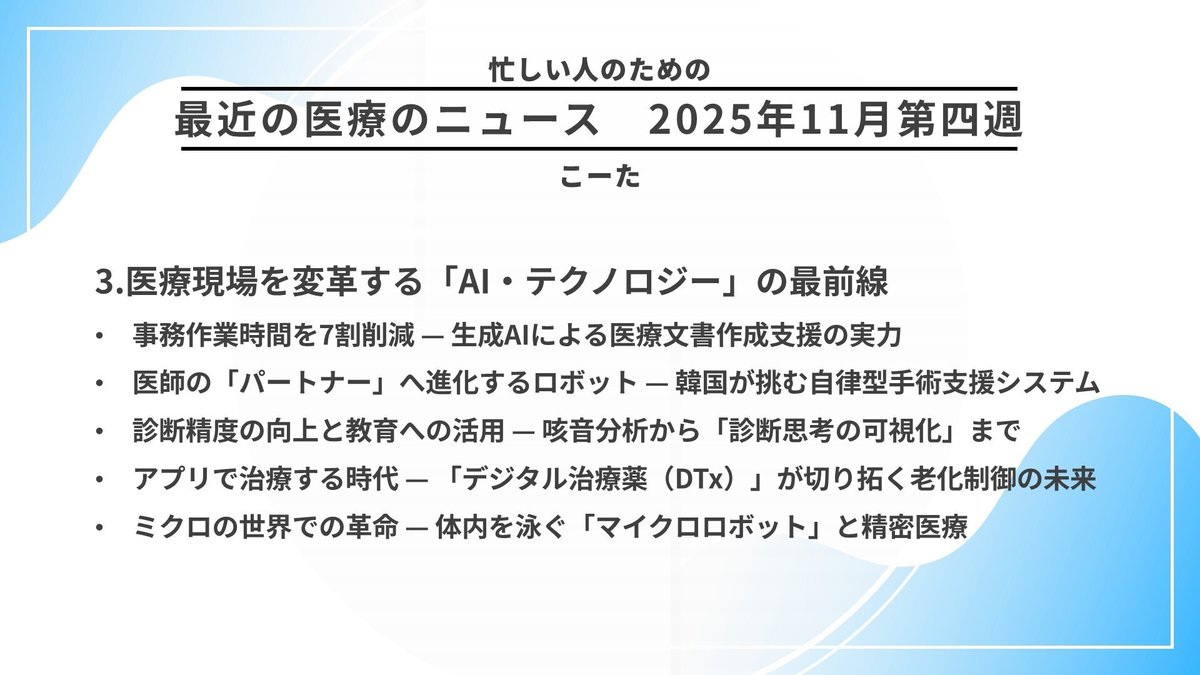
事務作業時間を7割削減 — 生成AIによる医療文書作成支援の実力
医療現場、特に医師の長時間労働の大きな要因の一つが、膨大な書類作成業務です。この課題に対し、生成AIが目に見える成果を上げ始めました。
名古屋医療センターでは、富士通Japanが開発した生成AIサービスを導入し、退院時に作成する要約書類(=退院サマリ)の作成時間を劇的に短縮しました。
これまで患者一人あたり平均28分かかっていた作業が、わずか8分へと短縮され、約7割もの効率化を実現しています。
また、富士通Japan自身も、従来の電子カルテベンダーという立場から「デジタルホスピタルサービス」事業者へと舵を切りました。
2030年にはAIを活用した医療変革で市場シェアの拡大を狙っており、安全な閉域ネットワークを用いたクラウド環境で、個人情報保護と利便性を両立させる仕組みを構築しています。
これは、医療DXにおける「決定打」になり得る事例です。
これまで医師の働き方改革といえば、看護師や事務職員へのタスク・シフトが中心でしたが、人手不足の中ではそれも限界がありました。
しかし、生成AIへの業務移譲は、文句も言わず24時間稼働してくれる強力な助手を雇うようなものです。
名古屋医療センターの試算では年間約5,000万円のコスト削減効果が見込まれていますが、それ以上に「医師が患者と向き合う時間」や「休息の時間」を取り戻せることの価値は計り知れません。
経営者としては、導入コストとセキュリティリスクを天秤にかけても、十分に投資回収が見込めるフェーズに入ったと判断できます。
医師の「パートナー」へ進化するロボット — 韓国が挑む自律型手術支援システム
手術支援ロボットといえば米国の「ダヴィンチ」が有名ですが、これは医師が操縦席で操作する「道具」に過ぎませんでした。
今、その概念を超えようとしているのが韓国です。 韓国政府は、AIを搭載したヒューマノイド型の手術支援ロボット開発プロジェクト「ミケランジェロ・システム」を進めています。
このロボットの最大の特徴は、「自律的な判断」です。執刀医の指示を待つだけでなく、手術の流れ(=文脈)を理解し、吸引や器具の受け渡しといったサポート動作を自ら判断して行います。
2030年までに世界をリードすることを目指し、国を挙げて開発に取り組んでいます。
このニュースの衝撃は、ロボットが単なる「延長アーム」から、意思を持った「パートナー」へと進化しようとしている点です。
熟練の看護師や助手が阿吽の呼吸で医師をサポートするように、AIロボットがその役割を担う未来が描かれています。 日本も医療ロボット開発には力を入れていますが、韓国のような「国家戦略としてのスピード感」には脅威を感じます。
手術室の人員配置を最小限にできるこの技術が実用化されれば、外科医不足やスタッフ確保に悩む病院経営にとって、強力な解決策となるでしょう。
診断精度の向上と教育への活用 — 咳音分析から「診断思考の可視化」まで
AIによる診断支援も、より身近で、より教育的な側面を持ち始めています。
インドの研究チームは、咳の音だけで呼吸器疾患のリスクを判定するAI「Swaasa」の有用性を実証しました。
スマートフォンのような簡易なデバイスでスクリーニングが可能になれば、発展途上国や僻地医療での強力な武器になります。
一方、ハーバード大学は「診断のプロセス」を可視化するAI「Dr.CaBot」を開発しました。従来のAIは「答え」だけを出しがちでしたが、このAIは「なぜその病気を疑うのか」「なぜ他の病気ではないのか」という思考過程を提示できるため、医学生や若手医師の教育ツールとして期待されています。
またスペインでは、卵巣腫瘍の良性・悪性を高精度に識別するAIが開発され、診断のばらつきを減らす成果を上げています。
これまでの診断AIには、なぜその結論になったか分からない「ブラックボックス問題」があり、医師が最終判断をする際の不安要素でした。
しかし、思考過程を説明できるAIの登場は、医師とAIの信頼関係を深め、ダブルチェック体制を強固にします。 また、「咳の音」のような非侵襲的なデータを用いた診断は、患者さんの受診ハードルを劇的に下げます。
これは、病気の早期発見につながるだけでなく、クリニックなどの初診患者を増やすマーケティング的な側面でも注目すべき技術です。
アプリで治療する時代 — 「デジタル治療薬(DTx)」が切り拓く老化制御の未来
薬を飲む代わりに、アプリを使う。そんな「デジタル治療薬(=DTx)」が、韓国を中心に急成長しています。
DTxは医師の処方が必要な「医療機器」として扱われ、AIが患者の生活データを解析し、不眠症改善や認知機能トレーニングなど、一人ひとりに最適な行動療法を提供します。
韓国ではすでに不眠症治療アプリなどが承認されており、さらには老化の進行を食い止めたり「逆転」させたりすることを目指す研究も進んでいます。
日本でも禁煙治療アプリなどが保険適用されていますが、韓国の動きはさらに活発です。製薬会社にとっては脅威にも見えますが、新たな収益源でもあります。
病院経営の視点では、薬物療法では効果が出にくい生活習慣病やメンタルヘルス領域において、DTxは有効な選択肢になります。
また、通院の合間の自宅でのケアをアプリが担ってくれるため、治療の脱落を防ぎ、患者エンゲージメントを高めるツールとしても機能します。
「薬を出して終わり」ではない、伴走型の医療サービスへの転換点と言えるでしょう。
ミクロの世界での革命 — 体内を泳ぐ「マイクロロボット」と精密医療
目に見えないミクロの世界の話です。
中国科学院が、髪の毛の太さよりも小さい40マイクロメートルのロボットを開発しました。 この極小ロボットは、磁力で操作でき、特定の細胞をつかんで運んだり、薬剤を患部に直接届けたりすることができます。
将来的には、体内に入り込んで手術を行う「見えない助手」としての活躍が期待されています。
まだ基礎研究の段階ですが、これは医療の「低侵襲化(=体への負担を減らすこと)」の究極形です。
開腹手術から腹腔鏡手術、そしてロボット手術へと進化してきましたが、最終的には「切らずに治す」時代が来るかもしれません。
こうした破壊的イノベーションは、既存の外科手術の設備や技術を陳腐化させる可能性があります。
経営者としては、今すぐ導入するものではありませんが、10年、20年先の医療施設のあり方を考える上で、常にウォッチしておくべき技術トレンドです。
臨床データの進化と健康寿命へのアプローチ
医療の進歩は、新しい薬や手術法の開発だけではありません。
蓄積された「データ」をどう活かすか、そして医療機関そのものが地域の中でどうあるべきかという「場の再定義」が、私たちの健康寿命を延ばす鍵となりつつあります。がん生存率の最新データや、大学キャンパスを活用した新しい高齢者ケアの形など、未来へのヒントとなる事例を解説します。
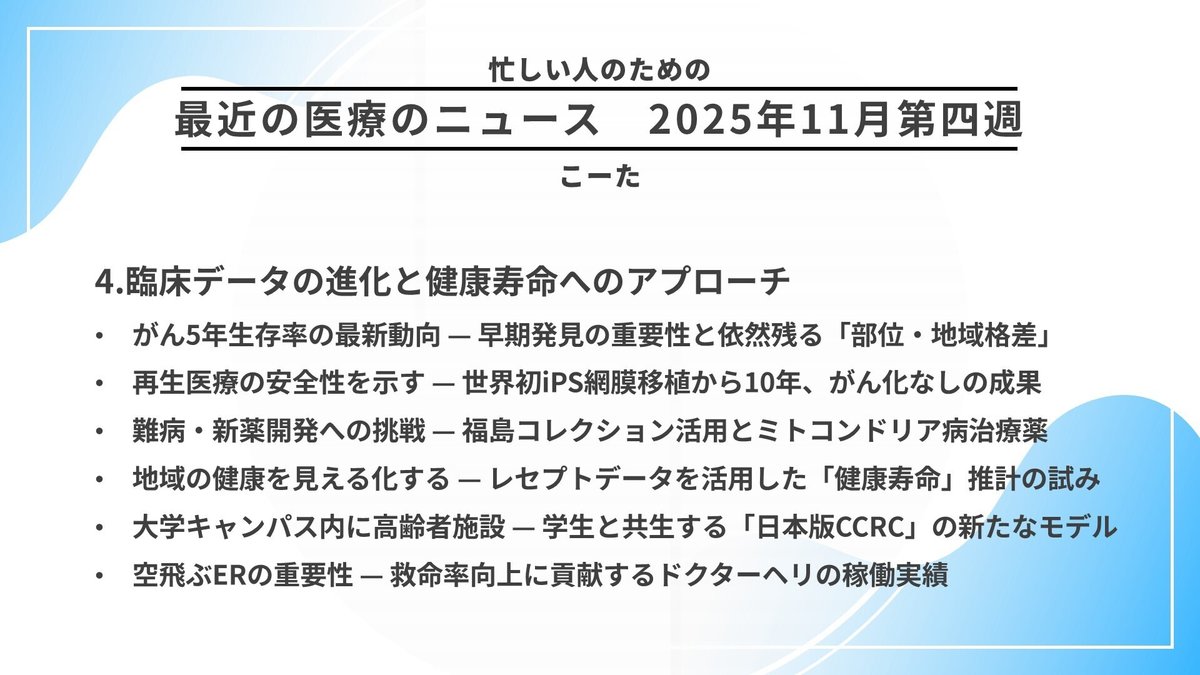
がん5年生存率の最新動向 — 早期発見の重要性と依然残る「部位・地域格差」
国立がん研究センターなどの研究班が、全国規模で集計した「がん5年生存率」の最新結果を公表しました。
今回は約255万件という過去最大規模のデータを分析しています。
結果を見ると、胃がんは約64%、大腸がんは約67%と高い水準を維持し、過去の調査と比較して前立腺がんや白血病などで生存率の大幅な向上が確認されました。
一方で、すい臓がんや胆のうがんなどは依然として低く、部位による治療成績の差は歴然としています。
また、今回のデータで浮き彫りになったのは「地域差」です。
胃や肺などの検診受診率が低い地域(特に北海道や東北の一部など)では、生存率も低い傾向が見られました。
逆に、乳がんや子宮がんでは地域差が少なく、これは全国的に標準治療が浸透していることを示唆しています。
このデータは2012年から2015年の診断例に基づいているため、現在のオプジーボなどの新薬の効果はまだ完全には反映されていません。
しかし、「検診率の低い地域は生存率が低い」という相関関係が数字で示された意義は大きいです。 ビジネスパーソンの皆さんにとっては、「どこに住んでいるか」で生存率が変わるリスクがあるという現実を突きつけられた形です。
企業検診の枠を超えて、自治体検診をどう受けるか、あるいは従業員にどう受けさせるかが、命を守る実質的な防衛策になります。
医療機関側も、単に治療を待つだけでなく、検診への動機づけを強化することが、地域の生存率向上への最短ルートだと言えます。
再生医療の安全性を示す — 世界初iPS網膜移植から10年、がん化なしの成果
再生医療の実用化に向けた、極めて重要なマイルストーンが達成されました。
2014年、理化学研究所などのチームが世界で初めて行った「iPS細胞」を使った網膜移植手術。その患者さんの術後10年の経過が報告され、移植した細胞が「がん化」することなく定着し、視力も維持されていることが確認されました。
iPS細胞は、どんな細胞にもなれる万能性を持つ反面、増殖能力が高すぎて「がん」になってしまうリスクが懸念されていました。
今回、10年という長期にわたり安全性が確認されたことは、目の病気だけでなく、パーキンソン病や心臓病など、他分野への応用を後押しする強力なエビデンスとなります。
再生医療は長らく「夢の技術」であり、投資対象としても「ハイリスク・ハイリターン」な領域でした。
しかし、この「10年の安全性」という事実は、この技術が「実験段階」から「計算できる治療オプション」へとフェーズ移行したことを意味します。
今後は、治療コストをどう下げるかという経済性の議論に移っていくでしょう。
現在はオーダーメイドに近い形で作られていますが、備蓄細胞を使うなどして量産化が進めば、一般的な病院でも再生医療が受けられる未来が現実味を帯びてきます。
難病・新薬開発への挑戦 — 福島コレクション活用とミトコンドリア病治療薬
大学病院の経営難が叫ばれる中、大学ならではの研究力が光るニュースも届いています。
東北大学は、難病「ミトコンドリア病」の治療薬候補「MA-5」の臨床試験を開始します。これは腎臓病や難聴の改善も期待される薬で、iPS細胞を活用して効果を確認したアカデミア発の創薬です。
また、福島県立医科大学は、明治グループの製薬会社と提携し、次世代の医薬品である「mRNA医薬品」の開発に乗り出します。ここで鍵となるのが、同大が保有する「福島コレクション」と呼ばれる膨大な生体試料データです。
これらのニュースは、大学病院の生き残り戦略を示唆しています。
診療収益だけで赤字を埋めるのは限界がありますが、大学には「知財」と「データ」という資産があります。 特に福島医大の事例は、大学内に眠っていた検体やデータを「福島コレクション」としてブランド化し、企業と組むことで新たな価値を生み出しています。
ただ研究して論文を書くだけでなく、企業と連携して「実用化」し、そのリターンを研究費に回す。こうしたエコシステムを作れるかどうかが、今後の大学病院の優勝劣敗を分けることになるでしょう。
地域の健康を見える化する — レセプトデータを活用した「健康寿命」推計の試み
「健康寿命を延ばしましょう」というスローガンはよく聞きますが、具体的にどうすれば延びるのか、成果はどう測るのかは曖昧でした。
京都府立医科大学と京都府綾部市は、診療報酬明細書などのビッグデータを使い、市町村単位かつ「1カ月ごと」に健康寿命を推計するシステムの共同研究を始めます。
これまでは数年に一度、都道府県単位でしかわからなかった健康指標が、リアルタイムに近い形で見えるようになります。
この研究によって、「この地域は高血圧による健康寿命の短縮が目立つから、減塩キャンペーンをしよう」といった、ピンポイントな対策が可能になります。
これは自治体経営におけるDXの好例です。これまでの保健事業は、経験則や大まかな傾向で行われがちでしたが、データに基づいて「どの病気が健康寿命を縮めているか」を可視化することで、予算を投じるべきポイントが明確になります。
企業経営で言うところのKPI管理が可能になるわけで、限られた財源で最大の予防効果を上げるための強力なツールになるはずです。
大学キャンパス内に高齢者施設 — 学生と共生する「日本版CCRC」の新たなモデル
少子化で学生が減る大学と、高齢化で施設が足りない介護業界。この二つを結びつける試みが神戸大学で始まります。
キャンパス内の敷地に、学研グループと協力して認知症グループホームやサービス付き高齢者向け住宅を建設し、学生マンションも併設します。
単に同居するだけでなく、日常的に学生と高齢者が交流し、そこから得られるデータを認知症予防の研究に活かすという「日本版CCRC(=生涯活躍のまち)」のモデルです。
大学にとって「キャンパスの余剰地」は未活用の資産です。
ここに高齢者を呼び込むことは、土地の有効活用だけでなく、医学部や看護学部の学生にとって最高の「実習の場」を提供することになります。
一方、高齢者にとっても、若者に囲まれて暮らすことは刺激になり、認知機能の維持にプラスに働きます。大学が「教育の場」から、多世代が共生する「地域の生活拠点」へと役割を再定義する、非常にスマートな戦略です。
空飛ぶERの重要性 — 救命率向上に貢献するドクターヘリの稼働実績
地域医療を空から支える「ドクターヘリ」の話題です。
静岡県の順天堂大学静岡病院では、ドクターヘリによる診療人数が全国最多となりました。救急車では間に合わない重症患者のもとへ医師を派遣し、現場で治療を開始することで、救命率を劇的に向上させています。
しかし課題もあります。
ヘリが着陸できる場所は事前に登録されていますが、砂ぼこりや騒音への苦情から、登録場所が増えない、あるいは使えないという問題が起きています。
ドクターヘリは「搬送時間の短縮」だけでなく、「治療開始の早期化」に最大の価値があります。まさに「空飛ぶER」です。
しかし、どんなに優れたハードウェアがあっても、それを受け入れる地域の理解がなければ機能しません。
「うるさいから近くに降りるな」という住民感情と、「助かる命を助けたい」という公益性のバランスをどうとるか。
これは医療機関だけの問題ではなく、行政と住民が話し合って解決すべき、地域の「民度」や「合意形成」に関わる課題と言えます。
組織を守る「ガバナンス」とリスク管理
医療の質や経営効率以前の問題として、組織の存続そのものを揺るがすのが「不祥事」です。
今週は、大学病院という権威ある組織での汚職と、地方病院でのSNSによる情報漏洩という、対照的かつ衝撃的なニュースが飛び込みました。
これらは決して「他山の石」ではなく、どこの組織でも起こりうるリスクです。
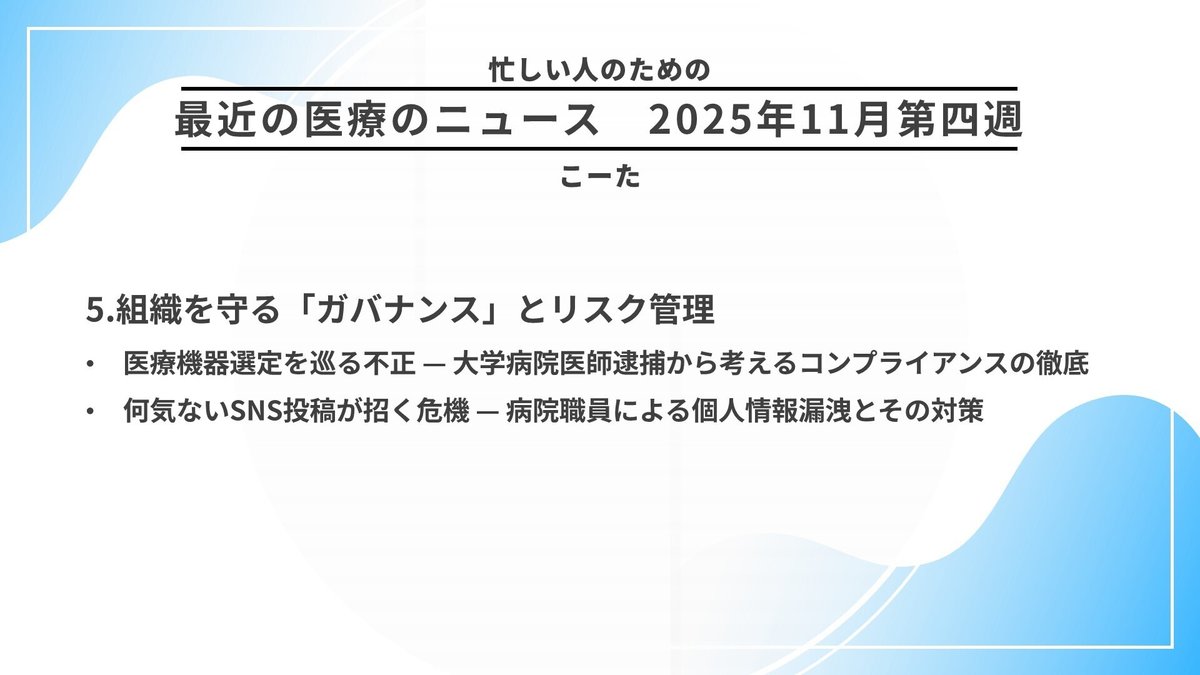
医療機器選定を巡る不正 — 大学病院医師逮捕から考えるコンプライアンスの徹底
日本の医療の最高峰とも言える東京大学医学部附属病院で、衝撃的な事件が起きました。
整形外科の准教授が、医療機器メーカー「日本エム・ディ・エム」側から、自社のインプラント製品を使い続ける見返りに賄賂を受け取ったとして、収賄容疑で逮捕されたのです。
国立大学の医師は「みなし公務員」となるため、金銭の授受は重い罪になります。今回悪用されたのは「奨学寄付金」という制度でした。
本来は研究のために企業が寄付するものですが、実際には約150万円が私的なパソコン購入や親族への贈り物に流用されていました。
医療機器の納入を巡る汚職は後を絶たず、昨年から今年にかけても、国立がん研究センター東病院や東京労災病院などで同様の逮捕者が出ています。
この事件の根深さは、「メーカー選定の権限が現場の医師個人に集中しすぎている」という構造的な問題にあります。 特に整形外科や循環器内科などが使うカテーテルやインプラントは非常に高額で、どのメーカーを使うかで企業の売上が億単位で変わります。
そのため、営業攻勢も激化しやすく、今回のように「研究への寄付」という隠れ蓑を使った癒着が生まれやすい土壌があります。 経営側としては、薬剤や機器の採用決定プロセスを透明化する(=委員会での審査を厳格化し、個人の裁量を減らす)しかありません。
「優秀な先生だから」と聖域化せず、定期的に外部の目を入れるガバナンス体制が機能していたか、改めて自院を点検する必要があります。
何気ないSNS投稿が招く危機 — 病院職員による個人情報漏洩とその対策
もう一つは、北海道の岩見沢市立総合病院で起きた、非常に現代的なトラブルです。
窓口業務を委託されていた会社の20代の職員が、自分のスマートフォンで患者さんの受付状況モニターを撮影し、SNSに投稿してしまいました。
これにより、患者20人分の氏名や年齢などが流出しました。 悪質だったのは、情報の転売などが目的ではなく、「リアルな日常を共有するアプリ」への投稿だった点です。
「今すぐ投稿しないといけない」というアプリ特有の遊び感覚に急かされ、仕事中であることや個人情報が映り込んでいることへの意識が飛んでしまったのです。
投稿は数時間で削除されましたが、病院側は対象の患者全員への謝罪に追われ、当該職員は業務から外されました。
正直なところ、収賄事件よりもこういったニュースの方に恐怖を感じる経営者の方が多いのではないでしょうか。
なぜなら、悪意のない「承認欲求」や「つながりへの渇望」が引き起こした事故だからです。
デジタルネイティブ世代にとって、スマホで日常を切り取ってシェアすることは呼吸と同じです。そのため、従来の「守秘義務研修」で誓約書を書かせるだけでは、この種のリスクは防ぎきれません。
「業務エリアへの私用スマホの持ち込みを物理的に禁止する」「ロッカーに預けさせる」といった、性悪説に基づいたハード面での対策が必要なフェーズに来ています。
性善説で運用するには、SNSの誘惑はあまりにも強大すぎます。
おわりに
今月のニュースに通底しているのは、「従来の延長線上に未来はない」という冷徹な事実です。
人手不足をAIで補い、赤字部門を再編し、データで健康を守る。痛みや摩擦を伴う変化ですが、これは日本の医療が持続可能な形へと生まれ変わるための産みの苦しみとも言えます。
私たち一人ひとりにとっても、医療は「ただ受けるもの」から「選び、関わるもの」へと変わりつつあります。
変化の激流を乗り越え、賢い選択をするための羅針盤として、今回の解説が少しでも役立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。