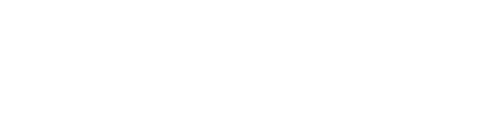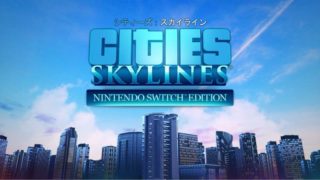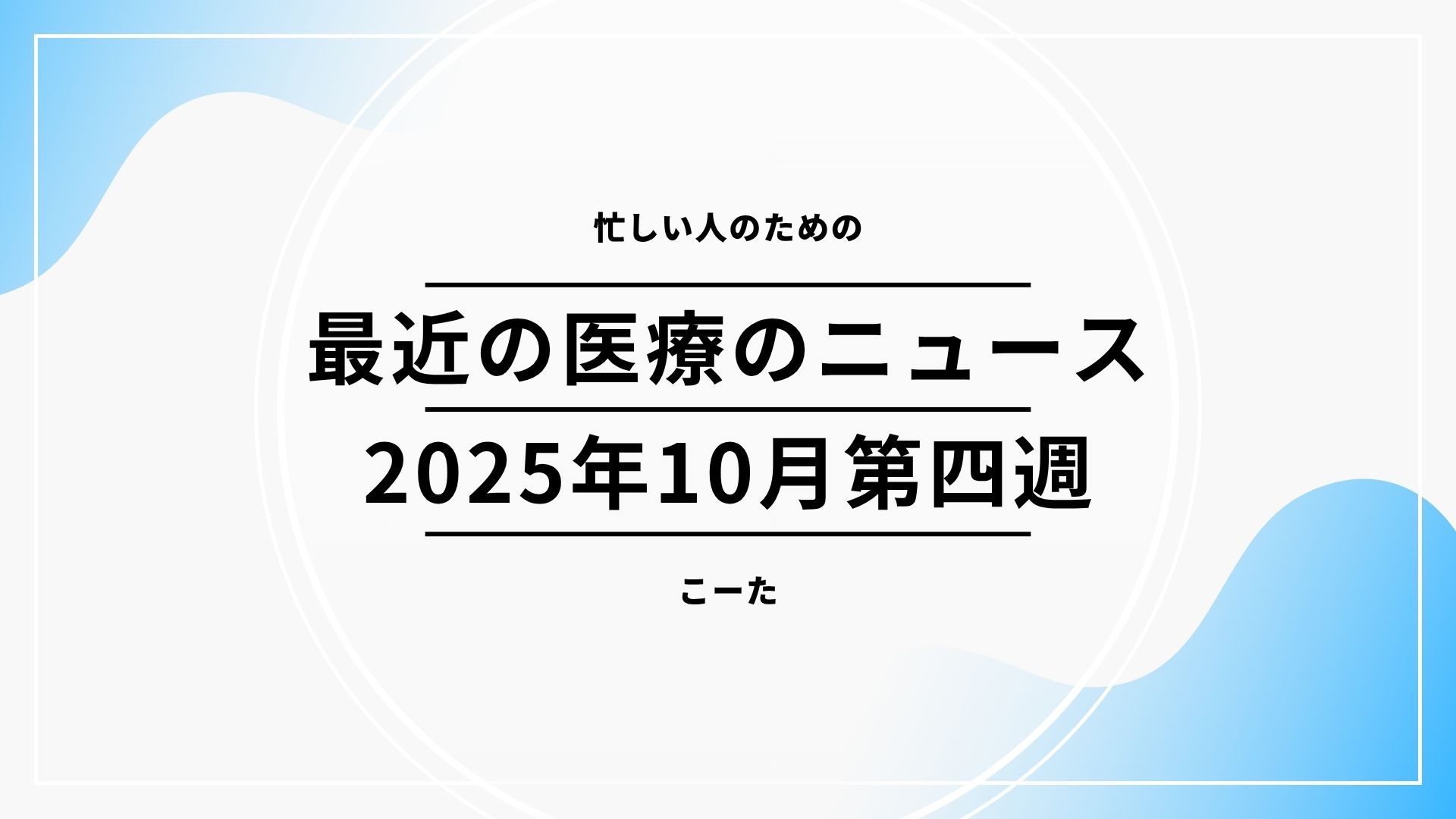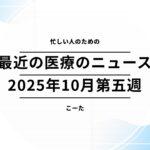- はじめに
- 行政・診療報酬の最新動向
- 病院経営の現実
- 兵庫県立3病院、130床休止へ:加速する公立病院の経営悪化と機能縮小
- 京都府立医科大、過去最大35億円の赤字:大学病院も例外ではない構造的赤字
- 鹿児島県立5病院、未収金1億円超え:連帯保証人代行と債権管理の強化
- 沖縄県立病院、人件費削減を要請:賃上げと働き方改革の裏で進む現場負担増
- 茨城県立3病院も赤字15億円:給与費増が直撃、収益改善の難しさ
- 松本市立病院、分娩廃止を決定:医療事故と医師確保難が招く地域医療の縮小
- 富山大病院、CFで消化器外科医育成資金1千万円達成:新たな資金調達と医師確保策
- 鳴門病院、診療報酬6,460万円を過大請求:内部ガバナンスと算定ルールの再点検
- 江別谷藤病院、負債25億円で経営譲渡:給与未払いと事業承継のリアル
- 医療DX・AI活用の最前線
- 先進医療と市場の動き
- 経営課題とセキュリティリスク
- 世界から見る医療の潮流
- おわりに
はじめに
全国の公立病院で巨額赤字や病床休止が相次ぎ、病院倒産も過去最多ペースとなるなど、医療経営は深刻な局面を迎えています。
物価高騰と人件費増が収益を圧迫する一方、看護記録AIや遠隔ロボット手術、再生医療「アクーゴ」の承認など、DXや新技術が現場の課題を解決する光も見えています。
今週もこの厳しい「経営の現実」と「未来への投資」という二極化する最新動向を、知っていただければ幸いです。
 Kota
Kota
35歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。
9年間医療事務として外来・入院を担当。
毎月約9億円を請求していました。
現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。
投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。
趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。
Twitterはこちら
行政・診療報酬の最新動向
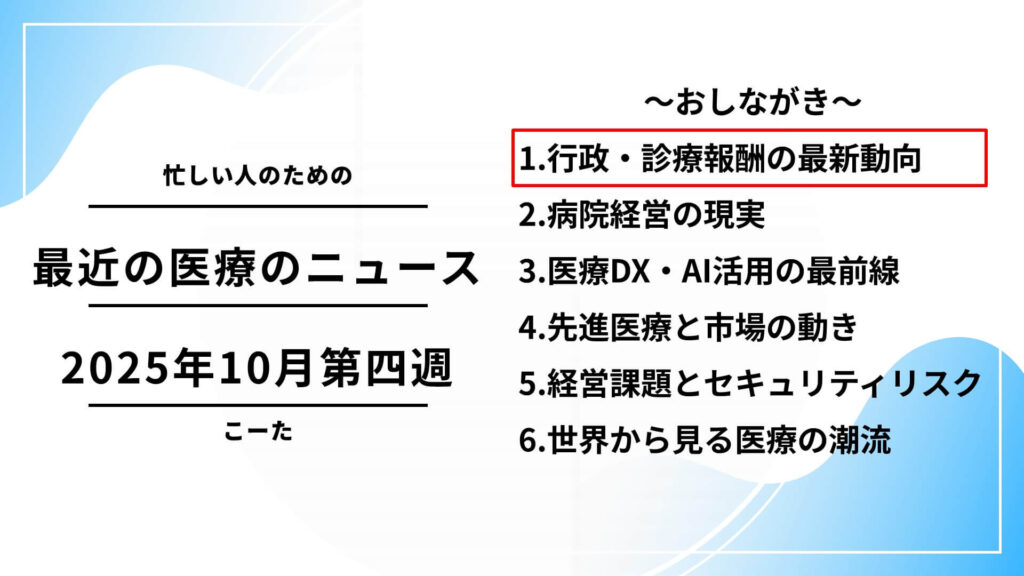
医療界を取り巻く「ルール」と「お金」に関する重要な動きが集中しました。新しい治療法への期待と、既存の保険適用の見直しという「アメとムチ」のような議論が同時に進んでいます。
また、病院経営の外部環境も、新たな収益源の模索と、深刻なコスト増への対策要求という、経営の根幹に関わるトピックが表面化しています。
再生医療「アクーゴ」出荷制限解除へ:新市場誕生と薬価の行方
まずは、再生医療という新しい分野での明るいニュースです。
脳損傷による運動まひの改善が期待される再生医療製品「アクーゴ」(サンバイオ)が、10月16日に厚生労働省の専門家部会で出荷制限の解除が了承されました。
昨年7月に条件付きで承認されていましたが、品質に関する追加データが必要な状態が続いていました。今回、そのデータが揃ったことで、いよいよ販売に向けた最終段階に入ります。
OTC類似薬の保険適用見直し議論:患者負担増と医療費抑制のジレンマ
新しい高額医療が登場する一方で、既存の医療費をどう抑制するかという、いわば「逆向き」の議論も始まっています。
10月16日、厚労省の部会で、市販薬(OTC)と成分や効き目が似た「OTC類似薬」の保険適用を見直す議論が開始されました。
OTC類似薬とは、例えば一部の湿布薬やビタミン剤、アレルギー治療薬などを指します。現在は1~3割の自己負担で処方されますが、この負担割合を引き上げるか、あるいは保険適用から外すかが焦点となっています。
これは「国民が納める保険料の抑制」を目的とした、聖域なき見直しの一環です。医療費削減を掲げる政党の動きも背景にあります。
しかし、部会でも指摘されている通り、アレルギーなどの慢性疾患で定期的に薬が必要な患者さんや、低所得層の方々にとっては、実質的な負担増に直結してしまいます。
「市販薬で買えるものは自分で」という論理ですが、保険から外れることで適切な受診が遅れたり、飲み合わせのリスクが高まったりする懸念もあります。
財政論と患者さんの生活実態との間で、非常に難しい舵取りが求められています。
医療インバウンド実証事業(上限500万円)公募開始:外国人患者受入体制構築の好機か
国内の保険診療が厳しさを増す中、政府は「医療インバウンド(外国人患者の受け入れ)」を新たな成長戦略として推進しています。
厚労省は10月15日、この実証事業に参加する医療機関の公募を開始しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202923_00030.html
選定されれば、1施設あたり最大500万円(税込み)の事業費が拠出されます。金額自体は大きくないものの、政府の「伴走支援」を受けながら、外国人患者受け入れのノウハウを蓄積できる点は大きな魅力です。
診療報酬「大幅引き上げ」を医療団体が要求:物価高騰と経営難の板挟み、年末改定の焦点
次は、医療現場の悲鳴とも言えるニュースです。日本医師会(日医)などが参加する「国民医療推進協議会」が14日、医療サービスの対価である「診療報酬」の「大幅な引き上げ」を国に求める決議を採択しました。
この背景にあるのは、全国的な病院経営の悪化です。物価や光熱費の高騰、そして人材確保のために必須である職員の賃上げ。こうしたコスト増に対し、収入源である診療報酬が全く追いついていないという現実があります。
日医の松本吉郎会長が「前例のない大規模で抜本的な対応が必要」と強調している通り、現場の危機感は非常に強いです。
2025年度補正予算による支援と、2026年度の診療報酬改定の両方が必要であると訴えています。
診療報酬の改定率は年末の予算編成で決定されます。医療の質と経営の安定を求める医療界と、財政規律を重視する財務省との間で、今後、激しい議論が交わされることになります。
病院経営の現実
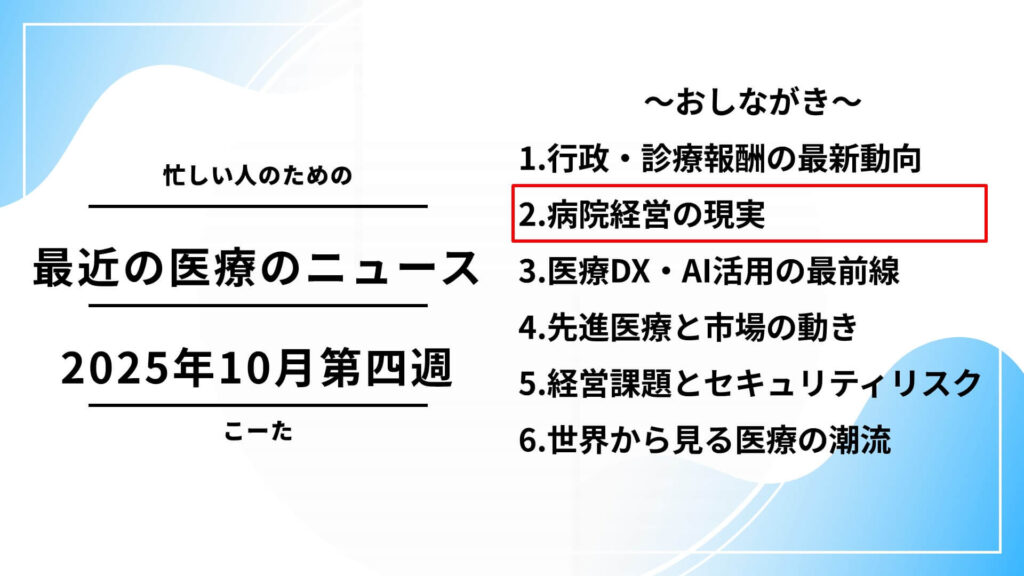
今週のニュースは、日本の医療経営がいかに厳しい局面に立たされているかを浮き彫りにしています。特に目立つのは、地域医療の中核を担う「公立病院」の経営危機です。
兵庫、京都、沖縄、茨城など、地域を問わず「過去最大の赤字」が報じられ、その対策として病床休止や人件費削減といった痛みを伴う判断が下されています。
これは物価高騰、人件費増、そして固定化された診療報酬という構造的な問題が、全国の病院経営を直撃している証拠です。一方で、経営破綻や機能縮小に直面する病院もあれば、新たな資金調達に活路を見出す病院もあり、経営の「現実」が多様化しています。
兵庫県立3病院、130床休止へ:加速する公立病院の経営悪化と機能縮小
兵庫県は10月19日、県立3病院(加古川医療センター、淡路医療センター、がんセンター)で、計130床を一時的に休止することを決定しました。
2024年度の経常損益は128億円の赤字見込みと、コロナ禍以降の受診控えや物価高騰が経営を直撃しています。
対象3病院の病床稼働率が69~78%と低迷していたこともあり、不採算部門を一時的に縮小し、経営効率化を図るという苦渋の決断です。
この決断は人口減少社会において、病院が「規模の維持」から「機能の最適化」へと舵を切らざるを得ない現実を示しています。
京都府立医科大、過去最大35億円の赤字:大学病院も例外ではない構造的赤字
公立病院の経営難は、地域の基幹病院だけに留まりません。京都府立医科大学の運営法人も、2024年度決算で過去最大となる35億8800万円の赤字を計上しました。経常損益ベースでは9年連続の赤字となります。
付属病院の収益は増加したものの、それを上回る勢いで医薬品費や人件費が増加し、診療報酬や交付金でカバーしきれない状態です。
大学法人の担当者が「抜本的な改善は難しい」とコメントしている通り、これは個別の経営努力だけでは解決困難な、構造的な問題であることを示唆しています。
鹿児島県立5病院、未収金1億円超え:連帯保証人代行と債権管理の強化
鹿児島県の県立5病院では、2年連続の赤字(2024年度は24億2500万円)に加え、患者負担分の「未収金」が累計1億円超えという課題も明らかになりました。
経営赤字という大きな問題に加え、入ってきたはずの収益を確実に回収できていない「債権管理」の問題がクローズアップされています。
対策として「連帯保証人代行制度」の導入や「クレジットカード決済」の導入を進めており、病院経営におけるリスク管理と収益確保の取り組みが急務となっています。
沖縄県立病院、人件費削減を要請:賃上げと働き方改革の裏で進む現場負担増
沖縄県立病院では、2024年度に約100億円という巨額の赤字が見込まれる中、ついに「人件費の削減」に踏み込む検討が始まりました。
赤字の理由は他県と同様に物価高騰や患者減ですが、対策として「夜勤体制の見直し」や「退職者の一部補充見送り」が要請されています。
職員の賃上げや働き方改革による採用増が人件費を押し上げた側面もあり、経営改善のために現場職員の負担が増加するという、深刻なジレンマに陥っています。
茨城県立3病院も赤字15億円:給与費増が直撃、収益改善の難しさ
茨城県立の3病院も、2024年度決算で過去最大の15億700万円の赤字を計上しました。最大の要因は、人事委員会勧告による職員給与費が前年度から12億6000万円も大幅に増えたことです。
これは、公立病院特有の課題を象徴しています。物価高騰に合わせて公務員給与が引き上げられる一方、収入源である診療報酬は連動して上がらないため、収支のギャップが自動的に拡大してしまうのです。
国への診療報酬引き上げ要望と並行し、地域医療機関との連携(入院患者の紹介要請)による収益改善を図る方針です。
松本市立病院、分娩廃止を決定:医療事故と医師確保難が招く地域医療の縮小
経営問題は、時として「医療機能の廃止」という形で地域住民に直接的な影響を及ぼします。長野県の松本市立病院は、産科診療の中核である「分娩機能」の廃止を決定しました。
背景には、分娩時の医療事故(7月から分娩中止)に加え、分娩件数の減少(10年で500件超→138件)と、将来的な医師・助産師の確保難があります。
分娩件数が減ることで、現場の「実践的判断能力」が低下したとの指摘もあり、地域の産科医療体制の維持がいかに困難であるかを物語っています。
富山大病院、CFで消化器外科医育成資金1千万円達成:新たな資金調達と医師確保策
暗いニュースが続く中、異なるアプローチで課題解決を図る動きもあります。富山大学付属病院は、消化器外科医の育成資金を募るクラウドファンディングで、第1目標の1千万円を達成しました。
将来的な医師不足を見据え、臨床研究や手術トレーニング、採用活動の費用を、病院本体の運営費ではなく、外部からの寄付で賄おうという試みです。
この試みは、大学病院などが「研究・教育」といった特定の目的のために、新たな資金調達チャネルを開拓する先進的な事例と言えます。
鳴門病院、診療報酬6,460万円を過大請求:内部ガバナンスと算定ルールの再点検
徳島県の鳴門病院で、診療報酬6,460万円の過大請求が発覚しました。国の調査で判明したもので、放射線科の画像診断加算や、産婦人科のハイリスク分娩管理加算の算定要件を満たしていませんでした。
ただでさえ病院経営が厳しい中、こうした過大請求(=返還義務)は経営に大きな打撃を与えます。
診療報酬のルールは非常に複雑ですが、「現場の実態把握が不十分だった」という弁明の通り、院内のガバナンス体制や定期的な算定チェックの仕組みが機能していたか、厳しく問われます。
江別谷藤病院、負債25億円で経営譲渡:給与未払いと事業承継のリアル
公立病院が赤字でも運営が継続できるのに対し、民間病院はよりシビアな現実に直面します。北海道の江別谷藤病院(医療法人社団藤花会)は、医師や職員への給与未払いを経て、札幌の「ライフグループ」に経営権が譲渡されました。
負債総額は約25億円。給与未払いでスタッフが相次いで退職するなど、地域医療に大きな混乱をもたらしました。このケースは、経営難に陥った民間病院が、最終的に経営破綻やM&Aによる事業承継に至る典型的なものだと言えます。
医療DX・AI活用の最前線
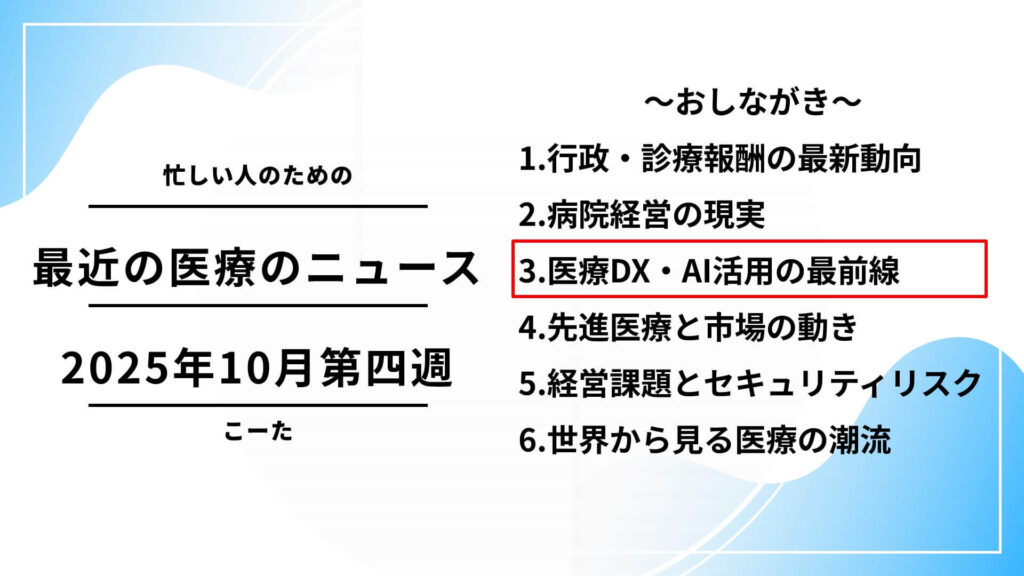
前のセクションでは病院経営の厳しい「現実」を見ましたが、ここでは「未来への投資」に目を向けます。
深刻化する人手不足、業務の非効率性、そして地域医療の格差といった根深い課題を、テクノロジーでどう乗り越えようとしているのか。今週は、現場の負担を直接減らすAIから、医療のあり方そのものを変えかねない遠隔技術まで、具体的なニュースが揃いました。
NECと東京科学大が協定:「バーチャル医療システム」構築と共創コミュニティへの期待
まずは、非常に大きな構想です。NECと東京科学大学が、仮想空間上で医療データを流通させるシステムの構築に向け、協定を締結しました。
これは単なる新製品開発ではなく、「予防から介護までをシームレスに繋ぐ」ためのエコシステムを作ろうという試みです。
具体的には、ウェアラブルデバイスで難病の予兆を掴んだり、医療的ケア児のデータを多職種で共有したり、AIでリハビリを支援したりと、多岐にわたります。
看護記録AI「Caretomo」九州初導入:看護師の業務負担軽減とケアの質向上は両立するか
次に、医療現場の「今、そこにある危機」に直結するソリューションです。長崎県のJCHO諫早総合病院が、看護師の記録作成を支援するAIシステム「Caretomo(ケアトモ)」を九州で初めて導入しました。
看護師が患者さんと会話する音声をAIがリアルタイムで文字起こしし、看護記録(SOAP)の形に自動で整理・要約するものです。
看護業務の中で、記録作成が占める時間は膨大であり、これが看護師の疲弊と残業の大きな原因となっています。
このAI導入の狙いは、まさに「記録業務の時間を削減し、その分を患者ケアに充てる」という、経営と医療の質向上の両立です。
現在は医師の説明時やカンファレンスでも活用されているとのことで、病院全体の情報共有の効率化にも寄与しそうです。これは、IT投資が「スタッフの負担軽減」という形で直接的に経営改善に貢献する好事例です。
気仙沼市「動く診察室」実証実験:診療カー×遠隔診療が拓く医療アクセスの未来
こちらは、医師不足と医療アクセスという地域医療の根本課題に挑む取り組みです。宮城県気仙沼市で、医療機器を積んだ「診療カー」が患者さんのもとへ出向き、医師が遠隔で診療する実証実験が行われました。
このシステムの画期的な点は、「患者さん一人でのオンライン診療」ではなく、「看護師が患者さんの隣にいる」ことです。
現地の医師が「より精度の高い情報が提供してもらえる」と評価している通り、看護師がサポートすることで、医師は遠隔にいながらも質の高い診察が可能になります。
医師不足に悩む地域にとって、これは非常に現実的かつ効果的なモデルです。専門医が都市部の病院にいながら、診療カーを通じて広範な地域の患者を診ることができるようになります。
豪州で世界初の「遠隔ロボット手術」成功:医療格差解消の切り札となるか
「動く診察室」が診断のアクセスを改善するものなら、こちらは「高度治療」のアクセスを根本から変えるニュースです。
オーストラリアのスタートアップ企業が、世界で初めて「完全遠隔操作によるロボット手術」に成功しました。
カナダで実施されたこの脳血管内治療では、遠隔地の医師がロボットカテーテルを操作して施術しました。AIが細い血管内での動作を補助し、通信遅延なども統合的に管理されます。
これは、気仙沼の事例の究極形とも言えます。
専門医がいない地域でも、現地の病院にこのロボットシステムとサポートするスタッフさえいれば、都市部のトップレベルの専門医による手術が受けられる可能性を示しています。
「病院の立地」という制約から、医療が解放される第一歩であり、地域医療格差を解消するゲームチェンジャーとなり得ます。
先進医療と市場の動き
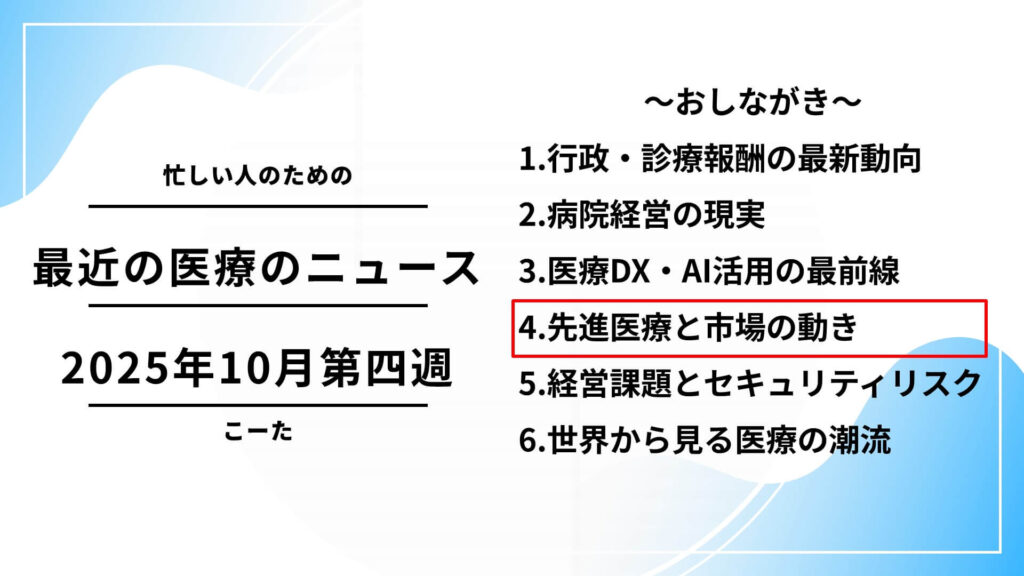
経営の「守り」や「効率化」がDX・AIの主な役割だとすれば、こちらは医療の「攻め」の中核、すなわち治療技術そのものの進化です。
日々の健康管理を支える医療機器の市場動向から、iPS細胞やワクチン開発といった最先端の研究、さらには医療現場の安全と効率を飛躍させる設備投資まで、未来の医療スタンダードを形作る「モノ」と「技術」のトレンドを見ていきます。
オムロン血圧計、世界累計4億台突破:「ゼロイベント」実現に向けたデータヘルス事業
オムロンヘルスケアの家庭用電子血圧計が、世界累計販売台数4億台を突破しました。
1973年の初号機発売以来、世界130カ国以上で普及し、特に3億台達成から4億台まではわずか4年で到達するなど、その普及は加速しています。
背景には、世界の高血圧患者が約13億人に上るなど、生活習慣病の深刻化があります。
このニュースの核心は、単なる「モノ売り」の成功ではありません。同社が掲げる「脳・心血管疾患の発症ゼロ」というビジョンこそが重要です。
近年は健康管理アプリや遠隔診療サービスを拡充しており、これはオムロンが「医療機器メーカー」から、家庭で測定された膨大な血圧データを活用する「データヘルス・プラットフォーマー」へと変貌を遂げていることを示しています。
医療機関側も、こうした院外のデータをいかに診療に取り込み、予防医療に繋げるかが問われています。
弘前大、安全な「ナノ粒子ワクチン」開発:変異株対応と次世代基盤技術への期待
新型コロナウイルスワクチンの分野でも、日本の大学から注目すべき成果が発表されました。
弘前大学の研究グループが、安全性の高い日本脳炎ワクチン由来の粒子を土台に、新型コロナの抗原を結合させた「ナノ粒子ワクチン」を開発しました。
このワクチンの特徴は、少量の抗原で強力な免疫を誘導できる点と、複数の変異株にも効果を示した点です。
これは、単に「新しいコロナワクチンができた」という話に留まりません。この開発手法は、将来発生しうる未知の新興感染症に対しても応用可能な「基盤技術」となり得ます。
こうした基礎研究の蓄積こそが、将来のパンデミックに対する日本の医療防衛力と、国際的な創薬競争における優位性に直結します。
iPS財団、3.8億円の寄付で「小児がん」新研究へ:iPS細胞による治療開発の加速
日本が世界をリードするiPS細胞分野でも、研究を加速させる資金が投じられました。
京都大学iPS細胞研究財団は15日、米国の実業家スティーブン・シュワルツマン氏から約3億8千万円の寄付を受け、iPS細胞を活用した新たながん治療開発を開始すると発表しました。
この寄付は、日本の先端医療に対する海外からの高い期待の表れです。
特に注目すべきは、その使途が「小児がんの治療法開発」である点です。iPS細胞技術が、従来の再生医療だけでなく、がんという難病の治療開発という新たなフェーズに進んでいることを象徴しています。
2028年度の臨床試験開始を目指しており、実用化に向けたスケジュールが具体的に動き出しました。
近畿大学病院、新病棟に「抗がん剤調製ロボット」導入:薬剤師の安全確保と業務効率化
11月1日に開院予定の近畿大学病院の新病棟が報道公開されました。病床数800床という規模もさることながら、導入される最新の医療機器が注目されます。
特に象徴的なのが、医師の処方に基づき「抗がん剤を自動的に調製するロボット」の配備です。
抗がん剤の調製は、わずかな量の違いが患者さんの安全に直結する非常にデリケートな作業であると同時に、薬剤師が有害な薬剤に曝露するリスクも伴いました。
このロボット導入は、医療ミスを防ぐ「医療安全」と、薬剤師を守る「労働安全」、そして服薬指導などの薬剤師の専門業務へのシフトを促す「業務効率化」の三つを同時に実現する、費用対効果の明確な設備投資と言えます。
経営課題とセキュリティリスク
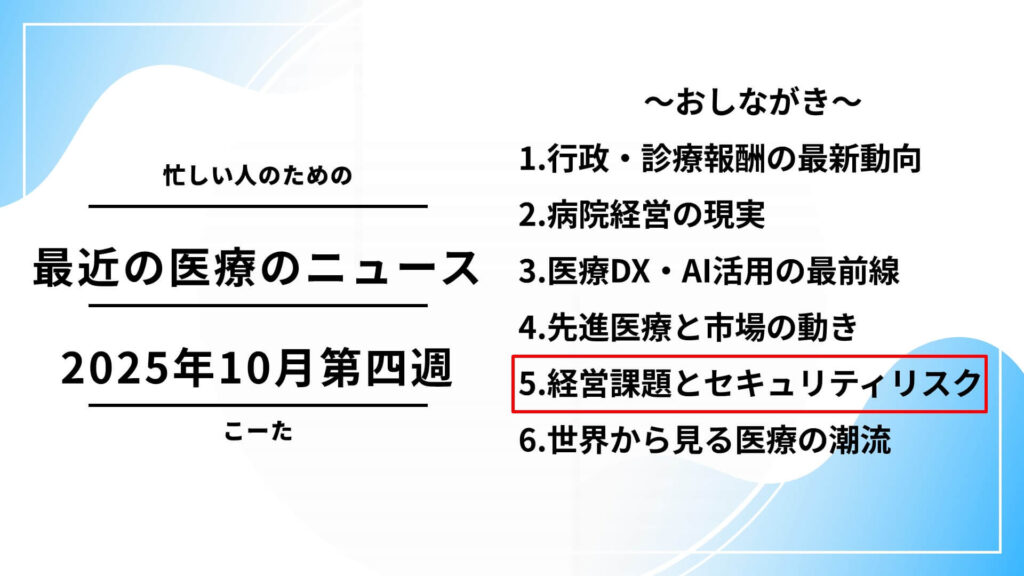
ここまでは病院経営の「収支」や「効率化」に焦点を当ててきましたが、このセクションでは、病院というインフラの「土台」そのものに関わる、より中長期的なリスクについて整理します。
建物の老朽化、地域内での連携、そして見えない脅威であるサイバー攻撃。これらは日々のオペレーション改善とは次元の異なる、経営トップの戦略的決断が求められる重い課題です。
病院倒産、過去最多ペース:4軒に1軒が「築40年超」、老朽化という時限爆弾
まず、病院経営の足元を揺るがす物理的なリスクです。
帝国データバンクの調査によると、2025年上半期の医療機関の倒産は35件と、過去最多のペースで推移していることが報じられました。
この深刻な事態の要因の一つとして、「病院建物の老朽化」が指摘されています。
全国保険医団体連合会によると、実に4軒に1軒(27%、1,623軒)の病院が、築40年以上の病棟を抱えているというのです。
建物が古いと、最新の感染防止対策やICT導入に対応できず、医療の質や効率化の足かせとなります。
しかし、いざ改築しようにも、近年の建築費高騰が経営難に追い打ちをかけ、資金調達が困難になっています。
この危機に対し、保団連は国に対し、老朽化医療機関の改築費用への補助金創設や、既に借り入れで改築した医療機関への残額補助などを求める要望書を提出しました。
診療報酬の引き上げだけでは追いつかない、インフラ維持への抜本的な支援が求められています。
地域医療維持の鍵は「病院間連携」:「地域医療連携推進法人」活用のメリットと課題
個々の病院経営が厳しさを増す中、解決策の一つとして国が活用を促しているのが「地域医療連携推進法人」制度です。
これは、複数の病院やクリニックなどが一つの一般社団法人を設立し、グループとして連携する仕組みです。
認定されると、参加病院間での病床の融通や、医薬品・医療材料の共同購入によるコストダウン、さらには職員の相互派遣などが可能になり、経営の効率化が期待できます。
福島県の例では、病院の約8割が赤字という厳しい状況下で、限られた医療資源を有効活用するために、この「連携」の重要度が増しています。
しかし、各病院が独立性を維持したいという思いもあり、関係機関が危機感を共有し、利害を調整する「まとめ役」の負担が非常に大きくなるという実務上の課題もあります。
「救急搬送が止まる」医療サイバー攻撃:見えざる最大の経営リスク
最後に、物理的な老朽化とは対極にある「情報的」なリスク、サイバー攻撃の脅威です。医療機関は、機密性の高い個人情報を大量に扱うため、サイバー犯罪者の格好の標的となっています。
海外では、米大手医療法人が攻撃を受け救急車の出動が中止されたり、保険請求サービスが停止し身代金2,200万ドルが支払われたりする甚大な被害が発生しています。
日本でも2022年、大阪急性期・総合医療センターがランサムウェア攻撃を受け、約6週間にわたり基幹システムが停止しました。
中核病院が機能停止すれば、その地域全体の救急搬送が受け入れられなくなり、地域医療が麻痺する事態に直結します。
問題は、多くの医療機関、特に中小規模のクリニックでは、セキュリティ専門の人材不足やIT予算の制約から、対策が不十分なままであることです。
診療報酬が公定価格であるため、セキュリティ対策のような「直接収益を生まない投資」は、どうしても優先順位が後回しにされがちな構造的課題を抱えています。
世界から見る医療の潮流
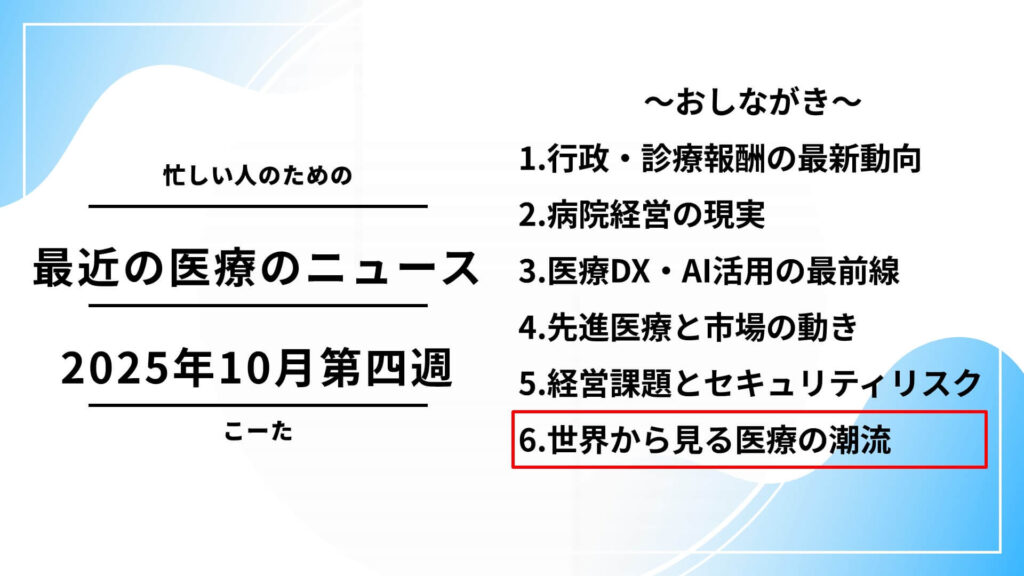
最後に、世界に目を向けてみましょう。
日本国内の制度や経営課題とは異なる文脈で、医療の「倫理」「経済」「政策」が動いています。経済的な困窮が違法な医療ビジネスを生み出す現実、人生の終え方に関する法整備の進展、そして高額な医療費に対する政治的な介入。
こういった動きは、日本の医療の未来を考える上でも重要な示唆を与えてくれます。
ミャンマーで臓器を売る人が急増中:経済混迷が招く違法医療の現実
内戦が続くミャンマーで、経済的な困窮から自らの臓器を売る人が急増しているという、非常にショッキングなニュースです。
クーデター後の失業と借金苦から、多くの人がインドへ渡り、腎臓一つを約25万円で売却しているといいます。問題は、これがブローカーによってシステム化されており、現地の病院や行政、警察も事実上黙認している点です。
これは、経済的な破綻が、医療倫理や法律の境界をいとも簡単に破壊してしまう現実を示しています。日本で議論される「医療インバウンド」とは対極にある、医療ツーリズムの最も暗い側面と言えます。
ウルグアイ、南米初の「安楽死」法成立:尊厳死を巡る世界の議論
変わってこちらは、医療と倫理に関する法整備の最前線です。ウルグアイ上院が15日、「尊厳死法」を可決し、南米で初めて議会立法によって安楽死を合法化した国となりました。
対象は、精神的に健康な成人で、治療不可能な末期疾患にあるか、耐えがたい苦痛を抱える人などに限られます。
特徴的なのは、余命が6ヶ月以内といった具体的な期間の条件がない点や、精神疾患があっても一律に除外せず、医師2名の心理評価を経て決定される点です。
ウルグアイはこれまでもリベラルな政策を推進してきた背景がありますが、「人生の自己決定権」をどこまで認めるかという、日本でも長く議論が続くテーマにおいて、世界が一歩進んだことを示す象徴的な出来事です。
米政府、体外受精(IVF)薬の値下げで合意:関税免除と引き換えの薬価引き下げ
最後は、医療と「政策」「経済」がダイナミックに結びついたニュースです。トランプ米大統領が、体外受精(IVF)で使われる医薬品の値下げについて、製薬会社EMDセローノと合意したと発表しました。
米国では不妊治療が1回あたり数百万円と非常に高額であることが社会問題化しています。
今回の合意は、同社が今後、米国内での医薬品製造に投資することを条件に、政府が「医薬品関税の対象から外す」というものです。この「取引」により、最大で80%以上の薬価引き下げが実現するケースもあるとしています。
国民皆保険制度を持たない米国ならではの高額医療問題と、それに対する政府の非常に直接的な「政治介入」の一例です。薬価の決定において、関税政策というカードが使われた点は特筆すべきです。
おわりに
今週のニュースを概観すると、公立病院の相次ぐ巨額赤字、病床休止、過去最多ペースの病院倒産、そして建物の老朽化やサイバー攻撃といった「経営の危機」が、これ以上ないほど鮮明になりました。
その一方で、再生医療「アクーゴ」の承認、看護記録AIや抗がん剤調製ロボットによる「業務効率化」、さらには遠隔ロボット手術やバーチャル医療システムといった「未来への投資」も具体的に進んでいます。
これは、日本の医療が「待ったなし」の変革期、あるいは厳しい「淘汰」の時代に入ったことを示しています。物価高騰や人件費増といった外部環境の嵐に対し、従来の経営努力だけでは立ち行かなくなっている現実は深刻です。
目先のコスト削減や業務改善(守り)と、AI・DX、医療インバウンド、新たな資金調達(攻め)のバランスをどう取るか。医療機関の経営者の皆様の手腕が、かつてないほど問われています。

ここまでお読みいただきありがとうございました!